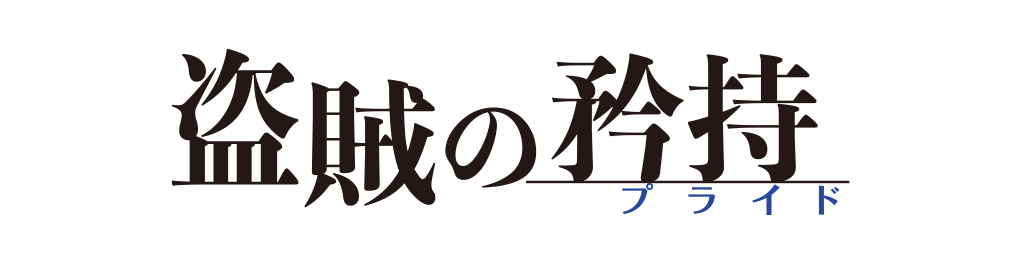10.尖塔から遠く
早朝。ケイは一睡もしないまま、重い足取りで弓師街に向かった。
目指すのは裏通りだ。表通りではない。今はアーティに用はないし、青果店はまだ開店前だろう。あのそばかすの少年や、その他の従業員が市場に果物を買い付けに行ったり、店開きの準備をしたりするにしても、もうしばらく後だ。ましてや〝どもり〟が店に現れるのはずっと遅く、午後になってからというのが常だった。
まだ夜明けから間もないが、それでも銀馬車道と弓師街が交わる交差点には人の行き来があった。早くから現場に向かう大工や、パン焼きの窯に火を入れに行く職人といった類の者たちだ。彼らもまたケイと同様に、やるべきことがある場所へと向かい、交差点に立つ掲示には目もくれなかった。
〝来る本年の夏至祭は〈王都〉を治めるオーグルヴィー大公猊下の在位十五周年にあたり、記念されるべき盛大さをもって執り行われる。例年以上に数多い賓客の来訪が予定され、それら貴賓の方々を敬して受け入れ、歓迎することを猊下は市民らに求めるものである。なお〈皇都〉からはハルグレイヴ侯爵閣下が各種式典への参加を表明しておられ、閣下は恐れ多くも皇帝陛下の祝賀の品を携え……〟
掲示に張り出されている文は、一週間前の正午に布告人が大声でがなり立てていたものと同じ内容だ。
――皇帝陛下の祝賀の品だってよ!
――へっ、それで〈皇都〉が〈王都〉に何をくれるってんだい?
――おおかた鱒の塩漬けとか、そんなんだろうよ!
――ちげぇねぇ。貧乏たらしい〈皇都〉にゃ、そのへんが関の山だろうさ。
〈王都〉育ちは〈皇都〉――この国の首都――を軽く見ていた。これは生まれの貴賤や、裕福か貧乏かを問わない。確かに〈皇都〉は〈王都〉に比べて歴史は浅く、豊かな富をもたらす港湾や多数の交易路を持つわけではないが、皇帝の玉座を抱く国家の枢要として盤石の地位があり、その繁栄も今や〈王都〉に伍すか、あるいは超えるほどなのだ、などと語ったところで、〈王都〉っ子は鼻で笑い飛ばす。
制度の面で見れば〈王都〉の総督――というのが正式な地位だが単に〝統治者〟と呼ばれることが多い――は〈皇都〉の枢密院が大貴族から選んで推挙し、皇帝が承認する形をとるのだが、それが座す〝宮殿〟を目にしたこともない下々の者らは、
「要は一番強ぇ奴が〈王都〉をとるってこったろ」
といった街のごろつきの縄張り争い程度にしか理解していなかった。だが、それはあながち間違いとも言えない。映えある〈王都〉を治めれば大きな利益が得られるものの、象牙色の尖塔に上るのを許されるのは力と富と格式を備え、他と影に日向に争って蹴落とす権謀術数に長けた強者のみである。
――んなことより、十五周年だとさ。
――長ぇな。こりゃ歴代最長じゃないか?
――だろうな。俺は並の御仁じゃねぇって、端っからわかってたぜ!
――ちぇっ、こいつ、ノミ屋で〝次の夏至祭まで大公が留任〟に賭けてるからって調子のいい……。
――しかしオーグルヴィーが強い統治者なのは本当だ。皇帝も大公の意向を無視できないと聞くし、これまで政変二回、暗殺の企て三回も乗り切ってる。
――そう考えると化け物じみてるな、我らが〈王都〉の統治者様はよぉ。
雲は濃く、風強し。掲示の脇に立てられた旗竿には大公家の旗が翻っていた。紋章は真紅の盾に金色の獅子。この国でも屈指の権勢を誇る家門の旗だ。
その旗を背に、ケイは左に折れて弓師街を進む。そしてまたすぐに左の路地に入り、裏通りに出た。
本当は〈雄羊の蹴り足〉の二階で泥のように眠りたかったが、そうもいかない。ダレックの店が閉まってしまう。老故買人は完全に昼夜逆転の生活をしていて、日が昇ってしばらくすると店仕舞いだ。
ダレックは大公が〝宮殿〟に座した時にはすでに老人で、故買人だった。店の場所も変わっていない。弓師街の裏通りから細い路地に入って、もぐりの賭博場の裏手に回る。すると壁に賭博場の裏口の黒い扉があるのだが、その扉を開けても、狭くて天井の低い通路が奥に続いているばかりで賭博場そのものとは繋がっていない。通路はすぐに行き止まりで、左に下り階段がある。それを下りると、傾いて上部に隙間のできたボロボロの扉が現れる。そこがダレックのよろず屋だ。
この、賭博場の地下に間借りして営まれている店が相手にする客は主にふたとおり。
まずは博打狂い。どこの賭博場で賭けたかを問わず、博打で負けておけらになった奴らは、賭け代欲しさに手持ちの品をダレックに売る。そうしてまた性懲りもなく賭け事に興じる。反対に勝った奴らはよろず屋を覗いて目ぼしい物があれば買う。ここは質屋ではないから、あまり期待できないが、以前に売った品を買い戻せることもある。
お次は表沙汰にはできない品を売買する悪党。盗品だろうが密輸品だろうが、詮索することなく買い付け、売りさばき、かつ客の素性を漏らさない、信頼の置ける故買人は〈王都〉に両手の指で数えるほどいるが、ダレックはその中でも古株だった。
ダレックの在位はオーグルヴィーよりもはるかに長い――とケイは思った。
よろず屋が間借りしている賭博場は、ケイが知るだけでも名前が三回変わっており、所有者の入れ替わりはその数倍だ。裏通りの賭博場は実入りがよく、悪党一家の抗争でしばしば奪い合いになる。持ち主がころころと変わっても何ら不思議がなかった。以前の客を引き止めるために屋号は変えないことが多いが、所有権が移る直前に衛士隊のガサ入れがあったとか、血なまぐさい刃傷沙汰の舞台になったとかいった場合には、心機一転で新しい名前になる。そして名が変わるにせよ、そのままにせよ、前の所有者との繋がりは断たれ、なかったことにされる。ハーウェルがただの区名になり、新王の名は削られ、失われたように。
それでもダレックのよろず屋は、地下に居座り続けている。激しく移ろうことが常である〈王都〉で、老故買人だけは流れに抗うがごとくだった。
ケイは、裏通りの酒場の脇にうずくまり、何か意味のわからぬことを喚いては嘔吐している酔っぱらいを尻目に、もぐり賭博場の裏口に向かった。粗悪な密造酒でも飲みすぎたのだろう。酔っぱらいはゼイゼイと荒い呼吸音と、地べたに吐瀉物をまき散らす音を泣き言混じりに朝の空気に響かせている。その体たらくに野良犬が吠えて伴奏をつけた。
裏口の扉にかけられた「営業中」の木のプレートを裏返して「閉店中」にする。
よろず屋に初めて訪れた時、ケイは先客の大男――に見えたが、それはケイが小僧だったからそう錯覚しただけかもしれない――に襟首をつかまれて店内から外の階段に引きずり出され、壁に叩きつけられた。
表の「閉店中」のプレートを見なかったのか、このクソガキが!
思えば、あの大男は親切だった。言葉で説明してくれたのだから。この店に入れんのは一度にひとりだけだ。わきまえやがれ! 次はねぇぞ、こら。
通路と階段は左右の壁に点々とかけられた蝋燭の明かりに照らされていた。あれから何度、ここを行き来したかはわからない。だが、どれほど時が経っても、この狭くて溶けた蠟の臭いが充満する空間は何も変わらないように思える。傾いた店の扉もだ。
ガタつく扉を開けて店内に入ると、カウンター奥にダレックが横を向いて座っていた。カップを手にしている。中身は得体のしれない香りのするお茶だ。
左右の虫食いだらけの木棚には雑然と商品が並んでいた。老人の向こうの棚にもだ。どれもこれも客が売った――あるいは仕方なく手放した――品々である。
たとえば左の上から二段目には、布が張られた小箱に真珠の指輪が置かれていた。ただし、その真珠はよくできてはいるが模造品だ。一方、その隣に立てかけられた弦楽器は、ケイの見立てではなかなかの代物だと思える。博打にうつつを抜かした楽士が泣く泣く売ったのかもしれない。稼ぎ時の夏至祭までに買い戻せりゃいいがな。
さらにカウンター奥の棚で、ダレックの皺だらけの顔に半ば隠れているのは、杉木立ラベルのウィスキー。北から隊商が運んできた樽の酒を〈王都〉の商会がボトル詰めした銘柄で、若い年数のようだが、それでも五、六シェールはするだろう。あまりに安い値段で買えるようなら、ボトルの中身が詰め替えられていると疑ったほうがいい。
他にも様々。天井から吊るされている物もある。
こうした商品に関するあれこれを、老故買人が自ら触れ込むことは一切ない。その品がどんなものなのか、聞けばダレックは抑揚のない声で、
「ヴィオラ。先週、楽団員から買った」
「杉木立ラベル、五年」
などと、つっけんどんに答えてはくれる。とはいえ、この老人は高値を付けるために眉ひとつ動かさずに嘘をつくから、あまり信じないほうが身のためだ。この店は売るにせよ、買うにせよ、ダレックの言い値に従うことになっている。交渉はできない。品物の価値は自分で判断して、納得するなら売るなり買うなりすればいい。買う時に商品の説明など求めたら、さもありそうなことを聞かされて、値段が釣り上がるだけだ。きっとベスにも、
「魔除けの紐。それに触れるほど近くで魔法は使えない。十シェール」
とでも言ったに違いなかった。
ケイは紫の繊維がところどころからはみ出した紐をカウンターに置く。
ダレックは横を向いたまま、目だけ動かして紐を見て、その脇に銅貨を投げた。五パース。
こんな商いを、老人は〈王都〉に囲む壁があった頃から続けているのではないか――小銭がカウンターで跳ねる音を聞いた途端、ふと、ケイはそんな気持ちになった。
馬鹿馬鹿しい夢想だ。
もしそうなら、ダレックは〝破城の戦い〟でハーウェルが討たれ、東の壁に続けて南北の壁が突き崩されるのも、新王と有力諸侯を打倒したソールベリ公が王を名乗ったのも、ソールベリが弑された後も〈王都〉に別の王や、その他の統治者が権力の座に就いては消えたのも、すべて見てきたことになる。
皮肉なことに〈王都〉が真の繁栄を迎えたのは、壁がなくなってからだった。
元より高い経済力と活力、莫大な人口で膨れ上がっていた〈王都〉は、囲んで抑えるものがなくなると、膿腫を針で突いたように内から外へとあふれ出した。版図は広がり、力はいや増し、人が流れ込み続ける。
西は海にせき止められていたが、東へ、北へ、南へ、肥溜めをぶち撒けたように〈王都〉が拡大するのを止められる者はいなかった。そこに集まる富や力は、ますます権勢の頂点を目指す野心家が統治するのに相応しいものになっていった。だが制御はままならず、長く統治を保てない。どんな王や王家が立とうとも、それに取って代わろうとする欲望に駆られた者が現れ、彼らの反逆は成功する。壁なき〈王都〉の守りは薄いのだ。
やがて、この国の王は別の場所に――今の〈皇都〉に首都を置くようになった。
ひょっとしたら、老故買人は遷都が行われ、王なき都市になった後も、〈王都〉には王を名乗る者らが何人も躍り出たのを見てきたのかもしれない。
逆賊が逃げ込み潜むにも、様々な貴族家や有力者と裏で繋がり力をつけるにも、人を集め満を持して挙兵するにも、壁がなく巨大な〈王都〉はもってこいだった。ここで雌伏の時をすごして反旗を翻したうちの何人かは、かつての新王やソールベリのごとく実際に玉座を奪ってみせた。そうした造反劇は、この国が対外戦争で数カ国を飲み込み、南方の諸島を植民地にする一大帝国になって、王が皇帝と称し、首都が〈皇都〉と呼ばれるようになるまでくり返された。
今や皇帝の威光が国土をあまねく照らす。
その影で、なお際限なく肥え太る〈王都〉は過去、数多の王や逆賊を引き寄せ、生み出し、玉座を襲う引き金になってきたことから、決して名誉とは言い難い通り名で呼ばれるようになった。
――〈王都〉、あるいは〝簒奪者の都〟と。
現在、国が帝国になり、枢密院が〝帝国に相応しき〟統治者を〝公明正大に〟選ぶようになってからは、皇帝を狙う逆賊や僭称者は〈王都〉に現れなくなった。しかし、代わりにこの地の統治者の地位をめぐっての謀略はひっきりなしで、誰かが就任するや、ほどなく何者かがそれを奪った。手法は政治工作から端的な暴力まで何でもあり。次の夏至祭で十五年間、〈王都〉総督の位を保とうとしているオーグルヴィーはまれな存在であり、この一大都市の実態は今もってなお〝簒奪者の都〟のままだと言える。
そんな血に塗れて後ろ暗い通り名を〈王都〉で口にする者はいないから、これをケイは知らない。知っていたら、悪くない名だ、と思うだろう。
ケイはカウンターの上から五枚の銅貨を取って懐に収めた。
「他には?」
まったく期待のこもっていない声でダレックが言った。相変わらずカップを手に、横を向いたままだが、目だけはケイを見ている。その右目は糸のように細く、ひっきりなしに痙攣していた。
〝死体がある〟
素早く手信号を送る。
「どっちだ?」
胸の前に手をやって小指だけを折る。
〝女〟
ダレックは茶をすすった。「後で持ってこい」
偽の魔除けの紐にも使い途があったように――あるいはそれ以上に――死体も〈王都〉では使える商品だ。自分や他の誰かが死んだことにしたい奴が買う。借金で首が回らなくなった債務者や、とことん追い詰められた賞金首、暗殺者の裏をかきたい貴族、今の生活を捨てて駆け落ちしようとしている男女。それが女の死体なら、あこぎな娼館から抜け出したい娼婦も手を出すだろう。他にも儀式の生贄? とか医学的な解剖? にも使うとの噂はあるが、それらが何で、何をするのか、ケイは知りたくもなかった。
ホーラーが隠し金を半分奪われて、娼婦のリルだかリリーだかは身請け話が遠のいたことを知ったとしよう。それで人づてに故買人から死体を買うかもしれない。暴漢に殺された――そういうことにした――頭部の潰れた死体を見て、手足は長く均整が取れているが、リルだかリリーだかにしては背丈が足りないと、女主人は即座に見抜くものの、館の一番人気が男の下に走るのを許す。「馬鹿な娘だね」と溜め息をついて。
ケイはよろず屋から出た。
今夜、日が昇る少し前、弓師街の裏通りにもほとんどひとけがなくなる頃に、乾いた汚水溝に隠したベスの死体を布に包んで持って行かなければならない。左胸の乳房の下に隠れて小さな傷だけがある死体は使い勝手がよく、それなりの値で売れるはずだ。
階段を上がり、通路を抜けて、裏口の扉から外へ。
木のプレートを裏返して「営業中」にした。
たぶん、この後すぐに老故買人は穴蔵のような店から出て、扉に鍵をかけ、本当に「閉店中」にするのだろうが、客は出入り時にプレートを必ず裏返すのが決まりだ。
汚れた空に厚い雲が立ち込め、強い風に煽られても、その場に淀んで流れる様子がない。夜には雨になるかもしれなかった。
初夏には珍しいが、土砂降りになったら、乾いていた汚水溝に水が溜まり、隠した死体が浮かび上がってしまうこともありそうだ。少し早めに回収しに行ったほうがいいだろう。
――それまでは〈雄羊の蹴り足〉二階の部屋でひとり、眠りたい。
雨で濡れても透けない、濃い色の布が必要だ。それで死体をくるんで麻糸で縛る。濡れて重くなった大きな包みを抱えたり、背負ったりして運ぶのは――人目を避けてだからなおさら――骨が折れる。今日は夜まで寝て、少しでも休んでおくべきだ。
路地から裏通りに出ると、酔っぱらいのろれつの回らぬ声が聞こえた。なんでだ、どうしてこうなっちまうんだ……。ひたすらクダを巻き、嗚咽するのが響く。〈王都〉ではお定まりの、野良犬の伴奏つきの泣き言。なぜ、こうなるのか、俺だけがそうなのか、誰もがそうなのか、納得できない。ちくしょう、信じるものか、どうしてこんな――。
――だが、他にどうありえよう?
背負い袋に金貨の重みを感じる。本当なら腰の左右の袋にあったはずだが、それを言うのは詮なきことだ。
ケイは口を一文字につぐんだまま、決してそこから見えはしない〝宮殿〟の象牙色の尖塔から遠ざかる方角へ、疲れた足を引きずるように歩いていった。
目指すのは裏通りだ。表通りではない。今はアーティに用はないし、青果店はまだ開店前だろう。あのそばかすの少年や、その他の従業員が市場に果物を買い付けに行ったり、店開きの準備をしたりするにしても、もうしばらく後だ。ましてや〝どもり〟が店に現れるのはずっと遅く、午後になってからというのが常だった。
まだ夜明けから間もないが、それでも銀馬車道と弓師街が交わる交差点には人の行き来があった。早くから現場に向かう大工や、パン焼きの窯に火を入れに行く職人といった類の者たちだ。彼らもまたケイと同様に、やるべきことがある場所へと向かい、交差点に立つ掲示には目もくれなかった。
〝来る本年の夏至祭は〈王都〉を治めるオーグルヴィー大公猊下の在位十五周年にあたり、記念されるべき盛大さをもって執り行われる。例年以上に数多い賓客の来訪が予定され、それら貴賓の方々を敬して受け入れ、歓迎することを猊下は市民らに求めるものである。なお〈皇都〉からはハルグレイヴ侯爵閣下が各種式典への参加を表明しておられ、閣下は恐れ多くも皇帝陛下の祝賀の品を携え……〟
掲示に張り出されている文は、一週間前の正午に布告人が大声でがなり立てていたものと同じ内容だ。
――皇帝陛下の祝賀の品だってよ!
――へっ、それで〈皇都〉が〈王都〉に何をくれるってんだい?
――おおかた鱒の塩漬けとか、そんなんだろうよ!
――ちげぇねぇ。貧乏たらしい〈皇都〉にゃ、そのへんが関の山だろうさ。
〈王都〉育ちは〈皇都〉――この国の首都――を軽く見ていた。これは生まれの貴賤や、裕福か貧乏かを問わない。確かに〈皇都〉は〈王都〉に比べて歴史は浅く、豊かな富をもたらす港湾や多数の交易路を持つわけではないが、皇帝の玉座を抱く国家の枢要として盤石の地位があり、その繁栄も今や〈王都〉に伍すか、あるいは超えるほどなのだ、などと語ったところで、〈王都〉っ子は鼻で笑い飛ばす。
制度の面で見れば〈王都〉の総督――というのが正式な地位だが単に〝統治者〟と呼ばれることが多い――は〈皇都〉の枢密院が大貴族から選んで推挙し、皇帝が承認する形をとるのだが、それが座す〝宮殿〟を目にしたこともない下々の者らは、
「要は一番強ぇ奴が〈王都〉をとるってこったろ」
といった街のごろつきの縄張り争い程度にしか理解していなかった。だが、それはあながち間違いとも言えない。映えある〈王都〉を治めれば大きな利益が得られるものの、象牙色の尖塔に上るのを許されるのは力と富と格式を備え、他と影に日向に争って蹴落とす権謀術数に長けた強者のみである。
――んなことより、十五周年だとさ。
――長ぇな。こりゃ歴代最長じゃないか?
――だろうな。俺は並の御仁じゃねぇって、端っからわかってたぜ!
――ちぇっ、こいつ、ノミ屋で〝次の夏至祭まで大公が留任〟に賭けてるからって調子のいい……。
――しかしオーグルヴィーが強い統治者なのは本当だ。皇帝も大公の意向を無視できないと聞くし、これまで政変二回、暗殺の企て三回も乗り切ってる。
――そう考えると化け物じみてるな、我らが〈王都〉の統治者様はよぉ。
雲は濃く、風強し。掲示の脇に立てられた旗竿には大公家の旗が翻っていた。紋章は真紅の盾に金色の獅子。この国でも屈指の権勢を誇る家門の旗だ。
その旗を背に、ケイは左に折れて弓師街を進む。そしてまたすぐに左の路地に入り、裏通りに出た。
本当は〈雄羊の蹴り足〉の二階で泥のように眠りたかったが、そうもいかない。ダレックの店が閉まってしまう。老故買人は完全に昼夜逆転の生活をしていて、日が昇ってしばらくすると店仕舞いだ。
ダレックは大公が〝宮殿〟に座した時にはすでに老人で、故買人だった。店の場所も変わっていない。弓師街の裏通りから細い路地に入って、もぐりの賭博場の裏手に回る。すると壁に賭博場の裏口の黒い扉があるのだが、その扉を開けても、狭くて天井の低い通路が奥に続いているばかりで賭博場そのものとは繋がっていない。通路はすぐに行き止まりで、左に下り階段がある。それを下りると、傾いて上部に隙間のできたボロボロの扉が現れる。そこがダレックのよろず屋だ。
この、賭博場の地下に間借りして営まれている店が相手にする客は主にふたとおり。
まずは博打狂い。どこの賭博場で賭けたかを問わず、博打で負けておけらになった奴らは、賭け代欲しさに手持ちの品をダレックに売る。そうしてまた性懲りもなく賭け事に興じる。反対に勝った奴らはよろず屋を覗いて目ぼしい物があれば買う。ここは質屋ではないから、あまり期待できないが、以前に売った品を買い戻せることもある。
お次は表沙汰にはできない品を売買する悪党。盗品だろうが密輸品だろうが、詮索することなく買い付け、売りさばき、かつ客の素性を漏らさない、信頼の置ける故買人は〈王都〉に両手の指で数えるほどいるが、ダレックはその中でも古株だった。
ダレックの在位はオーグルヴィーよりもはるかに長い――とケイは思った。
よろず屋が間借りしている賭博場は、ケイが知るだけでも名前が三回変わっており、所有者の入れ替わりはその数倍だ。裏通りの賭博場は実入りがよく、悪党一家の抗争でしばしば奪い合いになる。持ち主がころころと変わっても何ら不思議がなかった。以前の客を引き止めるために屋号は変えないことが多いが、所有権が移る直前に衛士隊のガサ入れがあったとか、血なまぐさい刃傷沙汰の舞台になったとかいった場合には、心機一転で新しい名前になる。そして名が変わるにせよ、そのままにせよ、前の所有者との繋がりは断たれ、なかったことにされる。ハーウェルがただの区名になり、新王の名は削られ、失われたように。
それでもダレックのよろず屋は、地下に居座り続けている。激しく移ろうことが常である〈王都〉で、老故買人だけは流れに抗うがごとくだった。
ケイは、裏通りの酒場の脇にうずくまり、何か意味のわからぬことを喚いては嘔吐している酔っぱらいを尻目に、もぐり賭博場の裏口に向かった。粗悪な密造酒でも飲みすぎたのだろう。酔っぱらいはゼイゼイと荒い呼吸音と、地べたに吐瀉物をまき散らす音を泣き言混じりに朝の空気に響かせている。その体たらくに野良犬が吠えて伴奏をつけた。
裏口の扉にかけられた「営業中」の木のプレートを裏返して「閉店中」にする。
よろず屋に初めて訪れた時、ケイは先客の大男――に見えたが、それはケイが小僧だったからそう錯覚しただけかもしれない――に襟首をつかまれて店内から外の階段に引きずり出され、壁に叩きつけられた。
表の「閉店中」のプレートを見なかったのか、このクソガキが!
思えば、あの大男は親切だった。言葉で説明してくれたのだから。この店に入れんのは一度にひとりだけだ。わきまえやがれ! 次はねぇぞ、こら。
通路と階段は左右の壁に点々とかけられた蝋燭の明かりに照らされていた。あれから何度、ここを行き来したかはわからない。だが、どれほど時が経っても、この狭くて溶けた蠟の臭いが充満する空間は何も変わらないように思える。傾いた店の扉もだ。
ガタつく扉を開けて店内に入ると、カウンター奥にダレックが横を向いて座っていた。カップを手にしている。中身は得体のしれない香りのするお茶だ。
左右の虫食いだらけの木棚には雑然と商品が並んでいた。老人の向こうの棚にもだ。どれもこれも客が売った――あるいは仕方なく手放した――品々である。
たとえば左の上から二段目には、布が張られた小箱に真珠の指輪が置かれていた。ただし、その真珠はよくできてはいるが模造品だ。一方、その隣に立てかけられた弦楽器は、ケイの見立てではなかなかの代物だと思える。博打にうつつを抜かした楽士が泣く泣く売ったのかもしれない。稼ぎ時の夏至祭までに買い戻せりゃいいがな。
さらにカウンター奥の棚で、ダレックの皺だらけの顔に半ば隠れているのは、杉木立ラベルのウィスキー。北から隊商が運んできた樽の酒を〈王都〉の商会がボトル詰めした銘柄で、若い年数のようだが、それでも五、六シェールはするだろう。あまりに安い値段で買えるようなら、ボトルの中身が詰め替えられていると疑ったほうがいい。
他にも様々。天井から吊るされている物もある。
こうした商品に関するあれこれを、老故買人が自ら触れ込むことは一切ない。その品がどんなものなのか、聞けばダレックは抑揚のない声で、
「ヴィオラ。先週、楽団員から買った」
「杉木立ラベル、五年」
などと、つっけんどんに答えてはくれる。とはいえ、この老人は高値を付けるために眉ひとつ動かさずに嘘をつくから、あまり信じないほうが身のためだ。この店は売るにせよ、買うにせよ、ダレックの言い値に従うことになっている。交渉はできない。品物の価値は自分で判断して、納得するなら売るなり買うなりすればいい。買う時に商品の説明など求めたら、さもありそうなことを聞かされて、値段が釣り上がるだけだ。きっとベスにも、
「魔除けの紐。それに触れるほど近くで魔法は使えない。十シェール」
とでも言ったに違いなかった。
ケイは紫の繊維がところどころからはみ出した紐をカウンターに置く。
ダレックは横を向いたまま、目だけ動かして紐を見て、その脇に銅貨を投げた。五パース。
こんな商いを、老人は〈王都〉に囲む壁があった頃から続けているのではないか――小銭がカウンターで跳ねる音を聞いた途端、ふと、ケイはそんな気持ちになった。
馬鹿馬鹿しい夢想だ。
もしそうなら、ダレックは〝破城の戦い〟でハーウェルが討たれ、東の壁に続けて南北の壁が突き崩されるのも、新王と有力諸侯を打倒したソールベリ公が王を名乗ったのも、ソールベリが弑された後も〈王都〉に別の王や、その他の統治者が権力の座に就いては消えたのも、すべて見てきたことになる。
皮肉なことに〈王都〉が真の繁栄を迎えたのは、壁がなくなってからだった。
元より高い経済力と活力、莫大な人口で膨れ上がっていた〈王都〉は、囲んで抑えるものがなくなると、膿腫を針で突いたように内から外へとあふれ出した。版図は広がり、力はいや増し、人が流れ込み続ける。
西は海にせき止められていたが、東へ、北へ、南へ、肥溜めをぶち撒けたように〈王都〉が拡大するのを止められる者はいなかった。そこに集まる富や力は、ますます権勢の頂点を目指す野心家が統治するのに相応しいものになっていった。だが制御はままならず、長く統治を保てない。どんな王や王家が立とうとも、それに取って代わろうとする欲望に駆られた者が現れ、彼らの反逆は成功する。壁なき〈王都〉の守りは薄いのだ。
やがて、この国の王は別の場所に――今の〈皇都〉に首都を置くようになった。
ひょっとしたら、老故買人は遷都が行われ、王なき都市になった後も、〈王都〉には王を名乗る者らが何人も躍り出たのを見てきたのかもしれない。
逆賊が逃げ込み潜むにも、様々な貴族家や有力者と裏で繋がり力をつけるにも、人を集め満を持して挙兵するにも、壁がなく巨大な〈王都〉はもってこいだった。ここで雌伏の時をすごして反旗を翻したうちの何人かは、かつての新王やソールベリのごとく実際に玉座を奪ってみせた。そうした造反劇は、この国が対外戦争で数カ国を飲み込み、南方の諸島を植民地にする一大帝国になって、王が皇帝と称し、首都が〈皇都〉と呼ばれるようになるまでくり返された。
今や皇帝の威光が国土をあまねく照らす。
その影で、なお際限なく肥え太る〈王都〉は過去、数多の王や逆賊を引き寄せ、生み出し、玉座を襲う引き金になってきたことから、決して名誉とは言い難い通り名で呼ばれるようになった。
――〈王都〉、あるいは〝簒奪者の都〟と。
現在、国が帝国になり、枢密院が〝帝国に相応しき〟統治者を〝公明正大に〟選ぶようになってからは、皇帝を狙う逆賊や僭称者は〈王都〉に現れなくなった。しかし、代わりにこの地の統治者の地位をめぐっての謀略はひっきりなしで、誰かが就任するや、ほどなく何者かがそれを奪った。手法は政治工作から端的な暴力まで何でもあり。次の夏至祭で十五年間、〈王都〉総督の位を保とうとしているオーグルヴィーはまれな存在であり、この一大都市の実態は今もってなお〝簒奪者の都〟のままだと言える。
そんな血に塗れて後ろ暗い通り名を〈王都〉で口にする者はいないから、これをケイは知らない。知っていたら、悪くない名だ、と思うだろう。
ケイはカウンターの上から五枚の銅貨を取って懐に収めた。
「他には?」
まったく期待のこもっていない声でダレックが言った。相変わらずカップを手に、横を向いたままだが、目だけはケイを見ている。その右目は糸のように細く、ひっきりなしに痙攣していた。
〝死体がある〟
素早く手信号を送る。
「どっちだ?」
胸の前に手をやって小指だけを折る。
〝女〟
ダレックは茶をすすった。「後で持ってこい」
偽の魔除けの紐にも使い途があったように――あるいはそれ以上に――死体も〈王都〉では使える商品だ。自分や他の誰かが死んだことにしたい奴が買う。借金で首が回らなくなった債務者や、とことん追い詰められた賞金首、暗殺者の裏をかきたい貴族、今の生活を捨てて駆け落ちしようとしている男女。それが女の死体なら、あこぎな娼館から抜け出したい娼婦も手を出すだろう。他にも儀式の生贄? とか医学的な解剖? にも使うとの噂はあるが、それらが何で、何をするのか、ケイは知りたくもなかった。
ホーラーが隠し金を半分奪われて、娼婦のリルだかリリーだかは身請け話が遠のいたことを知ったとしよう。それで人づてに故買人から死体を買うかもしれない。暴漢に殺された――そういうことにした――頭部の潰れた死体を見て、手足は長く均整が取れているが、リルだかリリーだかにしては背丈が足りないと、女主人は即座に見抜くものの、館の一番人気が男の下に走るのを許す。「馬鹿な娘だね」と溜め息をついて。
ケイはよろず屋から出た。
今夜、日が昇る少し前、弓師街の裏通りにもほとんどひとけがなくなる頃に、乾いた汚水溝に隠したベスの死体を布に包んで持って行かなければならない。左胸の乳房の下に隠れて小さな傷だけがある死体は使い勝手がよく、それなりの値で売れるはずだ。
階段を上がり、通路を抜けて、裏口の扉から外へ。
木のプレートを裏返して「営業中」にした。
たぶん、この後すぐに老故買人は穴蔵のような店から出て、扉に鍵をかけ、本当に「閉店中」にするのだろうが、客は出入り時にプレートを必ず裏返すのが決まりだ。
汚れた空に厚い雲が立ち込め、強い風に煽られても、その場に淀んで流れる様子がない。夜には雨になるかもしれなかった。
初夏には珍しいが、土砂降りになったら、乾いていた汚水溝に水が溜まり、隠した死体が浮かび上がってしまうこともありそうだ。少し早めに回収しに行ったほうがいいだろう。
――それまでは〈雄羊の蹴り足〉二階の部屋でひとり、眠りたい。
雨で濡れても透けない、濃い色の布が必要だ。それで死体をくるんで麻糸で縛る。濡れて重くなった大きな包みを抱えたり、背負ったりして運ぶのは――人目を避けてだからなおさら――骨が折れる。今日は夜まで寝て、少しでも休んでおくべきだ。
路地から裏通りに出ると、酔っぱらいのろれつの回らぬ声が聞こえた。なんでだ、どうしてこうなっちまうんだ……。ひたすらクダを巻き、嗚咽するのが響く。〈王都〉ではお定まりの、野良犬の伴奏つきの泣き言。なぜ、こうなるのか、俺だけがそうなのか、誰もがそうなのか、納得できない。ちくしょう、信じるものか、どうしてこんな――。
――だが、他にどうありえよう?
背負い袋に金貨の重みを感じる。本当なら腰の左右の袋にあったはずだが、それを言うのは詮なきことだ。
ケイは口を一文字につぐんだまま、決してそこから見えはしない〝宮殿〟の象牙色の尖塔から遠ざかる方角へ、疲れた足を引きずるように歩いていった。
〈了〉
メッセージを送る!