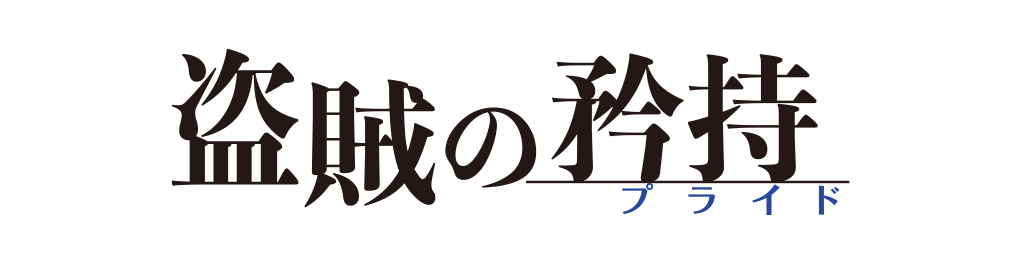5.闇に跳ぶ
二日後の夜。ケイは石工ヶ辻の冴えない建物の屋根の上から、しばし遠くを眺めていた。
〈王都〉には市街を囲む壁がない。
これは珍しい。この国で都市と言えば、繁栄しているにせよ、衰退しているにせよ、たいていは壁に囲まれた城郭都市で、それらの囲壁はこの国の歴史、血なまぐさい歴史の隠し切れない残響だった。
国がまだ国ではなかった時代、野心を胸に抱いた者らが奮い立ち、軍を率いて盛んに争い、他の砦や集落を攻略した。勝者は領土と権勢を増し、拠点を村から町へ、町から都市へと変えていく。それを受け継ぐ子や孫の世代になれば、より大きく、より豊かな都市の奪い合いだ。戦いに備え、都市は壁で囲まなければならない――滅亡や追放の憂き目に遭いたくなければ。
壁があってもなお、初期の攻防から数世代経つまでに数多の都市が滅んだ。生き延びた都市がいっそう富み栄える傍らに、いつの日にかの再生を夢見る廃墟が横たわる。そしてついに数個の都市が大都市に育ち、壁の高さも頂点に達そうかという頃、その内側の権力の座に蠢く者どもは〝貴族〟と呼ばれるようになり、他の貴族を圧倒して〝王〟と称する者も現れた。王の名の下に国は国となって、王は大都市から国民に号令を発する。
昔々、〈王都〉には王がいて、囲む壁もあった。
――今はない。
壁のない〈王都〉で〝壁抜け〟が何だというのだ?
決行の夜、ケイは少し苛立っていた。出発前に〈雄羊の蹴り足〉で、ベスに例の魔除けの紐を押しつけられたからだ。
「こいつはあんたが持っといてよ」
「いらない」
そんな物よりも、今夜のベスがナイフより大きな武器を持っていないことがケイには大事だった。
アーティは夜回りの数は増えていないと言ったが、それでも〝下の道〟で衛士に呼び止められる可能性はある。そうなったら面倒だ。
〈王都〉では路上で無許可の武器携帯は違法だ。小さなナイフは誰もが鞘に入れて腰に下げていたり、ブーツに差していたりするのだが、その程度なら〝道具〟として見逃される。とはいえ何が武器で、何が道具なのかの区分はひどく曖昧である。少し刃渡りの長い得物や、重そうな警棒、頭の反対側が尖ったハンマーあたりを夜の街で持っていれば、衛士に四の五の言われて詰所にしょっぴかれてもおかしくない。要は許すも許さぬも奴らの虫の居所次第だ。
「そんなら、これだけさ」
ベスはふてくされた顔で外套を手に取り、左の内側に鞘入りで収めたナイフを見せた。それが正解だ。衛士に咎められず、いざという時に役に立ち、投げることもできる。
「それでいい。まずは下からお前が来ないことには、始まるものも始まらないからな」
「わかってる、わかってるよ」
ベスは顔をしかめる。
仮に荒っぽい仕事をするとしても、ケイはベスに長い刃物は持たせなかっただろう。ろくに訓練もしていない素人が片手で扱える武器は、頑張って自分の肘から拳先の長さまで。それを超える得物は怪我の元だ。
何にせよ、今夜の計画はケイとベス、ふたり揃うことが前提で、どちらかでも欠けたらおじゃんだ。
「〝壁抜け〟なら、ひとりでやるんだろうけど――」
「ひとりでやれることなんざ、たかが知れてる」
ケイは吐き捨てた。
「――ね、だからだよ。だから、これはあんたが持っててって言ってるのさ」
ベスは怪しい紐の束を握ってケイに突きつける。ふたりでやる仕事でも、ほとんどはそれぞれが別行動。万が一、ひとりで〝壁抜け〟に出くわすとすれば、その可能性はケイのほうが高い。
これはそのとおりだった。
盗賊は盗賊のやり方で仕事をする。手際よく事を運ぼうとすれば手口が似るのは当然で、盗賊同士の計画は重なりやすい。狙い、日取り、経路、警備をどうかわして、どこを探すのか――。その結果、どこかで他の盗賊とかち合った時、一方がどうぞどうぞと譲ることはまず期待できない。ほぼ間違いなく、ひと悶着起きる。現場ではできるだけ避けたい事態だ。
結局のところ、盗みは早いもの勝ち。同業者よりもお先に獲物をかっさらうのが一番――なのだが、今回は他人が狙っている家に忍び込むという話である。 そいつはケイと同じように考え、同じ夜に、同じ経路を辿って、同じ振る舞いをするかもしれない。
「捕り物でもさせる気か?」
「んなわけないよ。でも、もしも……」
もしも俺が〝壁抜け〟を縛り上げたら、俺よりそいつと組みたくなるんじゃないか? とケイは嫌味を言おうとして、止めた。相棒と揉めるのは仕事に差し障る。
ケイは紐を自分の腰に吊るした。ベルトには他にもいろいろと道具を吊るさなければならないが、このくらいは問題ない。
ベスは破顔する。
そもそもこの仕事はベスが見つけてきたのだ。少しくらい言い分を聞いてやってもいいだろう。それで気が済むのなら――ケイは〝壁抜け〟と鉢合わせするとは思っていなかった。〝果物屋〟の取り巻きの放言にこうも煩わされるのは癪だが、そこには目をつぶる。これで今夜、仕入れがうまくいったら、アーティには迷惑料を上乗せして買わせるさ。
屋根の上から〈雄羊の蹴り足〉のある方角を眺めるうちに、ケイの苛立ちも収まってきた。
汚れた夜空の下、〈王都〉の外周に向かって徐々に低くなる屋根の連なりは暗く凪いだ海のように見えた。ところどころに影になって浮かぶ高い建築は島だ。ケイは河口の港から小さな船で近海に出たことがあるばかりで、遠洋にはからきし馴染みがなかったが、漁船や商船などに乗って大海原を行く船乗りたちに漠然とした、一方的な親近感を抱いていた。船乗りは頼るものなき無辺の空間で、独自の規律に従い、独特な言葉と道具を使い、自らの領分に応じて稼ぐ。盗賊も同じだ。
いずれベスも気づくだろう。
王なき〈王都〉に囲む壁はなく、それを〝抜ける〟も〝抜けない〟もない。どこまでも広がるここで盗れるものを盗る――あるのはそれだけだ。しかし、こういうことは話しても無駄で、ベスが自分の力で屋根まで登り、この光景を眺めて実感する他にない。
それにはまだ、しばらくかかりそうだが――とケイは思った。
望むままに高い建物の屋根に登りたければ、鈎縄の扱いを覚える必要がある。この夜、ケイは鈎縄を使い、ホーラーの別邸から少し離れた住宅の屋根に登った。暗闇の中、建物と建物の間の狭苦しい所からでも、狙ったとおりに鈎縄を投げられて、一発で鈎を引っかけられるようになるには相応の経験がいる。もちろん最初からやすやすとこなして見せる者もいるが、残念ながらベスはそうではなかった。
「本当にこれ、使えんの?」
「使える」
以前、樫ヶ橋通り裏の小さな空き地で、ものは試しにベスに投げさせた鉤縄は、廃屋の屋根のどこにも引っかからずにあっけなく滑り落ちた。最初はそんなものだ。鈎を窓にぶち込んだり、あらぬ所に引っかけて回収不能にしたりしないだけ、ベスはましなほうだった。
ケイは手にした鈎縄を頭上で小さく三回転させ、屋根めがけて放った。そして縄を手に両足を壁にかけて体を浮かせ、しっかり鈎がかかっていることを示す。
目を丸くしているベスの前で、地面に降りたケイは片手で縄を素早く上下に振り、鈎を外して取り戻した。縄の張りを活かして手元で鈎を回収することも、覚えなければならない技のひとつだ。これができなければ登った時はいいが、降りた時に鈎縄が置き去りになってしまう。
「ちくしょう、こっちは得意なのになあ!」
ベスは外套の内からナイフを抜き、振り返って木塀に投げた。
乾いた音を立てて、ナイフが突き刺さる。
いい腕だ。癖のない投げ方でナイフはまっすぐに飛んだ。これなら目標に深く刺さる。
「それができるなら、鉤縄も使えるようになる」
ケイは笑った。
気休めではない。ベスは鈎の投げ方も悪くなかった。
だが、仮に登れるようになったとしても、〝上の道〟を行くために覚える技は他にもある。
たとえば明かりがなくとも、周囲の建物も含めて、窓や煙突などの位置と構造を把握すること、スレート葺きで足を滑らせないこと、傾斜のきつい切妻屋根の上でも自在に動き回れること、屋根やバルコニーの縁に指をかけてぶら下がれること、そして――。
〝跳ぶ〟こと。
ケイは出窓で張り出した壁に右手を突き、強く押して勢いをつけると、二歩の助走で跳躍した。
一瞬、焦げ茶の外套が闇を裂き、裾がはためく。
音もなく隣家の屋根に着地して、ケイはゆっくり大きく息を吸った。〝上の道〟は〝跳ぶ〟こと抜きには語れない。屋根と屋根は繋がっていないから……。気取って〝空の道〟と呼ぶ盗賊もいるほどだ。
今夜の侵入経路は計五回、〝跳ぶ〟ことを要する。
その中で最も危険なのは、ケイが今、跳んでみせた四回目だった。距離の離れた次の屋根に着地できるのはそこだけなのに、助走する余地がほとんどない。屋根の縁を蹴る脚のばねが足りなかったり、空中に身を投げ出すタイミングがずれたりすれば真っ逆さまだ。落ちて地面に叩きつけられ骨折で済めばよいほうで、打ちどころが悪ければ死ぬ。盗賊にとって高所からの転落は、自らの技量の低さを証明する物笑いの種だった。
〈王都〉育ちなら、昔話の〝干物ドノバン〟、または〝ぶらりドノバン〟を聞いたことがあるはずだ。盗賊のドノバンは御殿の屋根から落ちて、返しが付いた鋭い鉄柵の先端に下顎を貫かれてしまった。朝になって、ドノバンは乾物屋に吊るされた魚の干物のように鉄柵にぶら下がった姿で見つかり、間抜けな泥棒としてそのまま晒しものになった。そんなドノバンの足が地面に着いたのは、本当にぼろぼろの干物になって、突き刺さった柵から顎が外れてようやくだったという。風が吹くたび、ぶらーん、ぶらんとドノバンぶらり――。街の餓鬼どもが「おい、ドノバンになるなよ」とほざくのは「ヘマをするな」と不良仲間に警告しているのだ。
ケイは、ドノバンほど運に見放されたわけではないが、落ちて腰を強く打ち、二度と〝跳ぶ〟ことができなくなった奴、跳んだはいいが距離が足りず、すぐ下のバルコニーに突っ込んで腕の骨を折った奴、着地で大きな音を立ててしまい、見張りに気づかれて捕まった奴など、難所でしくじった盗賊の話を幾つも知っていた。
だから今はまだ、ベスと一緒に〝上の道〟を行くことはできない……。
最後の、五回目の跳躍はあっさりしたものだった。
下見の時に確認した、ごく細い路地を跳んでホーラー別邸の黒い屋根に渡るだけ――〝跳ぶ〟というより〝跨ぐ〟感覚に近い。
この下の路地にベスが来る。
別邸の屋根の上で、ケイは背負い袋から太い蝋燭と、外側に革が張られた小さな缶を取り出した。蝋燭を腰に下げていた粗末な針金の蝋燭立てに挿して、缶に入った炭の種火で火を灯す。ベスへの合図だ。ベスは近くの地上の物陰から、こちらをじっと見ているはずで、ベスだけが蝋燭の小さな光を目にするだろう。真夜中の住宅街で建物を見上げる通行人はまずいない。衛士もだ。奴らは〝上の道〟のことを知らないはずがないのに無視している。下の見落としは隊長から叱責されるが、上については幾らでも言い訳できるからだ。はっ! しかし我々の職務は管轄内の街路を警戒することにありまして、そこは範囲外なのであります(屋根に賊を見つけたって、賄賂をせびることもできないからなあ)。
ケイは邸内への侵入の準備を始めた。
腰の管のような鞘から〝T字釘〟を抜く。
これは、かなり太くて長い釘の頭が、拳の幅ほどの長さの更に太い横棒になっている代物で、その形からケイが名づけた道具だ。腰の物なのでナイフだと思ったベスに見せたことはあるが、使い方は詳らかにしていない。
真下にある三階の窓のひとつを見計らい、ケイは位置を定めて屋根に葺かれたスレートとスレートの間に〝T字釘〟の鋭い先端を当て、軽く体重をかけるようにして横棒を手のひらで押し、ねじ込んだ。これは後で外しやすいように軽く刺すだけでいい。そしてベルトに挟んだ糸巻き棒を出して、ちょうどいい長さだけ太い麻糸を蝋燭の火で切り、片方の端を〝T字釘〟の頭に、もう片方の端を蝋燭立てに結びつけた。
蝋燭立てを降ろす。その明かりは糸で窓の真横に吊り下げられる。
ケイもまた、蝋燭立てとは反対側の窓の横にぶら下がった――もちろん鈎縄を使って。鈎を屋根の縁にかけ、体に巻きつけた縄を調整しながら、窓のすぐ横まで下りる。蝋燭立ては窓の右、ケイは左だ。背後には隣家の壁があった。窓の蝶番は右、かんぬきは左。
月明かりだけで、やれればいいんだがな。
やってやれないことはないのだが、時間がかかる。ケイは懐から大きな釣り針の付いた糸を取り出し、右手で窓の上枠と上桟の隙間に滑り込ませた。
蝋燭の小さな明かりを頼りに、糸をさばいてかんぬきを外す。この針に返しはないが、手元が狂ってカーテンに刺してしまったら厄介だ。それにかんぬきの位置を正確に知るためにも最低限の照明は必要だった。北の妖精族は月よりも弱い星明かりの下でも物が見えるというが、夜目が利くケイにしてもそこまではいかず、たとえそれが子供騙しのお伽噺でも羨ましかった。
だが、妖精ならざる者はやれることをやるしかない。
そのために隣家の窓には向き合っていない窓を選んだ。上の明かりを見る者はいないとしても、横からなら――カーテンを開けて窓の外に光があれば、気づかれることもあるだろう。用心するに越したことはなかった。
手応えあり。
微かな音を立ててかんぬきが外れる。
この窓は外開き。糸を大きな動作で引く。下手に力を入れると釣り針がカーテンや窓の桟に引っかかり、糸から外れるかもしれない。動きが小さくても遅すぎてもだめだ。糸が滑って、それでは窓は動かない。大きく適度な速さで、糸の摩擦を使えば手前に少しだけ、必要なだけ引っ張れる。
ケイは、動いてわずかにせり出した窓の上桟に指をかけて、注意深くさらに開いていった。音を立てるな。途中で糸と釣り針を開いた隙間から抜いて懐に戻す。
今は縄一本で宙ぶらりんになっていることは忘れろ。
風があっても体を揺らすな。
カーテンの向こうに全神経を集中する。
暗い。音はしない。気配もない。少しこもった空気が漏れてくる。
誰もいない。
そう確信してケイは右足を下枠にかけ、半開きの窓から、するりと中に忍び込んだ。
すぐさましゃがんでカーテンをくぐり、身構える。
左右をうかがう。やはり誰もいない。
カーテンを開き、窓の外に手を伸ばして蝋燭立てを回収した。その明かりで照らすと、自分が立っているのは寝室だとはっきりわかる。ホーラーの寝室ではなく、控えの――おそらく両親か妹が泊まる時のためのものだ。とはいえホーラーには、この別邸に家族を招くつもりはさらさらないのだろう。その証拠に、ここは塵ひとつなくベッドメイクもされているが、使われた形跡がない。使用人がまめに換気して掃除もしているのだろうが、乾き果てて崩れる寸前の押し花のような、見捨てられた部屋特有の臭いが漂っている。
蝋燭立てをサイドテーブルに置き、ケイは糸を強く引いて〝T字釘〟も取り戻す。麻糸が切れたり、警備が厳しくて余裕がなかったりする時には諦めるが、この道具は入手に手間がかかるので、それは本当にやむをえない場合だけだ。ケイは腰の鞘にもう一本挿しているが、あらためて手に入れるとなれば、鍛冶屋に寸法などを事細かく伝えた上で作らせなければならなかった。
お次は鉤縄――どちらかと言えば、今はこちらを失うわけにはいかない。窓の真下の路地でベスが待っている。ケイが下ろす縄で壁を登るために……。もし待っていなかったら? 〝下の道〟で衛士に怪しまれて足止めされていたら? 蝋燭の合図に気づかずにいたら? その時はその時だ。
ケイは屋根から外した鈎を窓の下枠にかけ直し、縄を路地に下ろした。
ベスが〝上の道〟を行けるようになれば、こうした面倒はなくなる。本人の望みどおり、もっと盗賊らしい役目を任せられる。
まずは鈎縄で屋根に登ることだ。
そうすれば上でケイがやっていることを見られる。見て、盗れると思ったら盗ればいい。ケイもずっとそうしてきた。鉤縄の扱いも、〝跳ぶ〟ことも、種火の缶や蝋燭の使い方も、釣り針と糸のさばき方も、何もかも盗ったものだ。それをベスが盗って何が悪い? 盗れるものなら盗ってみろ。文句は言わない。自分は盗っておきながら、他人に盗られて不平を漏らすような奴は、呆れ返るほど筋を違えている。
縄が下り切ると、それは間髪入れずにピンと張った。
登ってくる。
縄が下り切った直後、ベスは早すぎず遅すぎない、いいタイミングでつかんだ。今のところ音も立てていない。
――ケイは口元をほころばせた。
ことによったら、予想よりもずっと早く、ベスは上にやって来るかもしれない。
〈王都〉には市街を囲む壁がない。
これは珍しい。この国で都市と言えば、繁栄しているにせよ、衰退しているにせよ、たいていは壁に囲まれた城郭都市で、それらの囲壁はこの国の歴史、血なまぐさい歴史の隠し切れない残響だった。
国がまだ国ではなかった時代、野心を胸に抱いた者らが奮い立ち、軍を率いて盛んに争い、他の砦や集落を攻略した。勝者は領土と権勢を増し、拠点を村から町へ、町から都市へと変えていく。それを受け継ぐ子や孫の世代になれば、より大きく、より豊かな都市の奪い合いだ。戦いに備え、都市は壁で囲まなければならない――滅亡や追放の憂き目に遭いたくなければ。
壁があってもなお、初期の攻防から数世代経つまでに数多の都市が滅んだ。生き延びた都市がいっそう富み栄える傍らに、いつの日にかの再生を夢見る廃墟が横たわる。そしてついに数個の都市が大都市に育ち、壁の高さも頂点に達そうかという頃、その内側の権力の座に蠢く者どもは〝貴族〟と呼ばれるようになり、他の貴族を圧倒して〝王〟と称する者も現れた。王の名の下に国は国となって、王は大都市から国民に号令を発する。
昔々、〈王都〉には王がいて、囲む壁もあった。
――今はない。
壁のない〈王都〉で〝壁抜け〟が何だというのだ?
決行の夜、ケイは少し苛立っていた。出発前に〈雄羊の蹴り足〉で、ベスに例の魔除けの紐を押しつけられたからだ。
「こいつはあんたが持っといてよ」
「いらない」
そんな物よりも、今夜のベスがナイフより大きな武器を持っていないことがケイには大事だった。
アーティは夜回りの数は増えていないと言ったが、それでも〝下の道〟で衛士に呼び止められる可能性はある。そうなったら面倒だ。
〈王都〉では路上で無許可の武器携帯は違法だ。小さなナイフは誰もが鞘に入れて腰に下げていたり、ブーツに差していたりするのだが、その程度なら〝道具〟として見逃される。とはいえ何が武器で、何が道具なのかの区分はひどく曖昧である。少し刃渡りの長い得物や、重そうな警棒、頭の反対側が尖ったハンマーあたりを夜の街で持っていれば、衛士に四の五の言われて詰所にしょっぴかれてもおかしくない。要は許すも許さぬも奴らの虫の居所次第だ。
「そんなら、これだけさ」
ベスはふてくされた顔で外套を手に取り、左の内側に鞘入りで収めたナイフを見せた。それが正解だ。衛士に咎められず、いざという時に役に立ち、投げることもできる。
「それでいい。まずは下からお前が来ないことには、始まるものも始まらないからな」
「わかってる、わかってるよ」
ベスは顔をしかめる。
仮に荒っぽい仕事をするとしても、ケイはベスに長い刃物は持たせなかっただろう。ろくに訓練もしていない素人が片手で扱える武器は、頑張って自分の肘から拳先の長さまで。それを超える得物は怪我の元だ。
何にせよ、今夜の計画はケイとベス、ふたり揃うことが前提で、どちらかでも欠けたらおじゃんだ。
「〝壁抜け〟なら、ひとりでやるんだろうけど――」
「ひとりでやれることなんざ、たかが知れてる」
ケイは吐き捨てた。
「――ね、だからだよ。だから、これはあんたが持っててって言ってるのさ」
ベスは怪しい紐の束を握ってケイに突きつける。ふたりでやる仕事でも、ほとんどはそれぞれが別行動。万が一、ひとりで〝壁抜け〟に出くわすとすれば、その可能性はケイのほうが高い。
これはそのとおりだった。
盗賊は盗賊のやり方で仕事をする。手際よく事を運ぼうとすれば手口が似るのは当然で、盗賊同士の計画は重なりやすい。狙い、日取り、経路、警備をどうかわして、どこを探すのか――。その結果、どこかで他の盗賊とかち合った時、一方がどうぞどうぞと譲ることはまず期待できない。ほぼ間違いなく、ひと悶着起きる。現場ではできるだけ避けたい事態だ。
結局のところ、盗みは早いもの勝ち。同業者よりもお先に獲物をかっさらうのが一番――なのだが、今回は他人が狙っている家に忍び込むという話である。 そいつはケイと同じように考え、同じ夜に、同じ経路を辿って、同じ振る舞いをするかもしれない。
「捕り物でもさせる気か?」
「んなわけないよ。でも、もしも……」
もしも俺が〝壁抜け〟を縛り上げたら、俺よりそいつと組みたくなるんじゃないか? とケイは嫌味を言おうとして、止めた。相棒と揉めるのは仕事に差し障る。
ケイは紐を自分の腰に吊るした。ベルトには他にもいろいろと道具を吊るさなければならないが、このくらいは問題ない。
ベスは破顔する。
そもそもこの仕事はベスが見つけてきたのだ。少しくらい言い分を聞いてやってもいいだろう。それで気が済むのなら――ケイは〝壁抜け〟と鉢合わせするとは思っていなかった。〝果物屋〟の取り巻きの放言にこうも煩わされるのは癪だが、そこには目をつぶる。これで今夜、仕入れがうまくいったら、アーティには迷惑料を上乗せして買わせるさ。
屋根の上から〈雄羊の蹴り足〉のある方角を眺めるうちに、ケイの苛立ちも収まってきた。
汚れた夜空の下、〈王都〉の外周に向かって徐々に低くなる屋根の連なりは暗く凪いだ海のように見えた。ところどころに影になって浮かぶ高い建築は島だ。ケイは河口の港から小さな船で近海に出たことがあるばかりで、遠洋にはからきし馴染みがなかったが、漁船や商船などに乗って大海原を行く船乗りたちに漠然とした、一方的な親近感を抱いていた。船乗りは頼るものなき無辺の空間で、独自の規律に従い、独特な言葉と道具を使い、自らの領分に応じて稼ぐ。盗賊も同じだ。
いずれベスも気づくだろう。
王なき〈王都〉に囲む壁はなく、それを〝抜ける〟も〝抜けない〟もない。どこまでも広がるここで盗れるものを盗る――あるのはそれだけだ。しかし、こういうことは話しても無駄で、ベスが自分の力で屋根まで登り、この光景を眺めて実感する他にない。
それにはまだ、しばらくかかりそうだが――とケイは思った。
望むままに高い建物の屋根に登りたければ、鈎縄の扱いを覚える必要がある。この夜、ケイは鈎縄を使い、ホーラーの別邸から少し離れた住宅の屋根に登った。暗闇の中、建物と建物の間の狭苦しい所からでも、狙ったとおりに鈎縄を投げられて、一発で鈎を引っかけられるようになるには相応の経験がいる。もちろん最初からやすやすとこなして見せる者もいるが、残念ながらベスはそうではなかった。
「本当にこれ、使えんの?」
「使える」
以前、樫ヶ橋通り裏の小さな空き地で、ものは試しにベスに投げさせた鉤縄は、廃屋の屋根のどこにも引っかからずにあっけなく滑り落ちた。最初はそんなものだ。鈎を窓にぶち込んだり、あらぬ所に引っかけて回収不能にしたりしないだけ、ベスはましなほうだった。
ケイは手にした鈎縄を頭上で小さく三回転させ、屋根めがけて放った。そして縄を手に両足を壁にかけて体を浮かせ、しっかり鈎がかかっていることを示す。
目を丸くしているベスの前で、地面に降りたケイは片手で縄を素早く上下に振り、鈎を外して取り戻した。縄の張りを活かして手元で鈎を回収することも、覚えなければならない技のひとつだ。これができなければ登った時はいいが、降りた時に鈎縄が置き去りになってしまう。
「ちくしょう、こっちは得意なのになあ!」
ベスは外套の内からナイフを抜き、振り返って木塀に投げた。
乾いた音を立てて、ナイフが突き刺さる。
いい腕だ。癖のない投げ方でナイフはまっすぐに飛んだ。これなら目標に深く刺さる。
「それができるなら、鉤縄も使えるようになる」
ケイは笑った。
気休めではない。ベスは鈎の投げ方も悪くなかった。
だが、仮に登れるようになったとしても、〝上の道〟を行くために覚える技は他にもある。
たとえば明かりがなくとも、周囲の建物も含めて、窓や煙突などの位置と構造を把握すること、スレート葺きで足を滑らせないこと、傾斜のきつい切妻屋根の上でも自在に動き回れること、屋根やバルコニーの縁に指をかけてぶら下がれること、そして――。
〝跳ぶ〟こと。
ケイは出窓で張り出した壁に右手を突き、強く押して勢いをつけると、二歩の助走で跳躍した。
一瞬、焦げ茶の外套が闇を裂き、裾がはためく。
音もなく隣家の屋根に着地して、ケイはゆっくり大きく息を吸った。〝上の道〟は〝跳ぶ〟こと抜きには語れない。屋根と屋根は繋がっていないから……。気取って〝空の道〟と呼ぶ盗賊もいるほどだ。
今夜の侵入経路は計五回、〝跳ぶ〟ことを要する。
その中で最も危険なのは、ケイが今、跳んでみせた四回目だった。距離の離れた次の屋根に着地できるのはそこだけなのに、助走する余地がほとんどない。屋根の縁を蹴る脚のばねが足りなかったり、空中に身を投げ出すタイミングがずれたりすれば真っ逆さまだ。落ちて地面に叩きつけられ骨折で済めばよいほうで、打ちどころが悪ければ死ぬ。盗賊にとって高所からの転落は、自らの技量の低さを証明する物笑いの種だった。
〈王都〉育ちなら、昔話の〝干物ドノバン〟、または〝ぶらりドノバン〟を聞いたことがあるはずだ。盗賊のドノバンは御殿の屋根から落ちて、返しが付いた鋭い鉄柵の先端に下顎を貫かれてしまった。朝になって、ドノバンは乾物屋に吊るされた魚の干物のように鉄柵にぶら下がった姿で見つかり、間抜けな泥棒としてそのまま晒しものになった。そんなドノバンの足が地面に着いたのは、本当にぼろぼろの干物になって、突き刺さった柵から顎が外れてようやくだったという。風が吹くたび、ぶらーん、ぶらんとドノバンぶらり――。街の餓鬼どもが「おい、ドノバンになるなよ」とほざくのは「ヘマをするな」と不良仲間に警告しているのだ。
ケイは、ドノバンほど運に見放されたわけではないが、落ちて腰を強く打ち、二度と〝跳ぶ〟ことができなくなった奴、跳んだはいいが距離が足りず、すぐ下のバルコニーに突っ込んで腕の骨を折った奴、着地で大きな音を立ててしまい、見張りに気づかれて捕まった奴など、難所でしくじった盗賊の話を幾つも知っていた。
だから今はまだ、ベスと一緒に〝上の道〟を行くことはできない……。
最後の、五回目の跳躍はあっさりしたものだった。
下見の時に確認した、ごく細い路地を跳んでホーラー別邸の黒い屋根に渡るだけ――〝跳ぶ〟というより〝跨ぐ〟感覚に近い。
この下の路地にベスが来る。
別邸の屋根の上で、ケイは背負い袋から太い蝋燭と、外側に革が張られた小さな缶を取り出した。蝋燭を腰に下げていた粗末な針金の蝋燭立てに挿して、缶に入った炭の種火で火を灯す。ベスへの合図だ。ベスは近くの地上の物陰から、こちらをじっと見ているはずで、ベスだけが蝋燭の小さな光を目にするだろう。真夜中の住宅街で建物を見上げる通行人はまずいない。衛士もだ。奴らは〝上の道〟のことを知らないはずがないのに無視している。下の見落としは隊長から叱責されるが、上については幾らでも言い訳できるからだ。はっ! しかし我々の職務は管轄内の街路を警戒することにありまして、そこは範囲外なのであります(屋根に賊を見つけたって、賄賂をせびることもできないからなあ)。
ケイは邸内への侵入の準備を始めた。
腰の管のような鞘から〝T字釘〟を抜く。
これは、かなり太くて長い釘の頭が、拳の幅ほどの長さの更に太い横棒になっている代物で、その形からケイが名づけた道具だ。腰の物なのでナイフだと思ったベスに見せたことはあるが、使い方は詳らかにしていない。
真下にある三階の窓のひとつを見計らい、ケイは位置を定めて屋根に葺かれたスレートとスレートの間に〝T字釘〟の鋭い先端を当て、軽く体重をかけるようにして横棒を手のひらで押し、ねじ込んだ。これは後で外しやすいように軽く刺すだけでいい。そしてベルトに挟んだ糸巻き棒を出して、ちょうどいい長さだけ太い麻糸を蝋燭の火で切り、片方の端を〝T字釘〟の頭に、もう片方の端を蝋燭立てに結びつけた。
蝋燭立てを降ろす。その明かりは糸で窓の真横に吊り下げられる。
ケイもまた、蝋燭立てとは反対側の窓の横にぶら下がった――もちろん鈎縄を使って。鈎を屋根の縁にかけ、体に巻きつけた縄を調整しながら、窓のすぐ横まで下りる。蝋燭立ては窓の右、ケイは左だ。背後には隣家の壁があった。窓の蝶番は右、かんぬきは左。
月明かりだけで、やれればいいんだがな。
やってやれないことはないのだが、時間がかかる。ケイは懐から大きな釣り針の付いた糸を取り出し、右手で窓の上枠と上桟の隙間に滑り込ませた。
蝋燭の小さな明かりを頼りに、糸をさばいてかんぬきを外す。この針に返しはないが、手元が狂ってカーテンに刺してしまったら厄介だ。それにかんぬきの位置を正確に知るためにも最低限の照明は必要だった。北の妖精族は月よりも弱い星明かりの下でも物が見えるというが、夜目が利くケイにしてもそこまではいかず、たとえそれが子供騙しのお伽噺でも羨ましかった。
だが、妖精ならざる者はやれることをやるしかない。
そのために隣家の窓には向き合っていない窓を選んだ。上の明かりを見る者はいないとしても、横からなら――カーテンを開けて窓の外に光があれば、気づかれることもあるだろう。用心するに越したことはなかった。
手応えあり。
微かな音を立ててかんぬきが外れる。
この窓は外開き。糸を大きな動作で引く。下手に力を入れると釣り針がカーテンや窓の桟に引っかかり、糸から外れるかもしれない。動きが小さくても遅すぎてもだめだ。糸が滑って、それでは窓は動かない。大きく適度な速さで、糸の摩擦を使えば手前に少しだけ、必要なだけ引っ張れる。
ケイは、動いてわずかにせり出した窓の上桟に指をかけて、注意深くさらに開いていった。音を立てるな。途中で糸と釣り針を開いた隙間から抜いて懐に戻す。
今は縄一本で宙ぶらりんになっていることは忘れろ。
風があっても体を揺らすな。
カーテンの向こうに全神経を集中する。
暗い。音はしない。気配もない。少しこもった空気が漏れてくる。
誰もいない。
そう確信してケイは右足を下枠にかけ、半開きの窓から、するりと中に忍び込んだ。
すぐさましゃがんでカーテンをくぐり、身構える。
左右をうかがう。やはり誰もいない。
カーテンを開き、窓の外に手を伸ばして蝋燭立てを回収した。その明かりで照らすと、自分が立っているのは寝室だとはっきりわかる。ホーラーの寝室ではなく、控えの――おそらく両親か妹が泊まる時のためのものだ。とはいえホーラーには、この別邸に家族を招くつもりはさらさらないのだろう。その証拠に、ここは塵ひとつなくベッドメイクもされているが、使われた形跡がない。使用人がまめに換気して掃除もしているのだろうが、乾き果てて崩れる寸前の押し花のような、見捨てられた部屋特有の臭いが漂っている。
蝋燭立てをサイドテーブルに置き、ケイは糸を強く引いて〝T字釘〟も取り戻す。麻糸が切れたり、警備が厳しくて余裕がなかったりする時には諦めるが、この道具は入手に手間がかかるので、それは本当にやむをえない場合だけだ。ケイは腰の鞘にもう一本挿しているが、あらためて手に入れるとなれば、鍛冶屋に寸法などを事細かく伝えた上で作らせなければならなかった。
お次は鉤縄――どちらかと言えば、今はこちらを失うわけにはいかない。窓の真下の路地でベスが待っている。ケイが下ろす縄で壁を登るために……。もし待っていなかったら? 〝下の道〟で衛士に怪しまれて足止めされていたら? 蝋燭の合図に気づかずにいたら? その時はその時だ。
ケイは屋根から外した鈎を窓の下枠にかけ直し、縄を路地に下ろした。
ベスが〝上の道〟を行けるようになれば、こうした面倒はなくなる。本人の望みどおり、もっと盗賊らしい役目を任せられる。
まずは鈎縄で屋根に登ることだ。
そうすれば上でケイがやっていることを見られる。見て、盗れると思ったら盗ればいい。ケイもずっとそうしてきた。鉤縄の扱いも、〝跳ぶ〟ことも、種火の缶や蝋燭の使い方も、釣り針と糸のさばき方も、何もかも盗ったものだ。それをベスが盗って何が悪い? 盗れるものなら盗ってみろ。文句は言わない。自分は盗っておきながら、他人に盗られて不平を漏らすような奴は、呆れ返るほど筋を違えている。
縄が下り切ると、それは間髪入れずにピンと張った。
登ってくる。
縄が下り切った直後、ベスは早すぎず遅すぎない、いいタイミングでつかんだ。今のところ音も立てていない。
――ケイは口元をほころばせた。
ことによったら、予想よりもずっと早く、ベスは上にやって来るかもしれない。
メッセージを送る!