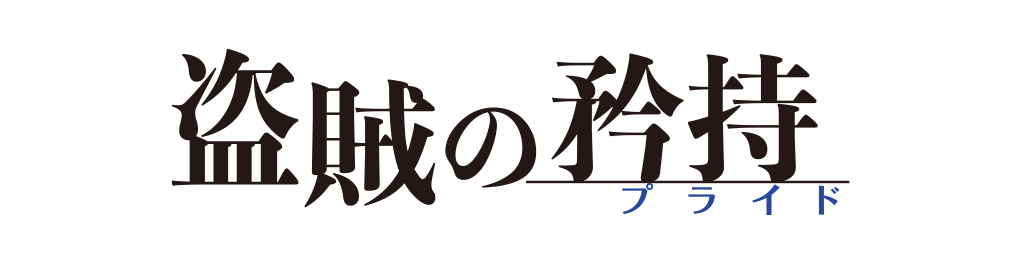6.金の在り処
ケイは伸ばされた手を取って、ベスを引っ張り上げた。
一本の蝋燭に照らされた寝室で、ふたりは何も言わず、目を合わせすらしなかった。侵入後の手筈も前もって打ち合わせ済みだ。〝下の道〟で、ベスは予期せぬ事件や事故に遭ったり、思わぬ冒険をやり遂げたりしたかもしれないが、その話を聞くのは仕事が済んでからでいい。
ベスはケイの横を素通りして扉に向かう。そして聞き耳を立て、少し開けた扉から顔だけ出して左右をうかがい、後ろ手に信号を送る――〝無人〟だ。
ケイは窓を閉めてかんぬきをかけ直し、カーテンを引いた。
鉤縄は束ねて左肩に巻きつけるようにして担ぐ。計画どおりにいけば、もう鉤縄の出番はないから背負い袋に放り込んでもいいのだが、そううまくいくとは限らない。便利な道具はいつでも使えるように持っておきたかった。
――顔を上げるとベスはいなくなっていた。
それでいい。ベスは蝋燭もなしに一階に下りて、玄関まで向かわなければならない。下手に目が火の光に慣れる前に出るのが正解だ。
一方、ケイにはまだ蝋燭が必要だった。
ベスが姿を消した後、少し間をおいてケイも控えの寝室から廊下に出る。
邸内を物色するのはケイの役目だ。無駄な動きを減らし、効率よく盗って回るには目端を利かせなければならない。見込みのない場所を探って、時間を無駄にするのは危険だ。この別邸には使用人夫妻が住み込んでいて、今も地下の部屋にいるのだ。まず間違いなく寝ているだろうが……だからといって、ぼやぼやしている暇はなかった。
不慣れな者だと、無人の屋内に入る〝空き巣〟では明かりを手にし、誰かがいる場所に忍び込む〝居抜き〟の場合は無灯で――そんなふうに家探しするべきではないかと思うだろう。
逆だ。
屋外の誰かにカーテンの隙間などから、無人のはずの中で光源が動いているのを見られたら確実に怪しまれる。そんな危険は冒さなくていいし、誰もいない場所なら物色するにも少しは時間に余裕が持てる。〝空き巣〟に常時の照明は不要だ。ここぞという時、光が外に漏れる恐れがない時にのみ、火を灯せばいい。
それが〝居抜き〟では話が変わる。侵入後は手際のよさと速さが何よりも優先だ。短時間でめぼしい獲物を漁り、できるだけ早く逃走する。そのため手元に明かりを携えていたい。よしんば外の者が光に気づいたとしても、中の誰かが灯したものだと考えて、まず怪しまないだろう。
では外ではなく建物内にいる誰かに気づかれた場合はどうか。直ちに逃走――ではなく脱出に全力を傾けなければならない。
〝居抜き〟は侵入を悟られた瞬間に失敗である。明かりを手にしていようがいまいが関係ない。もちろん失敗しても逃げずに脅しと実力行使で中の者を制圧する――つまりその夜の仕事を〝押し込み強盗〟に切り替えることもできるが、そういう泥縄な手口をケイは好まなかった。悟られることなく侵入し、見つからず、目立った痕跡も残さず、逃走から何日も経って、こちらがすでに盗品を故買人に売り払うか、依頼者に渡した後でようやく何か盗まれたと発見されるのが理想だ。
ケイは廊下の左右にさっと目を走らせ、左手の蝋燭立てを膝のあたりまで下げた。
罠があるかもしれない。床に張った糸や紐に引っかかると大きな音が鳴る……そういう報知器の類が。
実際、ケイはかつての仕事で、組んだ老盗賊が罠にかかってしまい、ふたりして盗るものも盗らずにほうほうの体で逃げたことがある。老盗賊はケイよりも経験豊富だったが、その種の装置は比較的近年に発明された物なので、存在を知らずにいた。単純な仕掛けだが、我こそは不寝番なりと豪語して雇われようとする輩(不審者の間違いだろう)や、ご大層な金庫の錠前(金庫ごと盗むとか対処法は幾らでもあるが?)などよりも、そうした〝糸と鳴子〟式の報知器のほうがずっと盗賊避けになる。これは戦場の野営地で用いられていたのを都市向けに改造した罠だそうだが、正直、あまり〈王都〉に広まって欲しくない代物だった。
だが知っていれば、かわせないわけではない。
今頃、ベスは這うほど姿勢を低くして慎重に玄関に向かっているはずだ。隠密を重視して明かりを持たない時はそうやって壁際を進む。焦らなくていい。罠にかからないことに集中しろ。ケイが盗みを済ませて下りてくるまでに玄関の鍵を開けておく。そして使用人夫妻が地下から出てくるようなら、急いでケイに知らせられるように隠れて見張る。それがベスの役目だ。
何事もなければ、後はふたりで玄関から悠々と逃走できる。玄関の鍵が開いたままになるが、今回はそれでいい。他に侵入した形跡を残さなければ、家の者は施錠し忘れたと思い込みやすいというのもあるし、今夜の狙いは商人の隠し金、つまり被害を公にしにくい獲物だという点も大きい。盗みの発覚は確実に遅れる。
だが、運悪く使用人が一階に出てきたら、そこで侵入は終わりだ。
そうなったら、ケイは知らせにきたベスと一緒に、二階か三階の窓から脱出することになるだろう。まだ金目の物があったとしても諦めなければならない。口惜しいが盗賊の仕事とはそういうものだ。準備万端で、特にミスを犯したわけではなくても、少し幸運がなかっただけで欲しいものが手に入らないこともある。
だからといって出たとこ勝負な仕事は論外だ。捕まった盗賊に〈王都〉の司法は甘くない。くすねた富の大きさにもよるが、監獄送りと強制労働なら御の字で、盗った相手次第では片手くらい簡単に切り落とされる。それが嫌なら放免や釈放を求めて衛士や判事、獄吏に鼻薬を嗅がせることもできるが……どれほど足元を見られることか!
更には、これなら衛士にしょっぴかれたほうがましだった、ということすら起きうる。捕まった挙げ句、その場で激しい暴行を受けたり、最悪、雇い主の命令なら何でも従う冷酷な用心棒に処分されたりといったこともざらだった。法は窃盗には厳しいが、そうした〝私的制裁〟には甘い。貴族や金持ちが命じたものなら特に。
――要は引き際が肝心ということだ。
捕まって迎える悲惨な結末に比べたら、獲物を諦めることなど安い。それもあって多くの盗賊は、波止場の倉庫の中身や輸送馬車の貨物を根こそぎ奪うような大掛かりな仕事でなくても、二人組、三人組、更に大人数と徒党を組む。ひとりあたりの稼ぎは減るかもしれないが、偵察役や見張り役、連絡係、事前の内部潜入者など、作業を分担することで危険を避け、退路を確保し、密かで速やかな仕事を実現する。
今夜のケイとベスの計画もそうだった。
この程度の仕事なら、ケイはひとりでもこなせる自信があった。それでも、これはベスが見つけた仕事だということを抜きにしても、状況が許せばやはり誰かと組むだろう。脱出口を開き、危機の接近を見張ってくれる誰かがいれば、ケイは盗みに集中できる。
今、あの老盗賊――通り名は〝ご隠居〟――と組んでいたら、老人は玄関に向かいつつ、途中に罠があれば解除するか、それが無理なら後で下りてくるケイのためにさりげなくパース銅貨でも置いて目印を付けてくれるはずだ。〝ご隠居〟が同じ罠に二度もかかるほど間抜けでないことは言わずもがな、一度知った罠や警備には容易に対策してみせる。
ベスにはそこまで求めていない――今のところ。
ケイは右に歩を進めた。
ここは三階。左は下り階段の踊り場で見るべきものはない。突き当たりは出窓。そこはせり出していて、別邸正面を外から見れば、玄関ポーチの上の雨避け、簡易の屋根になっている。これは石工ヶ辻の住宅の多くに見られる造りだ。
出窓のカーテンが少し開いているのは、ベスが階段に最低限の明かりが入るように開けたのだ。この時刻、街灯の火はあったとしても消えかけだから、外の明かりは主に月や星のそれで、ごくわずかなものである。それでもあるとないとでは大違いだ。足を滑らせて物音を立てたり、罠にかかったりする確率をぐっと下げられる。カーテンは後でケイが下りる時に閉めればいい。続く一階への階段に光を入れられる、二階踊り場の窓のカーテンもベスは少し開けるだろう。
反対の右奥、突き当たりの扉は建物の主――若き商人ホーラーの寝室だ。ここは新築ではなく空き家を購入したものである。ならば間取りや各部屋の使い途は通り一遍のもののはずだ。一階にはまず玄関ホール。そこに来客の荷物やコートを預かるクローク、そして上り階段がある。奥の扉の向こうは居間兼応接室だ。金持ちが気取って〝パーラー〟とか呼ぶ、その種の居間の奥の壁には大きな両開きの窓があるものだが、ホーラー別邸の窓は小さい。建物の裏にほとんど余地がなく、窓を大きくしても他人の家の塀が殺風景なばかりだからだ。
居間の左右にも扉があって、ひとつは食堂に通じている。ここの場合は左の扉がそれで――下見の時に外から確認した――その食堂には正面から見て奥にも小さな扉がある。そちらからは短い廊下に出られて、下り階段があるだろう。地下の調理室や食料庫、ワインセラーから、料理や酒を運んでくるのは使用人の仕事だ。彼らが住み込む使用人部屋も地下である。
ベスは一階に下りたら玄関に直行して鍵を開け、上り階段の脇にでもうずくまり、使用人夫妻が地下から出てこないかどうか、耳を澄ませるだろう。玄関ホールへの扉が開くようなら、急いで階段を駆け上ってケイにご注進だ。
この手筈は〝ご隠居〟も同様だろうが、海千山千な老人のことだ。鍵を開けた後、ついでの仕事もするに違いない。安全だと判断するや、こっそり居間に忍び込む。食堂に入れば金の燭台や銀食器があるかもしれないが、それは狙わない。〝ご隠居〟のお目当ては別の扉、喫煙室への扉だ。そこの戸棚から煙草をくすねる。もちろん輸入ものの高級品――下町の街角で三パースも出せば買えるクズ煙草とは比較にならない、香り高い上物をあまり欲張らずに拝借する。売れば五シェール前後、銘柄によってはその二倍、三倍の稼ぎになるが、これは自分用である。老人は好みにうるさい愛煙家で、〈王都〉にはまれな盗まずとも生活に困らない盗賊だった。
〝ご隠居〟は隊商を三つも所有する大手商会の会計を見事に勤め上げた人物で、引退後は以前の勤め先から支払われる年金で悠々自適の晩年を過ごしていた。長年連れ添った妻との間には子がいて孫もいる。そんな経歴の御仁が盗みを働く理由は、本人の言葉を借りれば「持って生まれた性分」だった。
幼い頃から〝ご隠居〟には盗癖があった。
盗むのは日々の糧ではなく喜びで、やらずにはいられない。おまけに才能にも恵まれていた。盗賊になったのはいつからなのか、ケイは知らなかったが、商会に勤めていた時にはすでにそうだっただろう。にもかかわらず、家族やかつての同僚たちはそれを知らない。〝ご隠居〟がちょくちょく下町の酒場に足を運ぶのは――もちろん仕事のためだが――その手の騒がしい場所で煙草を吹かすのを愛しているからだと思われていた。
ケイは〝ご隠居〟に商会で横領したことはないのか? と尋ねたことがある。
「あるとわかり切っている金を盗って面白いかね?」
それが答えだった。
この熟練の老盗賊は、どこそこの貴族が所蔵する絵画を盗るとか、富豪の金庫を狙うといった話にはすげなく紫煙をくゆらせるばかりで、あそこにはたぶん何かがありそうだと聞くと、火をつけた煙草が灰になるのも構わず放ったらかしにして身を乗り出してきた。そしてまんまと見込みが図に当たって稼ぎを得ると、肺から煙を吐き出しつつ、
「いやはや、あるところにはあるものだね」
と含み笑いを漏らしながら言うのだった――心底満足そうに。
卑しい生まれの食い詰め者がお定まりの盗賊たちに対して、〝ご隠居〟は生まれも育ちも恵まれていた。元からいい暮らしをして懐にも余裕がある。ゆえに、まるで煙草の銘柄のように好みの仕事を選べるし、たいていの盗賊が不案内な金持ちの習慣や住まいの細部にも通じていた。その知識は当の本人が獲物を見定め、それを盗って「やはりあった」と喜ぶ上で大いに役立った。
そんなやり口をケイもずいぶんと盗ませてもらった。
小金持ちが住む建物の一階は居間などの共有空間。これはもっと裕福なお大尽の邸宅でもだいたいそうなっているが、富豪のお屋敷に比べれば全体に手狭なので、貯蔵庫だけでなく調理場や使用人の部屋も地下に配される。
二階にはおおむね客室が並び、三階が家族の個人的空間だ。その一番奥は主人、または主人夫妻の寝室である……。侵入する前から、こうしたことがわかるのは〝ご隠居〟と組んで仕事をしたおかげだ。
ホーラー別邸の間取りが想定の範囲内だとすれば、二階は端から無視していい――とケイは考えていた。客が寝泊まりして自由に動き回る階に、隠し金を置いたりはしないだろう。同様の理由で一階も物色する必要がない。こちらは客に加えて使用人も頻繁に出入りするからなおさらだ。家の主人が極めつきに天邪鬼であるか、盗賊の裏をかけるほど擦れた人物でもない限り、まず間違いない。ベスの調べではホーラーは天邪鬼でも擦れっ枯らしでもない。やり手ではあるが、青臭さが抜けて強欲さが鎌首をもたげてきたばかりのお坊ちゃんだ。
――金は三階にあるとして、どこに?
寝室から出てすぐ向かいに扉があるが、これはもうひとつの控えの寝室の扉だ。今、出てきたばかりの部屋にはシングルベッドがあった。妹用だろう。ということは、こちらの扉の先は両親用の寝室でダブルベッドがある。いずれも金を置くとは思えない。
奥の主人の寝室に隠している? そこそこありうる話だ……が、それはホーラーが臆病な猜疑心の塊だった場合だ。違う。ベスが語った若き商人の人物像にそぐわない。物怖じせず、堂々としていて、百天秤街で店を切り盛りできるだけの気概がある男。それが寝床に硬貨を敷き詰めて、ようやく枕を高くできるといった、せせこましい振る舞いをするとは思えなかった。
まだ他にも扉はふたつある。突き当たりの手前、左右の壁に向き合ってひとつずつ。
ケイは蝋燭の明かりでふたつの扉を照らし、見比べた。
蝋燭立てを少し高く掲げると、暗さに慣れたケイの目に三階の廊下が浮かび上がる。塵ひとつなく、象牙色の壁紙も上等できれいに貼られていた。わずかに青みがかった白で淡く描かれた模様は蘭の花。真鍮のランプかけと調和がとれている。そういえば玄関ポーチ階段脇の鉢植えの花も蘭だった。そちらの色は昨今〈王都〉で流行りの紫。
足元の絨毯は複雑な幾何学模様の舶来品だ。言うまでもなくホーラーの店のものだろう。この別邸を粗暴な盗賊団が襲ったなら、引っ剥がして奪うはずだ。まともに一巻持ち出して故買にかければ、売り値はシェール銀貨どころかクロン金貨で設定される獲物である。
だが、ケイが屈んで明かりを下げ、絨毯に目を凝らしたのは盗るためではなかった。盗ろうとしたところで、これはベスとふたりでやる〝居抜き〟ではどうにもならない――ケイは絨毯の乱れや擦れ具合を確認していた。
向かって右の扉の前の絨毯には数え切れないほど踏まれた形跡がある。使い込まれている部屋の入り口だ。奥の寝室の扉の前もほぼ同じ。一方、左の扉は絨毯の様子から察するに、控えの寝室ふたつと同様に、あまり使われていないことが見て取れた。
右の部屋は別邸の執務室だ。そこでホーラーは店から持ち帰った事務仕事をしたり、読書に――そういう習慣があればだが――耽ったりしているだろう。
すると左の部屋は何か? 家主が所帯持ちなら妻の居室かもしれない。夫人はそこで編み物をしたり、手に入れたばかりの衣装や装飾品を身に着けて鏡と向き合い、着飾った自分にうっとりしたりするのだ。子があれば子供部屋でもおかしくない。しかしホーラーは独身だ。本当に読書家なら図書室ということもありうるし(これは客に蔵書を自慢するために二階に配されることもある)、楽器を奏でるのが趣味なら(そんなことをベスは言っていなかったが)演奏室……だが、これも違うだろう。主人の娯楽部屋ならもっと使っているはずだ。
この部屋に金がある。
左の扉の前に立ち、ケイはノブのあたりを蝋燭の火で照らした。マホガニーの扉に真鍮のノブ。手入れはよく、ピカピカに磨き上げられている。鍵はかかっていない。
いいぞ、ホーラー。
大して使いもしないのに主人が鍵をかける部屋があったら、使用人のいらぬ好奇心をくすぐるからな。
扉の先が何部屋なのかはわからなかったが、そこに金があるとケイは確信していた。見込みが外れたら? それなら次は向かいの執務室だ。その余裕がある――下でベスが見張ってくれているから。
ひとりでやれることなんざ、たかが知れてる。
おそらく昔話の盗賊ドノバンはひとりだったのだろう。ひとりであれもこれもやろうとして――そうしなければならないことはケイもしばしばだったが――高い鉄柵にぶら下がる干物に成り果てた。
俺はドノバンにならない。
ケイは真鍮のノブを回して部屋に入った。
一本の蝋燭に照らされた寝室で、ふたりは何も言わず、目を合わせすらしなかった。侵入後の手筈も前もって打ち合わせ済みだ。〝下の道〟で、ベスは予期せぬ事件や事故に遭ったり、思わぬ冒険をやり遂げたりしたかもしれないが、その話を聞くのは仕事が済んでからでいい。
ベスはケイの横を素通りして扉に向かう。そして聞き耳を立て、少し開けた扉から顔だけ出して左右をうかがい、後ろ手に信号を送る――〝無人〟だ。
ケイは窓を閉めてかんぬきをかけ直し、カーテンを引いた。
鉤縄は束ねて左肩に巻きつけるようにして担ぐ。計画どおりにいけば、もう鉤縄の出番はないから背負い袋に放り込んでもいいのだが、そううまくいくとは限らない。便利な道具はいつでも使えるように持っておきたかった。
――顔を上げるとベスはいなくなっていた。
それでいい。ベスは蝋燭もなしに一階に下りて、玄関まで向かわなければならない。下手に目が火の光に慣れる前に出るのが正解だ。
一方、ケイにはまだ蝋燭が必要だった。
ベスが姿を消した後、少し間をおいてケイも控えの寝室から廊下に出る。
邸内を物色するのはケイの役目だ。無駄な動きを減らし、効率よく盗って回るには目端を利かせなければならない。見込みのない場所を探って、時間を無駄にするのは危険だ。この別邸には使用人夫妻が住み込んでいて、今も地下の部屋にいるのだ。まず間違いなく寝ているだろうが……だからといって、ぼやぼやしている暇はなかった。
不慣れな者だと、無人の屋内に入る〝空き巣〟では明かりを手にし、誰かがいる場所に忍び込む〝居抜き〟の場合は無灯で――そんなふうに家探しするべきではないかと思うだろう。
逆だ。
屋外の誰かにカーテンの隙間などから、無人のはずの中で光源が動いているのを見られたら確実に怪しまれる。そんな危険は冒さなくていいし、誰もいない場所なら物色するにも少しは時間に余裕が持てる。〝空き巣〟に常時の照明は不要だ。ここぞという時、光が外に漏れる恐れがない時にのみ、火を灯せばいい。
それが〝居抜き〟では話が変わる。侵入後は手際のよさと速さが何よりも優先だ。短時間でめぼしい獲物を漁り、できるだけ早く逃走する。そのため手元に明かりを携えていたい。よしんば外の者が光に気づいたとしても、中の誰かが灯したものだと考えて、まず怪しまないだろう。
では外ではなく建物内にいる誰かに気づかれた場合はどうか。直ちに逃走――ではなく脱出に全力を傾けなければならない。
〝居抜き〟は侵入を悟られた瞬間に失敗である。明かりを手にしていようがいまいが関係ない。もちろん失敗しても逃げずに脅しと実力行使で中の者を制圧する――つまりその夜の仕事を〝押し込み強盗〟に切り替えることもできるが、そういう泥縄な手口をケイは好まなかった。悟られることなく侵入し、見つからず、目立った痕跡も残さず、逃走から何日も経って、こちらがすでに盗品を故買人に売り払うか、依頼者に渡した後でようやく何か盗まれたと発見されるのが理想だ。
ケイは廊下の左右にさっと目を走らせ、左手の蝋燭立てを膝のあたりまで下げた。
罠があるかもしれない。床に張った糸や紐に引っかかると大きな音が鳴る……そういう報知器の類が。
実際、ケイはかつての仕事で、組んだ老盗賊が罠にかかってしまい、ふたりして盗るものも盗らずにほうほうの体で逃げたことがある。老盗賊はケイよりも経験豊富だったが、その種の装置は比較的近年に発明された物なので、存在を知らずにいた。単純な仕掛けだが、我こそは不寝番なりと豪語して雇われようとする輩(不審者の間違いだろう)や、ご大層な金庫の錠前(金庫ごと盗むとか対処法は幾らでもあるが?)などよりも、そうした〝糸と鳴子〟式の報知器のほうがずっと盗賊避けになる。これは戦場の野営地で用いられていたのを都市向けに改造した罠だそうだが、正直、あまり〈王都〉に広まって欲しくない代物だった。
だが知っていれば、かわせないわけではない。
今頃、ベスは這うほど姿勢を低くして慎重に玄関に向かっているはずだ。隠密を重視して明かりを持たない時はそうやって壁際を進む。焦らなくていい。罠にかからないことに集中しろ。ケイが盗みを済ませて下りてくるまでに玄関の鍵を開けておく。そして使用人夫妻が地下から出てくるようなら、急いでケイに知らせられるように隠れて見張る。それがベスの役目だ。
何事もなければ、後はふたりで玄関から悠々と逃走できる。玄関の鍵が開いたままになるが、今回はそれでいい。他に侵入した形跡を残さなければ、家の者は施錠し忘れたと思い込みやすいというのもあるし、今夜の狙いは商人の隠し金、つまり被害を公にしにくい獲物だという点も大きい。盗みの発覚は確実に遅れる。
だが、運悪く使用人が一階に出てきたら、そこで侵入は終わりだ。
そうなったら、ケイは知らせにきたベスと一緒に、二階か三階の窓から脱出することになるだろう。まだ金目の物があったとしても諦めなければならない。口惜しいが盗賊の仕事とはそういうものだ。準備万端で、特にミスを犯したわけではなくても、少し幸運がなかっただけで欲しいものが手に入らないこともある。
だからといって出たとこ勝負な仕事は論外だ。捕まった盗賊に〈王都〉の司法は甘くない。くすねた富の大きさにもよるが、監獄送りと強制労働なら御の字で、盗った相手次第では片手くらい簡単に切り落とされる。それが嫌なら放免や釈放を求めて衛士や判事、獄吏に鼻薬を嗅がせることもできるが……どれほど足元を見られることか!
更には、これなら衛士にしょっぴかれたほうがましだった、ということすら起きうる。捕まった挙げ句、その場で激しい暴行を受けたり、最悪、雇い主の命令なら何でも従う冷酷な用心棒に処分されたりといったこともざらだった。法は窃盗には厳しいが、そうした〝私的制裁〟には甘い。貴族や金持ちが命じたものなら特に。
――要は引き際が肝心ということだ。
捕まって迎える悲惨な結末に比べたら、獲物を諦めることなど安い。それもあって多くの盗賊は、波止場の倉庫の中身や輸送馬車の貨物を根こそぎ奪うような大掛かりな仕事でなくても、二人組、三人組、更に大人数と徒党を組む。ひとりあたりの稼ぎは減るかもしれないが、偵察役や見張り役、連絡係、事前の内部潜入者など、作業を分担することで危険を避け、退路を確保し、密かで速やかな仕事を実現する。
今夜のケイとベスの計画もそうだった。
この程度の仕事なら、ケイはひとりでもこなせる自信があった。それでも、これはベスが見つけた仕事だということを抜きにしても、状況が許せばやはり誰かと組むだろう。脱出口を開き、危機の接近を見張ってくれる誰かがいれば、ケイは盗みに集中できる。
今、あの老盗賊――通り名は〝ご隠居〟――と組んでいたら、老人は玄関に向かいつつ、途中に罠があれば解除するか、それが無理なら後で下りてくるケイのためにさりげなくパース銅貨でも置いて目印を付けてくれるはずだ。〝ご隠居〟が同じ罠に二度もかかるほど間抜けでないことは言わずもがな、一度知った罠や警備には容易に対策してみせる。
ベスにはそこまで求めていない――今のところ。
ケイは右に歩を進めた。
ここは三階。左は下り階段の踊り場で見るべきものはない。突き当たりは出窓。そこはせり出していて、別邸正面を外から見れば、玄関ポーチの上の雨避け、簡易の屋根になっている。これは石工ヶ辻の住宅の多くに見られる造りだ。
出窓のカーテンが少し開いているのは、ベスが階段に最低限の明かりが入るように開けたのだ。この時刻、街灯の火はあったとしても消えかけだから、外の明かりは主に月や星のそれで、ごくわずかなものである。それでもあるとないとでは大違いだ。足を滑らせて物音を立てたり、罠にかかったりする確率をぐっと下げられる。カーテンは後でケイが下りる時に閉めればいい。続く一階への階段に光を入れられる、二階踊り場の窓のカーテンもベスは少し開けるだろう。
反対の右奥、突き当たりの扉は建物の主――若き商人ホーラーの寝室だ。ここは新築ではなく空き家を購入したものである。ならば間取りや各部屋の使い途は通り一遍のもののはずだ。一階にはまず玄関ホール。そこに来客の荷物やコートを預かるクローク、そして上り階段がある。奥の扉の向こうは居間兼応接室だ。金持ちが気取って〝パーラー〟とか呼ぶ、その種の居間の奥の壁には大きな両開きの窓があるものだが、ホーラー別邸の窓は小さい。建物の裏にほとんど余地がなく、窓を大きくしても他人の家の塀が殺風景なばかりだからだ。
居間の左右にも扉があって、ひとつは食堂に通じている。ここの場合は左の扉がそれで――下見の時に外から確認した――その食堂には正面から見て奥にも小さな扉がある。そちらからは短い廊下に出られて、下り階段があるだろう。地下の調理室や食料庫、ワインセラーから、料理や酒を運んでくるのは使用人の仕事だ。彼らが住み込む使用人部屋も地下である。
ベスは一階に下りたら玄関に直行して鍵を開け、上り階段の脇にでもうずくまり、使用人夫妻が地下から出てこないかどうか、耳を澄ませるだろう。玄関ホールへの扉が開くようなら、急いで階段を駆け上ってケイにご注進だ。
この手筈は〝ご隠居〟も同様だろうが、海千山千な老人のことだ。鍵を開けた後、ついでの仕事もするに違いない。安全だと判断するや、こっそり居間に忍び込む。食堂に入れば金の燭台や銀食器があるかもしれないが、それは狙わない。〝ご隠居〟のお目当ては別の扉、喫煙室への扉だ。そこの戸棚から煙草をくすねる。もちろん輸入ものの高級品――下町の街角で三パースも出せば買えるクズ煙草とは比較にならない、香り高い上物をあまり欲張らずに拝借する。売れば五シェール前後、銘柄によってはその二倍、三倍の稼ぎになるが、これは自分用である。老人は好みにうるさい愛煙家で、〈王都〉にはまれな盗まずとも生活に困らない盗賊だった。
〝ご隠居〟は隊商を三つも所有する大手商会の会計を見事に勤め上げた人物で、引退後は以前の勤め先から支払われる年金で悠々自適の晩年を過ごしていた。長年連れ添った妻との間には子がいて孫もいる。そんな経歴の御仁が盗みを働く理由は、本人の言葉を借りれば「持って生まれた性分」だった。
幼い頃から〝ご隠居〟には盗癖があった。
盗むのは日々の糧ではなく喜びで、やらずにはいられない。おまけに才能にも恵まれていた。盗賊になったのはいつからなのか、ケイは知らなかったが、商会に勤めていた時にはすでにそうだっただろう。にもかかわらず、家族やかつての同僚たちはそれを知らない。〝ご隠居〟がちょくちょく下町の酒場に足を運ぶのは――もちろん仕事のためだが――その手の騒がしい場所で煙草を吹かすのを愛しているからだと思われていた。
ケイは〝ご隠居〟に商会で横領したことはないのか? と尋ねたことがある。
「あるとわかり切っている金を盗って面白いかね?」
それが答えだった。
この熟練の老盗賊は、どこそこの貴族が所蔵する絵画を盗るとか、富豪の金庫を狙うといった話にはすげなく紫煙をくゆらせるばかりで、あそこにはたぶん何かがありそうだと聞くと、火をつけた煙草が灰になるのも構わず放ったらかしにして身を乗り出してきた。そしてまんまと見込みが図に当たって稼ぎを得ると、肺から煙を吐き出しつつ、
「いやはや、あるところにはあるものだね」
と含み笑いを漏らしながら言うのだった――心底満足そうに。
卑しい生まれの食い詰め者がお定まりの盗賊たちに対して、〝ご隠居〟は生まれも育ちも恵まれていた。元からいい暮らしをして懐にも余裕がある。ゆえに、まるで煙草の銘柄のように好みの仕事を選べるし、たいていの盗賊が不案内な金持ちの習慣や住まいの細部にも通じていた。その知識は当の本人が獲物を見定め、それを盗って「やはりあった」と喜ぶ上で大いに役立った。
そんなやり口をケイもずいぶんと盗ませてもらった。
小金持ちが住む建物の一階は居間などの共有空間。これはもっと裕福なお大尽の邸宅でもだいたいそうなっているが、富豪のお屋敷に比べれば全体に手狭なので、貯蔵庫だけでなく調理場や使用人の部屋も地下に配される。
二階にはおおむね客室が並び、三階が家族の個人的空間だ。その一番奥は主人、または主人夫妻の寝室である……。侵入する前から、こうしたことがわかるのは〝ご隠居〟と組んで仕事をしたおかげだ。
ホーラー別邸の間取りが想定の範囲内だとすれば、二階は端から無視していい――とケイは考えていた。客が寝泊まりして自由に動き回る階に、隠し金を置いたりはしないだろう。同様の理由で一階も物色する必要がない。こちらは客に加えて使用人も頻繁に出入りするからなおさらだ。家の主人が極めつきに天邪鬼であるか、盗賊の裏をかけるほど擦れた人物でもない限り、まず間違いない。ベスの調べではホーラーは天邪鬼でも擦れっ枯らしでもない。やり手ではあるが、青臭さが抜けて強欲さが鎌首をもたげてきたばかりのお坊ちゃんだ。
――金は三階にあるとして、どこに?
寝室から出てすぐ向かいに扉があるが、これはもうひとつの控えの寝室の扉だ。今、出てきたばかりの部屋にはシングルベッドがあった。妹用だろう。ということは、こちらの扉の先は両親用の寝室でダブルベッドがある。いずれも金を置くとは思えない。
奥の主人の寝室に隠している? そこそこありうる話だ……が、それはホーラーが臆病な猜疑心の塊だった場合だ。違う。ベスが語った若き商人の人物像にそぐわない。物怖じせず、堂々としていて、百天秤街で店を切り盛りできるだけの気概がある男。それが寝床に硬貨を敷き詰めて、ようやく枕を高くできるといった、せせこましい振る舞いをするとは思えなかった。
まだ他にも扉はふたつある。突き当たりの手前、左右の壁に向き合ってひとつずつ。
ケイは蝋燭の明かりでふたつの扉を照らし、見比べた。
蝋燭立てを少し高く掲げると、暗さに慣れたケイの目に三階の廊下が浮かび上がる。塵ひとつなく、象牙色の壁紙も上等できれいに貼られていた。わずかに青みがかった白で淡く描かれた模様は蘭の花。真鍮のランプかけと調和がとれている。そういえば玄関ポーチ階段脇の鉢植えの花も蘭だった。そちらの色は昨今〈王都〉で流行りの紫。
足元の絨毯は複雑な幾何学模様の舶来品だ。言うまでもなくホーラーの店のものだろう。この別邸を粗暴な盗賊団が襲ったなら、引っ剥がして奪うはずだ。まともに一巻持ち出して故買にかければ、売り値はシェール銀貨どころかクロン金貨で設定される獲物である。
だが、ケイが屈んで明かりを下げ、絨毯に目を凝らしたのは盗るためではなかった。盗ろうとしたところで、これはベスとふたりでやる〝居抜き〟ではどうにもならない――ケイは絨毯の乱れや擦れ具合を確認していた。
向かって右の扉の前の絨毯には数え切れないほど踏まれた形跡がある。使い込まれている部屋の入り口だ。奥の寝室の扉の前もほぼ同じ。一方、左の扉は絨毯の様子から察するに、控えの寝室ふたつと同様に、あまり使われていないことが見て取れた。
右の部屋は別邸の執務室だ。そこでホーラーは店から持ち帰った事務仕事をしたり、読書に――そういう習慣があればだが――耽ったりしているだろう。
すると左の部屋は何か? 家主が所帯持ちなら妻の居室かもしれない。夫人はそこで編み物をしたり、手に入れたばかりの衣装や装飾品を身に着けて鏡と向き合い、着飾った自分にうっとりしたりするのだ。子があれば子供部屋でもおかしくない。しかしホーラーは独身だ。本当に読書家なら図書室ということもありうるし(これは客に蔵書を自慢するために二階に配されることもある)、楽器を奏でるのが趣味なら(そんなことをベスは言っていなかったが)演奏室……だが、これも違うだろう。主人の娯楽部屋ならもっと使っているはずだ。
この部屋に金がある。
左の扉の前に立ち、ケイはノブのあたりを蝋燭の火で照らした。マホガニーの扉に真鍮のノブ。手入れはよく、ピカピカに磨き上げられている。鍵はかかっていない。
いいぞ、ホーラー。
大して使いもしないのに主人が鍵をかける部屋があったら、使用人のいらぬ好奇心をくすぐるからな。
扉の先が何部屋なのかはわからなかったが、そこに金があるとケイは確信していた。見込みが外れたら? それなら次は向かいの執務室だ。その余裕がある――下でベスが見張ってくれているから。
ひとりでやれることなんざ、たかが知れてる。
おそらく昔話の盗賊ドノバンはひとりだったのだろう。ひとりであれもこれもやろうとして――そうしなければならないことはケイもしばしばだったが――高い鉄柵にぶら下がる干物に成り果てた。
俺はドノバンにならない。
ケイは真鍮のノブを回して部屋に入った。
メッセージを送る!