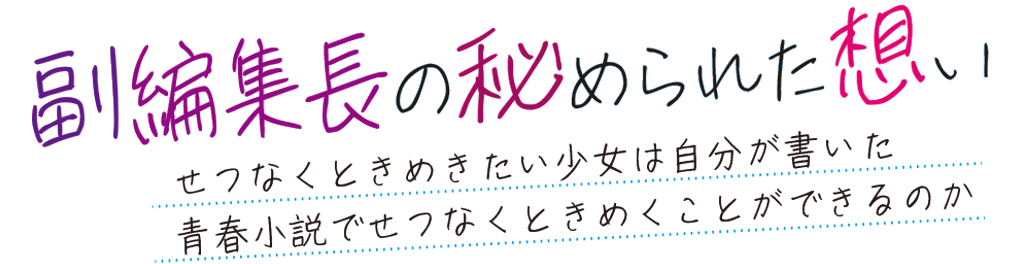第1章 告白のせつないときめきと副編集長からの挑戦状【前編】
「私がこんな事を言っても、あなたは困るだけかもしれないけれど、もう、自分の気持ちを。……抑えられないんだよ。だから、聞いて欲しいんだ」
いつもはクールなメガネキャラ、新聞部では原稿の最終チェックを担当するアンカーマンをやっている副編集長が、耳まで真っ赤にしながら、言葉を絞り出すようにして訴えかけてくる。
放課後の新聞部部室、窓からは秋の夕暮れの光が入ってきてデスクやパソコンを茜色に染めている。部室にいるのが俺と副編集長の二人っきりであれば、ラブストーリーで良く見る告白シーン、しかも典型的なやつ。俺みたいな高校生男子であれば絶対そう勘違いするぞ。二人っきりなら。
二人っきりじゃないけどな!
部室には、編集長も、後輩の福地も、新体操部の芽宮もいる。この状況ではさすがの俺も勘違いしようがない。これは愛の告白ではない。勘違いはしないが、副編集長は何かを告白しようとしていることはわかる。そして、それはとても恥ずかしい、告白することをためらわせるほどの内容だということだ。
俺以外の三人は、副編集長の必死ささえ感じさせる真剣な様子に呑まれて、思考が停止していると見えるが。
俺にだけはわかる。なるほど、理解した、わかった。副編集長がなにを告白しようとしてるか。俺にはわかるぞ。
だから俺は、副編集長に伝えてあげることにする。
「大丈夫だ。きみは小説を、あるいは漫画かもしれないけど、書いた。それがどんな内容であっても恥ずかしがることはない。それがきみが心から表現したいもの、きみの魂から生まれたものであるならば、どんなものであってもそれは尊いものだから、俺が読んだとしてもそれを笑ったり、きみを軽蔑したりすることは絶対にないと誓う。だから、大丈夫だ」
「ちょ、おいおい」
「センパイっ、それは」
編集長と芽宮は面食らっている。
「茶化す場面じゃないと思うンすけどねー。副編集長、真面目に相談したいみたいッスよ」
呆れたように言うのは福地だ。心外だ。
「茶化してなんかないぞ。今の俺は副編集長以上に真面目だと断言できる」
「いきなり小説とか漫画の話を始めるの、どこが真面目ッスか。あの、副編集長、リテイクでお願いできるッスか? 聞いて欲しい、の続きから。オレは真面目に聞くッスから」
うつむいて黙ってしまっていた副編集長が、顔を上げる。
「どうして」
顔から赤みが引いて、驚いたような表情になっている。
「そこまでわかるんだい? まだ何も言っていないのに?」
「え? え?」
芽宮は副編集長と俺の間で視線を行ったり来たりさせている。
「ゴメン、話についていけない」
右手で顔を覆う編集長。
「まさかの正解!? ワケわかんないッスよ!」
ふふふ。では謎解きといこうじゃないか。
「ヒントはふたつあった。
一つ目、副編集長が切り出したタイミング。今日は水曜日だ。芽宮が、『戦国ワルキューレ』の橘華の演技について、原作者の俺に相談にくる日、新聞部の仕事が一段落した今、このとき。いつもは小説をメインにした創作論を始めていた時間だ。当然、副編集長が持ち出す話もそれに類する相談だと想像できる。
二つ目、副編集長の態度だ。彼女はとても恥ずかしがっていて、ためらっていた。創作に関して、言うのをためらうほど恥ずかしいことといったらひとつしかない。それは自分が創作したものに関することだ。そして、それを読んでもらうことだ。
だから、副編集長は小説を、あるいはマンガかもしれないが、書いた。そしてそれを俺達に読んでもらおうとしている。俺はそう判断した。そういうことだ」
「ツッコミことはいろいろあるのに、当たってるみたいだから何も言えねー」
「いや、つーか、創作が恥ずかしいって、読んでもらうのに勇気が要るって、そんなワケないっしょ、恥ずかしいなら書かなきゃいいし、読んでもらうために書くんだし」
わかってないなー福地よ。まあ、これは創作をしたことがないとわからないことだから、仕方ないともいえる。
「あのな、創作したいって欲求は、複雑なんだ。誰かにわかって欲しい、誰かに伝えたいから表現をする、それが創作だと、普通は思うよな?」
「そりゃそうでしょ。何も恥ずかしいことなんてないじゃないッスか」
「そうだとすれば、視覚や聴覚で伝えればいいだろ? 会って、声に出して、なんなら身振り手振り加えて思う存分、わかって欲しいこと、伝えたいことを表現すればいい。文章を書いたり絵を描いたりするってのは、けっこう手間と時間がかかる。なんでわざわざそんな、まだるっこしいことをするんだ?」
「え? いや、それは。そうしないと伝わらないくらい複雑な内容だから? 形に残して、不特定多数の人に見てもらいたいから? とか?」
「もちろんそういう場合もあるだろう。だが、
・他人に見られるのは恥ずかしいけれど、表現したい
あるいは、
・表現したいけれど、恥ずかしくて他人に見られたくない
という人のほうが多いんだ。それも圧倒的に多い。100人いたら99人がそう思う、それほど恥ずかしいことなんだ。
だってそうだろう? 大勢の人の前に立つってだけで緊張してしまうのが普通の人だ。わかって欲しいこと、伝えたいことを表現するのは、簡単に聞こえるけど実はとても勇気が必要なことなんだ。
ファッションや化粧だってそうだろ? あれだって一種の自己表現、創作とも言えるよな。
しかし、だ。
えーと、福地よ、お前だってファッションには気を遣っているよな? ウチの標準服の学ランじゃなくて私服だし、髪型だって毎日キメてる感じだ」
「いきなりッスね。オトコに言われるの不気味なんスけど。普通っしょ、これくらい」
「そう、普通なんだよな、お前にとっては。
・格好良く見られようとしてる
・女にアピールするために毎朝鏡の前で15分かけている
とかいうふうには思われたくないってことだよな? いや、実はそうなんだろ、って言ってるわけじゃないぞ。
あくまで自分のためにやっている、見て欲しくてやってるわけじゃない、これがオレにとっての普通だ、そういう主張がお前にとってのファッションってわけだ。
伝えること、見てもらうことが目的ならば、自己主張が強い、目立つことがいいこととされるはずだ。でも、さりげなさや自然な感じが好きな人もいるし、自分らしさが一番って話になるだろ? 主張はするけど、見られることが目的ではない、注目されすぎるのは恥ずかしいってことだよな」
福地は不満そうだが、渋々と頷いた。
「まあ。そうなるッスかね」
「創作ってのは、ファッションよりもさらに直接的で濃厚な自己主張になる。創った人の想いが、主張が、魂が凝縮されたものだ。特に小説やマンガといった物語形式の創作の中には、登場人物というペルソナを借りて、正も負も、光も闇も、聖も邪も、綺麗事だけじゃない全てが詰め込まれる。それは創作者の全てが詰まったひとつの世界と言っていい。創った人にとってはうひとりの自分なんだ。それを見てくれ、読んでくれと副編集長は言っている。これがどれだけすごいことか、勇気の要ることか、わかるだろう?」
「いや、あのね、自己主張とか世界とか、私が書いたのはそんな大したものではなくて、ね? ちょっと書いてみただけだし、初めてだし、私は素人だし」
「初めてとか素人とかは関係ない。創作するというのはそういうことなんだ。
もちろん、技法としての上手い下手はあるだろう。副編集長の場合、新聞部としての経験があるから文章力には問題ないが、物語の構築力は不明だな。だが、問題ない。俺が今まで、どれだけの数の創作物、小説や映画を楽しんできたと思っているんだ? 世間的には駄作、失敗作といわれるものにだって、俺はその中の想いを、主張を読み取って楽しむことができるぞ。創る側だけではなく、楽しむ側としてもプロを自負している。さあ、恥ずかしがらずに副編集長の全てを見せてくれ」
真っ赤になって黙り込んでしまった副編集長を前にして、さすがの俺も失敗を悟る。
「あ。すまん、そうだ、それが恥ずかしいって話だったよな。ごめんな、無神経で」
だからそういう意味ではなくて、とかもごもご言っている副編集長は初めて見る。あまり感情を出さない、怒ったり泣いたりするのは見た事がないから、ちょっと新鮮で可愛い、なんて思っていたら、もう、見るな! と背中を向けられた。どうしよう、ホント可愛いぞ。
副編集長のようすを見かねたか、編集長が話を引き取る。
「お前は恥ずかしくないのかよ。って聞くまでもないかー」
「俺は、表現したい云々じゃなくて、俺の理想の『格好良く戦う女の子』を見て欲しい、だったからな。読んでもらうのが大前提だから、恥ずかしいとかは別に」
「そんなんでどうして、恥ずかしいって気持ちについて偉そうに語れるのかねー」
「たぶんですけど」
芽宮だ。
「いつもの、Gさんが言ってた、じゃないですか? ベテラン編集者だったらしい、んでしょう?」
「まー正解。あの人に言わせると、そういう恥を乗り越えるだけで表現者、創作者としての第一段階はクリアしたことになるんだってさ。そして、それが出来るのは100人にひとりくらいしかいない、とか」
「そりゃ言い過ぎっしょ。『小説家になろう』やコミケは盛り上がってるっスよ? アレみんな、恥ずかしいのを我慢しながらやってるんスか? とてもそうは思えないッスけど」
「我慢しながらってんじゃなくて、見られて喜んでるよなー。露出狂かよ。それが十万人単位とか、さすがヘンタイ大国日本」
「盛り上がってるのはお客さんも含めての話だ。書いて、コミケに出す、なろうに載せるって人よりは、読んで楽しむ人のほうが多いのは確かだろ?
それにな、恥ずかしいのを我慢しながら書き続けることが、実は創作においてとても大事なこと、らしい。これもGさんの受け売りな。恥を乗り越えるのが第一のハードルだけど、恥を捨てちゃいけないんだと。
えーと、なんだったかな、そう、表現したい、でも見られるのは恥ずかしい、そういうアンビバレンツな、葛藤? を通して、表現がさらに磨かれる、純化される、濃縮される、みたいな? 大麦が発酵してアルコールになって、それを何回も蒸留して度数を高めて、さらに樽の中で5年10年熟成するなんて手間をかけて旨いウイスキーが生まれるように、見られる事の葛藤を繰り返して創作物に個性が付与される、とかなんとか。俺は酒呑まんからわからんけど、あのときGさん酔っ払ってた感じだな。呑みながら電話してたよ、絶対」
「あ、そういう意味なら、なんとなくわかります」
意外。芽宮にはわかるらしい。酒呑まないのに。
「演技について、観る人を常に意識しろ、と言われるのと通じる気がします。観られるのが恥ずかしいって気持ちを完全に捨てしまうのは、お客さんを意識から外してしまうことにもなりますから」
なるほど。そう理解するか。さすが、橘華役で人気の新人俳優は違うな。
ちなみに、Gさんの話には続きがあって、
『お前の書く小説には、そういう意味の個性がない。お前は恥ずかしがっていないからな。すっきり呑みやすいけどクセがない、万人向けの味だからこそ売れている、とも言える。だけどな、もっと練れた、個性的な味が欲しくなるんだよ、時と場合によってはな。失敗とか恥とか挫折とか苦労とか、もう書きたくない、みたいな想いをあと百回くらい経験してみてくれよ。そしたらお前も、30年もののスコッチみたいな味が出せるようになる。長生きして、もっともっと俺を楽しませてくれよな』
生まれてからまだ20年も生きてない若造になにを言ってるんだか。酔っ払うとGさんはたまにそういうことになる。
「まあ、仮に、あくまで仮になー? 布留田の言うとおりだったとしても、だ。副編集長、もっと俺を信用してくれもいいんじゃないかと思うぞー?」
こちらに背を向けたままの副編集長に、編集長が声をかけた。
「君が何を書いたのかはわからないけど、それを読んで俺が笑ったり、君を軽蔑したりすると思うのか? だったら悲しいぞー。2年以上、新聞部仲間として付き合ってる俺としちゃあさ。いつもは真面目な君に、少しくらいヘンな趣味があったって、そりゃ愛嬌ってモンじゃないか」
おっと編集長、うかつだな。ここは副編集長を庇わせてもらおう。
「おいおい、その認識じゃあ副編集長はもっと困っちゃうぞ。
ジキルとハイドみたいな、人間の二面性ってのは小説の話だけじゃない。凶悪犯の知り合いがインタビューで「普通の人でした。あんな事をするなんて信じられません」とか答えてるだろ? 人は上っ面で見えるだけの単純な存在じゃない、心の中にはいろいろと複雑な想いを秘めているのが当然なんだ。ちゃらんぽらんに見えるけど実は他人の顔色を気にしてそう振る舞っているだけだったり、異性に興味がないような顔をしているのは、人一倍強い性欲を抑えているだけだったりな。
それは責められることじゃない、悪いことじゃないんだ。誰だってそうなんだから、自分自身でもよくわからない複雑な深層自我をかろうじてコントロールしながら、上っ面だけでも取り繕って社会に適応しなきゃいけないのが文明社会の住民ってもんだ。 そう、創作表現は、そういう、抑圧された自我、もうひとりの自分を解放する唯一の手段であるともいえる。だから楽しいんだ、だから気持ちいいんだ。だからみんな、表現はしてみたい、でも恥ずかしいんだよ。
副編集長が、真面目でクールなその仮面の下に、どんな自分を隠していたとしても俺は驚かない、むしろ楽しみだ。仮面がクールであればあるだけ、真面目であればあるだけ、その下で内面は煮詰められて濃厚になる、秘められた欲望が磨かれて純化される。そうやって創作物は光り輝く、らしいぞ、Gさんに言わせると。
さあ副編集長、きみの内面を、秘められた欲望をさらけ出すんだ! 俺は決してそれを否定しない!」
「ひっ……」
こっちを振り向いた副編集長は、もう恥ずかしがってなんかいなかった。むしろ怒髪天という感じだ。目をつり上げて、俺を糾弾するように指をつきつけてくる。
「人聞きの悪いことを言わないでもらえるかな! なんなんだいさっきから、まだ読んでもいないのに勝手に決めつけて! 私の魂とかもうひとりの私とかヘンな趣味とか取り繕ってるとか秘められた欲望とか! 凶悪犯扱いまでしてくれて! 私、そこまで酷いことを言われるようなことを君にしたかい!? してたのなら言ってほしいものだね!」
「いや、仮にそうであっても俺は気にしないって言っただけで」
「そこは気にしろ! そんな想像をされるだけでも気分が悪いんだよ!
そんなおかしなものを私が書けるわけないでしょう! ただの青春もの、女子高校生のラブストーリー! 私が書いたのは!」
「うえっ!?」
おかしな声を上げたのは福地だ。
「副編集長が、ラブストーリーッスか?」
「そうだよ、文句でもあるのかい? 惚れたはれたのラブ、恋愛もの。キャラじゃないのはわかっている、笑えばいいさ、君のキャラでしょう、それが」
「いや、ここで笑うような空気の読めないキャラだと思われてるってののショックがでかすぎなんスけど。まー、副編集長のキャラじゃないってのはそうかもだけど、高校生主人公でラブストーリー、いいんじゃないスか? 等身大で」
女子高生の副編集長が、女子高生のラブストーリーを書いた。なるほど、等身大だが。等身大すぎて、フツーだな、と俺は思ってしまう。フツーじゃ面白くないってGさんも言ってたし、もっとひねれよ、と。だがもちろん口には出さない。さすが俺、空気が読める。
「わたしは、読んでみたいです、副編集長さんの書いたラブストーリー。そういうのが好きなんですか?」
「いや、別に」
しれっと否定する副編集長。照れ隠し、という感じではない。
「嫌いでもないけれど、好きってわけじゃないのだけどさ」
「じゃあなんで」
芽宮は不思議そうだ。
「ラブストーリーを書いたんですか?」
「……不意打ちだったから」
「不意打ち?」
「予想もしていないところから、いきなり殴ってくるような小説があったんだよ。それがとても衝撃的で。あんなにせつない気持ちになるのは初めてで、今でもあれ以上のものは見つからない。だから忘れられなかったんだ」
「私が読む小説は、翻訳もののミステリーとかサスペンスとか、そういうものが多いんだけれど。それも新刊ではないんだ、古本屋の文庫棚にそういうコーナーがあって、中学生の頃、安いから買って、読んでみたらはまってしまって、それからずっとそのコーナーがお気に入りなんだ。ジャンルは、モダンホラー、とか言うのかな? 巻末の解説に書いてあったけれど」
「あーなんか聞いたことあるなー」
編集長が、もどかしそうな感じに人差し指を回す。
「スティーヴン・キングとか? 確かに、新刊じゃ見ないよな、ああいうホラー小説って。たまにあっても日本の作家だし。昔、流行ったジャンルってことなのかねー? Gペディアではどうよ、そのへん?」
「その言い方じゃ、俺がGさんの受け売りしかしてないみたいじゃないか。キングとかクーンツとかなら俺だって読んだことあるぞ、モダンホラーな、親父の本だったから、3、40年前に日本でも流行ったんだろうな」
「いや、昔じゃん。モダンじゃないじゃん」
「当時としてはモダンって意味だろ。こう、モンスターとかオカルトとかで人がわーきゃー叫んだり死んだりするそれまでのホラーじゃなくて、社会の裏とか個人の心の中の闇の部分とかに焦点を当てて、じっとりねっとりぞくぞくさせる、それが新しい、それが今風、それこそがモダンホラー、そんな感じ、じゃないか?」
「映画の原作で、キングは知ってます。『キャリー』とか『ペット・セメタリー』とかは観たことがあります。最近だと『ミッドサマー』とか、ああいう感じですか?」
あれは映画だから絵的にハデにするために、わーきゃー叫んだり死んだりする成分が多めに足されていた気がするが。モダンホラーのじっとりねっとりしたニュアンスはやはり小説ならではのものだよな、とか思いつつ、俺はGペディアではなくWikipediaを検索。
「映画の『キャリー』は1976年で、『ペット・セメタリー』が1989年か。やっぱりそれくらいの時期に、日本でも流行ったんだろうな」
いつもはクールなメガネキャラ、新聞部では原稿の最終チェックを担当するアンカーマンをやっている副編集長が、耳まで真っ赤にしながら、言葉を絞り出すようにして訴えかけてくる。
放課後の新聞部部室、窓からは秋の夕暮れの光が入ってきてデスクやパソコンを茜色に染めている。部室にいるのが俺と副編集長の二人っきりであれば、ラブストーリーで良く見る告白シーン、しかも典型的なやつ。俺みたいな高校生男子であれば絶対そう勘違いするぞ。二人っきりなら。
二人っきりじゃないけどな!
部室には、編集長も、後輩の福地も、新体操部の芽宮もいる。この状況ではさすがの俺も勘違いしようがない。これは愛の告白ではない。勘違いはしないが、副編集長は何かを告白しようとしていることはわかる。そして、それはとても恥ずかしい、告白することをためらわせるほどの内容だということだ。
俺以外の三人は、副編集長の必死ささえ感じさせる真剣な様子に呑まれて、思考が停止していると見えるが。
俺にだけはわかる。なるほど、理解した、わかった。副編集長がなにを告白しようとしてるか。俺にはわかるぞ。
だから俺は、副編集長に伝えてあげることにする。
「大丈夫だ。きみは小説を、あるいは漫画かもしれないけど、書いた。それがどんな内容であっても恥ずかしがることはない。それがきみが心から表現したいもの、きみの魂から生まれたものであるならば、どんなものであってもそれは尊いものだから、俺が読んだとしてもそれを笑ったり、きみを軽蔑したりすることは絶対にないと誓う。だから、大丈夫だ」
「ちょ、おいおい」
「センパイっ、それは」
編集長と芽宮は面食らっている。
「茶化す場面じゃないと思うンすけどねー。副編集長、真面目に相談したいみたいッスよ」
呆れたように言うのは福地だ。心外だ。
「茶化してなんかないぞ。今の俺は副編集長以上に真面目だと断言できる」
「いきなり小説とか漫画の話を始めるの、どこが真面目ッスか。あの、副編集長、リテイクでお願いできるッスか? 聞いて欲しい、の続きから。オレは真面目に聞くッスから」
うつむいて黙ってしまっていた副編集長が、顔を上げる。
「どうして」
顔から赤みが引いて、驚いたような表情になっている。
「そこまでわかるんだい? まだ何も言っていないのに?」
「え? え?」
芽宮は副編集長と俺の間で視線を行ったり来たりさせている。
「ゴメン、話についていけない」
右手で顔を覆う編集長。
「まさかの正解!? ワケわかんないッスよ!」
ふふふ。では謎解きといこうじゃないか。
「ヒントはふたつあった。
一つ目、副編集長が切り出したタイミング。今日は水曜日だ。芽宮が、『戦国ワルキューレ』の橘華の演技について、原作者の俺に相談にくる日、新聞部の仕事が一段落した今、このとき。いつもは小説をメインにした創作論を始めていた時間だ。当然、副編集長が持ち出す話もそれに類する相談だと想像できる。
二つ目、副編集長の態度だ。彼女はとても恥ずかしがっていて、ためらっていた。創作に関して、言うのをためらうほど恥ずかしいことといったらひとつしかない。それは自分が創作したものに関することだ。そして、それを読んでもらうことだ。
だから、副編集長は小説を、あるいはマンガかもしれないが、書いた。そしてそれを俺達に読んでもらおうとしている。俺はそう判断した。そういうことだ」
「ツッコミことはいろいろあるのに、当たってるみたいだから何も言えねー」
「いや、つーか、創作が恥ずかしいって、読んでもらうのに勇気が要るって、そんなワケないっしょ、恥ずかしいなら書かなきゃいいし、読んでもらうために書くんだし」
わかってないなー福地よ。まあ、これは創作をしたことがないとわからないことだから、仕方ないともいえる。
「あのな、創作したいって欲求は、複雑なんだ。誰かにわかって欲しい、誰かに伝えたいから表現をする、それが創作だと、普通は思うよな?」
「そりゃそうでしょ。何も恥ずかしいことなんてないじゃないッスか」
「そうだとすれば、視覚や聴覚で伝えればいいだろ? 会って、声に出して、なんなら身振り手振り加えて思う存分、わかって欲しいこと、伝えたいことを表現すればいい。文章を書いたり絵を描いたりするってのは、けっこう手間と時間がかかる。なんでわざわざそんな、まだるっこしいことをするんだ?」
「え? いや、それは。そうしないと伝わらないくらい複雑な内容だから? 形に残して、不特定多数の人に見てもらいたいから? とか?」
「もちろんそういう場合もあるだろう。だが、
・他人に見られるのは恥ずかしいけれど、表現したい
あるいは、
・表現したいけれど、恥ずかしくて他人に見られたくない
という人のほうが多いんだ。それも圧倒的に多い。100人いたら99人がそう思う、それほど恥ずかしいことなんだ。
だってそうだろう? 大勢の人の前に立つってだけで緊張してしまうのが普通の人だ。わかって欲しいこと、伝えたいことを表現するのは、簡単に聞こえるけど実はとても勇気が必要なことなんだ。
ファッションや化粧だってそうだろ? あれだって一種の自己表現、創作とも言えるよな。
しかし、だ。
えーと、福地よ、お前だってファッションには気を遣っているよな? ウチの標準服の学ランじゃなくて私服だし、髪型だって毎日キメてる感じだ」
「いきなりッスね。オトコに言われるの不気味なんスけど。普通っしょ、これくらい」
「そう、普通なんだよな、お前にとっては。
・格好良く見られようとしてる
・女にアピールするために毎朝鏡の前で15分かけている
とかいうふうには思われたくないってことだよな? いや、実はそうなんだろ、って言ってるわけじゃないぞ。
あくまで自分のためにやっている、見て欲しくてやってるわけじゃない、これがオレにとっての普通だ、そういう主張がお前にとってのファッションってわけだ。
伝えること、見てもらうことが目的ならば、自己主張が強い、目立つことがいいこととされるはずだ。でも、さりげなさや自然な感じが好きな人もいるし、自分らしさが一番って話になるだろ? 主張はするけど、見られることが目的ではない、注目されすぎるのは恥ずかしいってことだよな」
福地は不満そうだが、渋々と頷いた。
「まあ。そうなるッスかね」
「創作ってのは、ファッションよりもさらに直接的で濃厚な自己主張になる。創った人の想いが、主張が、魂が凝縮されたものだ。特に小説やマンガといった物語形式の創作の中には、登場人物というペルソナを借りて、正も負も、光も闇も、聖も邪も、綺麗事だけじゃない全てが詰め込まれる。それは創作者の全てが詰まったひとつの世界と言っていい。創った人にとってはうひとりの自分なんだ。それを見てくれ、読んでくれと副編集長は言っている。これがどれだけすごいことか、勇気の要ることか、わかるだろう?」
「いや、あのね、自己主張とか世界とか、私が書いたのはそんな大したものではなくて、ね? ちょっと書いてみただけだし、初めてだし、私は素人だし」
「初めてとか素人とかは関係ない。創作するというのはそういうことなんだ。
もちろん、技法としての上手い下手はあるだろう。副編集長の場合、新聞部としての経験があるから文章力には問題ないが、物語の構築力は不明だな。だが、問題ない。俺が今まで、どれだけの数の創作物、小説や映画を楽しんできたと思っているんだ? 世間的には駄作、失敗作といわれるものにだって、俺はその中の想いを、主張を読み取って楽しむことができるぞ。創る側だけではなく、楽しむ側としてもプロを自負している。さあ、恥ずかしがらずに副編集長の全てを見せてくれ」
真っ赤になって黙り込んでしまった副編集長を前にして、さすがの俺も失敗を悟る。
「あ。すまん、そうだ、それが恥ずかしいって話だったよな。ごめんな、無神経で」
だからそういう意味ではなくて、とかもごもご言っている副編集長は初めて見る。あまり感情を出さない、怒ったり泣いたりするのは見た事がないから、ちょっと新鮮で可愛い、なんて思っていたら、もう、見るな! と背中を向けられた。どうしよう、ホント可愛いぞ。
副編集長のようすを見かねたか、編集長が話を引き取る。
「お前は恥ずかしくないのかよ。って聞くまでもないかー」
「俺は、表現したい云々じゃなくて、俺の理想の『格好良く戦う女の子』を見て欲しい、だったからな。読んでもらうのが大前提だから、恥ずかしいとかは別に」
「そんなんでどうして、恥ずかしいって気持ちについて偉そうに語れるのかねー」
「たぶんですけど」
芽宮だ。
「いつもの、Gさんが言ってた、じゃないですか? ベテラン編集者だったらしい、んでしょう?」
「まー正解。あの人に言わせると、そういう恥を乗り越えるだけで表現者、創作者としての第一段階はクリアしたことになるんだってさ。そして、それが出来るのは100人にひとりくらいしかいない、とか」
「そりゃ言い過ぎっしょ。『小説家になろう』やコミケは盛り上がってるっスよ? アレみんな、恥ずかしいのを我慢しながらやってるんスか? とてもそうは思えないッスけど」
「我慢しながらってんじゃなくて、見られて喜んでるよなー。露出狂かよ。それが十万人単位とか、さすがヘンタイ大国日本」
「盛り上がってるのはお客さんも含めての話だ。書いて、コミケに出す、なろうに載せるって人よりは、読んで楽しむ人のほうが多いのは確かだろ?
それにな、恥ずかしいのを我慢しながら書き続けることが、実は創作においてとても大事なこと、らしい。これもGさんの受け売りな。恥を乗り越えるのが第一のハードルだけど、恥を捨てちゃいけないんだと。
えーと、なんだったかな、そう、表現したい、でも見られるのは恥ずかしい、そういうアンビバレンツな、葛藤? を通して、表現がさらに磨かれる、純化される、濃縮される、みたいな? 大麦が発酵してアルコールになって、それを何回も蒸留して度数を高めて、さらに樽の中で5年10年熟成するなんて手間をかけて旨いウイスキーが生まれるように、見られる事の葛藤を繰り返して創作物に個性が付与される、とかなんとか。俺は酒呑まんからわからんけど、あのときGさん酔っ払ってた感じだな。呑みながら電話してたよ、絶対」
「あ、そういう意味なら、なんとなくわかります」
意外。芽宮にはわかるらしい。酒呑まないのに。
「演技について、観る人を常に意識しろ、と言われるのと通じる気がします。観られるのが恥ずかしいって気持ちを完全に捨てしまうのは、お客さんを意識から外してしまうことにもなりますから」
なるほど。そう理解するか。さすが、橘華役で人気の新人俳優は違うな。
ちなみに、Gさんの話には続きがあって、
『お前の書く小説には、そういう意味の個性がない。お前は恥ずかしがっていないからな。すっきり呑みやすいけどクセがない、万人向けの味だからこそ売れている、とも言える。だけどな、もっと練れた、個性的な味が欲しくなるんだよ、時と場合によってはな。失敗とか恥とか挫折とか苦労とか、もう書きたくない、みたいな想いをあと百回くらい経験してみてくれよ。そしたらお前も、30年もののスコッチみたいな味が出せるようになる。長生きして、もっともっと俺を楽しませてくれよな』
生まれてからまだ20年も生きてない若造になにを言ってるんだか。酔っ払うとGさんはたまにそういうことになる。
「まあ、仮に、あくまで仮になー? 布留田の言うとおりだったとしても、だ。副編集長、もっと俺を信用してくれもいいんじゃないかと思うぞー?」
こちらに背を向けたままの副編集長に、編集長が声をかけた。
「君が何を書いたのかはわからないけど、それを読んで俺が笑ったり、君を軽蔑したりすると思うのか? だったら悲しいぞー。2年以上、新聞部仲間として付き合ってる俺としちゃあさ。いつもは真面目な君に、少しくらいヘンな趣味があったって、そりゃ愛嬌ってモンじゃないか」
おっと編集長、うかつだな。ここは副編集長を庇わせてもらおう。
「おいおい、その認識じゃあ副編集長はもっと困っちゃうぞ。
ジキルとハイドみたいな、人間の二面性ってのは小説の話だけじゃない。凶悪犯の知り合いがインタビューで「普通の人でした。あんな事をするなんて信じられません」とか答えてるだろ? 人は上っ面で見えるだけの単純な存在じゃない、心の中にはいろいろと複雑な想いを秘めているのが当然なんだ。ちゃらんぽらんに見えるけど実は他人の顔色を気にしてそう振る舞っているだけだったり、異性に興味がないような顔をしているのは、人一倍強い性欲を抑えているだけだったりな。
それは責められることじゃない、悪いことじゃないんだ。誰だってそうなんだから、自分自身でもよくわからない複雑な深層自我をかろうじてコントロールしながら、上っ面だけでも取り繕って社会に適応しなきゃいけないのが文明社会の住民ってもんだ。 そう、創作表現は、そういう、抑圧された自我、もうひとりの自分を解放する唯一の手段であるともいえる。だから楽しいんだ、だから気持ちいいんだ。だからみんな、表現はしてみたい、でも恥ずかしいんだよ。
副編集長が、真面目でクールなその仮面の下に、どんな自分を隠していたとしても俺は驚かない、むしろ楽しみだ。仮面がクールであればあるだけ、真面目であればあるだけ、その下で内面は煮詰められて濃厚になる、秘められた欲望が磨かれて純化される。そうやって創作物は光り輝く、らしいぞ、Gさんに言わせると。
さあ副編集長、きみの内面を、秘められた欲望をさらけ出すんだ! 俺は決してそれを否定しない!」
「ひっ……」
こっちを振り向いた副編集長は、もう恥ずかしがってなんかいなかった。むしろ怒髪天という感じだ。目をつり上げて、俺を糾弾するように指をつきつけてくる。
「人聞きの悪いことを言わないでもらえるかな! なんなんだいさっきから、まだ読んでもいないのに勝手に決めつけて! 私の魂とかもうひとりの私とかヘンな趣味とか取り繕ってるとか秘められた欲望とか! 凶悪犯扱いまでしてくれて! 私、そこまで酷いことを言われるようなことを君にしたかい!? してたのなら言ってほしいものだね!」
「いや、仮にそうであっても俺は気にしないって言っただけで」
「そこは気にしろ! そんな想像をされるだけでも気分が悪いんだよ!
そんなおかしなものを私が書けるわけないでしょう! ただの青春もの、女子高校生のラブストーリー! 私が書いたのは!」
「うえっ!?」
おかしな声を上げたのは福地だ。
「副編集長が、ラブストーリーッスか?」
「そうだよ、文句でもあるのかい? 惚れたはれたのラブ、恋愛もの。キャラじゃないのはわかっている、笑えばいいさ、君のキャラでしょう、それが」
「いや、ここで笑うような空気の読めないキャラだと思われてるってののショックがでかすぎなんスけど。まー、副編集長のキャラじゃないってのはそうかもだけど、高校生主人公でラブストーリー、いいんじゃないスか? 等身大で」
女子高生の副編集長が、女子高生のラブストーリーを書いた。なるほど、等身大だが。等身大すぎて、フツーだな、と俺は思ってしまう。フツーじゃ面白くないってGさんも言ってたし、もっとひねれよ、と。だがもちろん口には出さない。さすが俺、空気が読める。
「わたしは、読んでみたいです、副編集長さんの書いたラブストーリー。そういうのが好きなんですか?」
「いや、別に」
しれっと否定する副編集長。照れ隠し、という感じではない。
「嫌いでもないけれど、好きってわけじゃないのだけどさ」
「じゃあなんで」
芽宮は不思議そうだ。
「ラブストーリーを書いたんですか?」
「……不意打ちだったから」
「不意打ち?」
「予想もしていないところから、いきなり殴ってくるような小説があったんだよ。それがとても衝撃的で。あんなにせつない気持ちになるのは初めてで、今でもあれ以上のものは見つからない。だから忘れられなかったんだ」
「私が読む小説は、翻訳もののミステリーとかサスペンスとか、そういうものが多いんだけれど。それも新刊ではないんだ、古本屋の文庫棚にそういうコーナーがあって、中学生の頃、安いから買って、読んでみたらはまってしまって、それからずっとそのコーナーがお気に入りなんだ。ジャンルは、モダンホラー、とか言うのかな? 巻末の解説に書いてあったけれど」
「あーなんか聞いたことあるなー」
編集長が、もどかしそうな感じに人差し指を回す。
「スティーヴン・キングとか? 確かに、新刊じゃ見ないよな、ああいうホラー小説って。たまにあっても日本の作家だし。昔、流行ったジャンルってことなのかねー? Gペディアではどうよ、そのへん?」
「その言い方じゃ、俺がGさんの受け売りしかしてないみたいじゃないか。キングとかクーンツとかなら俺だって読んだことあるぞ、モダンホラーな、親父の本だったから、3、40年前に日本でも流行ったんだろうな」
「いや、昔じゃん。モダンじゃないじゃん」
「当時としてはモダンって意味だろ。こう、モンスターとかオカルトとかで人がわーきゃー叫んだり死んだりするそれまでのホラーじゃなくて、社会の裏とか個人の心の中の闇の部分とかに焦点を当てて、じっとりねっとりぞくぞくさせる、それが新しい、それが今風、それこそがモダンホラー、そんな感じ、じゃないか?」
「映画の原作で、キングは知ってます。『キャリー』とか『ペット・セメタリー』とかは観たことがあります。最近だと『ミッドサマー』とか、ああいう感じですか?」
あれは映画だから絵的にハデにするために、わーきゃー叫んだり死んだりする成分が多めに足されていた気がするが。モダンホラーのじっとりねっとりしたニュアンスはやはり小説ならではのものだよな、とか思いつつ、俺はGペディアではなくWikipediaを検索。
「映画の『キャリー』は1976年で、『ペット・セメタリー』が1989年か。やっぱりそれくらいの時期に、日本でも流行ったんだろうな」
メッセージを送る!