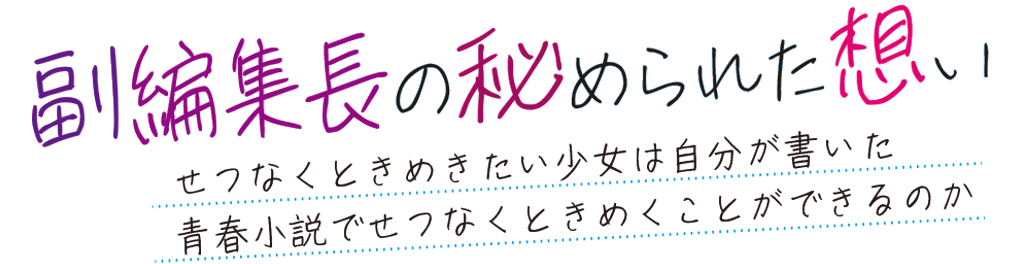第1章 告白のせつないときめきと副編集長からの挑戦状【後編】
ああ、思い出してきた。Gさんが言ってたな。スティーヴン・キングのメインどころは日本だと文春文庫が押さえていたけど、モダンホラーが売れると思った他社も追随して、扶桑社って出版社の文庫なんかは一時期、翻訳ものモダンホラー専門レーベルみたいになってたって。副編集長の言う古本屋のコーナーは、そういう文庫が置いてあるんだろう。
ちなみにGさんは表紙も背も黒ずくめにしたホラー専門文庫レーベルの立ち上げに関わって苦労したらしい。最後発になったから売れる原書は残っていなくて、結局、日本で書き手を発掘するしかなかったとか。でも結果としては、その中からベストセラーになって映画化までされたタイトルが出て来て、翻訳ものモダンホラーのブームを終わらせてジャパニーズホラーの時代を作る事ができたから苦労の甲斐があった、と言ってたな。
なぜそうなったか、モダンホラーとジャパニーズホラーの違い、なんて話もしていたし、それはそれで興味深い部分もあったが、またの機会にしよう。今は副編集長の話だ。
「キャラじゃないとは思わないけど、ラブストーリーよりは副編集長のイメージかもな、モダンホラーのほうが。こう、綺麗事だけじゃない、人の心のリアルな部分みたいなところがあってさ。いいよな、ああいうのも」
「そうだね、別に、ジャンルとして意識したことはないけれど、確かに、そういうところが好き、だったのかもしれない。
だからこそ、あれは不意打ちだったんだよ。ロバート・マキャモンの『ブルーワールド』、布留田君なら、知っているかい?」
「マキャモンね。キング、クーンツ、で、マキャモンだよな。モダンホラーっていったらこの三人だ。『ブルーワールド』は、えーと、短編集じゃなかったか? 読んだ、と思うよ。ちゃんと覚えてないけど」
「表題作の『ブルーワールド』が長くて、普通の長編くらいあるとても厚い短編集なんだ。他の短編は、いつものマキャモンらしさで、不条理で、ダークで、期待通り面白かった。最後の『ブルーワールド』だけが、全然違う小説だった。気取った小皿ばかりのコース料理の最後にいきなり、大ボリュームのハンバーガーが出てくる、あれ、でもこれすごく美味しいぞ、と思わされてしまう。とんでもない不意打ちでしょう?」
「あー、思い出してきた。そうか、あれ、ラブストーリーだったっけ?」
「恋とか愛とか一言も使ってない。地の文でも台詞でも。あったかもしれないけど少なくとも私の印象にはまったく残っていないな。いつものマキャモンらしい、甘さの欠片もない筆致だったけれど、そう、あれはラブストーリーだったよ。綺麗事の欠片もない、だれも、わかりやすい意味での幸せじゃないし、最後まで幸せにはならない。そういう意味でもいつものマキャモンで、ラブストーリー的要素なんてまったくないのに、私は、ふたりの男女が出会って、別れる、それだけのストーリーがせつなくて、せつなくて、ときめかされてしまった、ときめいてしまったんだよ。その不意打ちにやられたな、降参だ、とまで思ってしまった」
「あの、わたし、せつなそうだなとは思うんですが、どういう話なのかっぱりわからなくてムズムズするんですけど」
「オレも気になるッスね。あらすじ、あらすじを! いったいどういうストーリーなんスか!?」
こめかみに指を置いて話を整理するようすの副編集長。
「主人公は、カトリックの神父なんだ。禁欲の誓いを立てているのにある日、アダルトビデオのポスターを観てしまって、その、主演の彼女の裸が頭から離れなくなってしまう。こんなはずではない、わたしは誓いを立てた身、背教者じゃない、と苦悩しながら結局、神父という身分は隠しながらそのポルノ女優のお友達になってしまう話。ポルノ女優はポルノ女優で、彼のミステリアスなところにドキドキしてしまう軽い女で、彼に愛想を振りまいたりする。どころか、ポルノ女優をしているということを彼女も彼に隠してしまう。南部の片田舎からブロードウェースターを目指してきた、今はオフブロードウェーで修行中だけど、そろそろ大きな劇場からも声がかかっている、みたいに見栄を張るんだ。本当はどうなのか、彼は最初から知っているのに」
「どうしよう福地君、副編集長さんがどこにときめいたのかさっぱりわからなくなった」
「いやコレ、コメディでしょ!? 布留田先輩、マジ、コレなんスか? 副編集長の説明が下手ってワケじゃなくて?」
「間違っちゃいないんだよなー。実際そういう話だったし」
そう、俺はこの話をコメディとして楽しんだ記憶がある。ポスターを観た神父が、アダルトビデオを――そう、これはまだ1980年代のニューヨークの話、本番アリのエロエロ動画がネット配信でもDVDでもなくて、VHSのビデオテープとして売られているんだ――買おうとして止めて、止めたけどやっぱり買ってしまう場面、そして自分の部屋に帰って戸締まりを確認して、おそるおそるそのビデオを、真面目な宗教啓発ムービーを観るための私物のデッキで再生するまでのドタバタ劇、大笑いしたよなー。
いけないことをしている! こんなことをしちゃいけないんだ! でも、気になる! 観たい! 彼女の裸が観たいんだ! 裸で動いている彼女を観たいんだ! たとえ今、天地がひっくり返ろうと神罰が下ろうともうどうでも良い、どうとでもしろ、俺は! 今! これを観るんだ! という、他人からすればどうでもいい、本人にとっては切実な葛藤がじっとりねっとり描かれていて、俺は神父じゃないけれど、主人公の気持ちに完全にシンクロできた。こういうところはさすがのマキャモン、キングの再来と言われるだけのことはある。
そう、副編集長の言うことも間違ってない。ただのふざけたコメディじゃないんだ。ラブストーリーとして楽しむこともできる。
「うん、確かにね、コメディにもなっている。出てくるのは男も女もみんな、愚かで、自分のことしか考えていない、その場その場の感情でしか動かない。他のモダンホラーもたいていそういうキャラクターの話で、見方、書き方をちょっと変えるだけでコメディにも見える。でも、『ブルーワールド』には、他のモダンホラーにはない、綺麗さがあるんだよ。
みんな、正直なの。神父は、ポルノ女優に恋してるとも愛してるとも言わない、だって違うから。彼は、彼女の性的な部分に興味があるだけだから。最初から最後まで、彼はそのまま。まったくロマンチックではないし、女の目から見るとどうかと思うけれど、男ってそういうものでしょう? 彼は彼女に、神父であることは秘密にしているけれど、ウソはつかない、正直なの、考えていることは綺麗さの欠片もないのに、そういう意味で、まっすぐで、綺麗なの。
ポルノ女優もそう。彼女は、だれかに自分という存在を認めて欲しいだけ。だれにだってある、ごく普通の感情。彼女はそれに正直すぎて、それ以外はどうでもよくなるくらいには綺麗なの。
スターになりたかった、でもなれなかった、でも観てくれる人がいる、だからポルノにだって出る。でも足りない、そんな彼女の前に現れたのは、ストイックでミステリアスな――彼女にはそう見えた、ということだけれど、周りにはいなかったタイプの異性。彼女は、彼にこそ認めて欲しいと思った。そのためには見栄だって張る、すぐにバレるようなウソだってついてしまう。愚かすぎるくらいに必死で、自分の気持ちに正直なところがこの上ないくらい綺麗に描かれている」
「その小説を忘れられなくて、自分でも書いてみようと思った、ということですか? センパイにとっての『復讐のガンガール』みたいな?」
「ちょっと違うかな。直接のきっかけは、あなたなんだよ、宮城さん」
「わたし?」
「正確には、あなたと、布留田君だね。布留田君とあなたがしていた『女護ヶ島』と『戦国ワルキューレ』の内幕話を聞いたのがきっかけ。
私はね、創作には、私は持っていないような、何か特別なものが必要なんだと思っていた。ひらめき、発想とか、才能とか、情熱とか、そんな類の、ね。『ブルーワールド』には、作者のマキャモンの持っているそういう『特別』が詰め込まれている、だから面白いんだ、だからせつないんだ、だからときめくんだ、と思っていた。
でも、あなたたちふたりの話には、私には理解できないような『特別』な要素はひとつも出てこなかった。創作に必要なのは『表現』だ、自分の想いを、イメージを、不特定多数の相手に、文章で、声で、演技で伝えることなんだと言っていて、その理屈は、私にもとても納得できるものだった。
一応、確認しておきたいんだけれど、ふたりの話についての私の理解は間違ってないよね?」
俺は芽宮をうかがう。芽宮も俺を見ていた。
少なくとも俺には、そんな大それた、特別なものなんてひとつもない、と、思うぞ。芽宮はどうか。あのお尻は特別だと思うが、副編集長の言う特別はそういう意味じゃなんんだろうなあ。
「間違ってないと思うけど。俺達が話していたのは、その表現の難しさについて、だった、よな?」
「ですね。難しいけれど、それができる人は簡単にやっちゃう、という意味では特別かもしれませんけど」
「簡単なことだなんて、私だって思ってはいない。ふたりはしっかり結果も出している、小説もドラマも私は面白いと感じているからね。ふたりはプロとして素晴らしい表現をしているんだと思う。
でもね、私にも学校新聞副編集長としてのプライドがある。文字で、文章での表現について、同い年の人には負けない自信がある。正確で適切な表現をすれば、面白い小説が書けるのなら、私が小説を書けば、面白くならないはずがない。
そう思ったから、書いてみたんだよ」
将棋の駒を差すように、ぱちり、とSDカードを置く副編集長。
「ドラマとか映画なら、原稿用紙の束のシーンになるんでしょうけどね」
原稿用紙ってまだ売ってるのかね。少なくとも俺は、出版社で編集者が原稿用紙で仕事しているのは見たことがない。
「布留田君に読んでもらえばいいと思っていたから、これを渡すつもりだったんだけれど」
副編集長がそんなことを言うので、芽宮と福地は不満を表明する。
「ここまで聞かされて、蚊帳の外はないっスよねー?」
「わたしも読んでみたいんですけど、ダメですか?」
「部のサーバーに共有フォルダ作ってそこに上げればー? 読めるのは俺と布留田と福地にして、SDカードは宮城君に渡せばいい」
おお、さすが編集長。判断が早い、そして自分も読む気マンマンか。
「うん、でも」
しかし副編集長は、なにかをためらうようにSDカードを指で叩く。
「いや、恥ずかしいなら無理にとは言わないぞー?」
「恥ずかしい、のとはちょっと違うけど。どう言えばいいんだろうね?」
苦笑いしてる。
「これは、100%、ウソの話だから。こうだったら面白いのかな、という私の妄想、だけれど、私がこうなりたいわけじゃない、読むのなら、それを承知した上で読んでほしい、かな」
「そりゃ、そうだろ。俺だって、格好良く戦う女の子が面白いと思って書いてるが、自分が女の子になりたいわけじゃない」
「さっき、秘められた欲望がとかなんとか言ってなかったかい?
あのね、この小説の舞台は新聞部なの。主人公は副編集長で、編集長がいて、主人公と同学年がひとり、後輩が、男女ふたり」
んん? 副編集長以外の四人で顔を見合わせる。それって、この面子そのままじゃないか? 正確には、芽宮は新聞部員じゃなくて体操部員で、週一で俺と話をしに来ているだけだが。
「学校という集団の中での立ち位置とかそれぞれの性格を、ゼロから考えるのが面倒くさくて、そこだけはモデルにさせてもらったんだ。けれど、本当にそれだけ。似ているように見えるところもあるけれど、副編集長は私じゃないし、他のキャラクターも、あなたたちのことじゃない、それぞれが考えていることも、内面も、小説の中で描かれていることは、全部、現実とは違う、ウソだから。
ああ、わかってる。みんなは、フィクションと現実を混同なんてしない。それはわかってる、でも、ちょっとだけ心配になるの。私が、実は内面でこんなことを考えていたんだ、とか、私が、みんなのことをこう評価していたんだ、とか、思われたらどうしようとか思ってしまうんだ」
「そう言われっちゃうと、ちょっと怖くなるッスね、読むの。どう描かれてるんだろ、オレ?」
「バーカ。そんなふうに思われたくないって、副編集長はそう言ってるんだろ」
俺はSDカードを受け取って自分のモバイルノートでテキストファイルを読み込む。共有フォルダを作って、コピー、っと。エディタで開いてみる。タイトルは、『想い出に追いかけられて』、なるほど、少なくとも、タイトルのセンスは俺よりも良さそうだ。ざっとスクロールして流し読み。
「読ませようと思ったってことは、自信があるってことだよな。表現したいと思ったものは表現できたんだよな?」
「もちろんさ。言ったでしょう、私にもプライドがあるって。ちゃんと小説家をやっている布留田君にこんなことを言うのは思い上がりに聞こえるかもしれないけど。これは、私のあなたに対する挑戦状だよ。面白かった、と言わせてみせる」
ああ、副編集長はこういう表情もできるんだな。ちょっと意外、今まで気がつかなかったとは俺もまだまだだ。なかなか格好良いじゃないか。不敵な笑みが似合っている。
「OKOK、楽しませてもらうよ、副編集長の書きたかったせつなさを、さ」
とは言いつつ。
流し読みしたテキストに俺は、ひっかかるものを感じていた。
これでせつなさを感じるのは難しいかもしれない。
いやもちろん、副編集長の文章が、表現がおかしいわけじゃない。この小説を読むまでもなく、普段書いている記事を読んでいるから、俺は副編集長の表現力を認めている。簡潔に、的確に意図を伝える、無駄のない記事を書いていた。じゃなきゃアンカーマンを任されたりはしない。
でもこの小説の表現は、せつなさには向いていない、そう思った。決定的だったのは、括弧書き、キャラクターの内心の独白を表現するための()で囲った台詞があった事だ。それ自体が悪いわけじゃない、表現として特別なものじゃないし、ドラマチックなインパクトのありそうな台詞になっている。
面白そうなのは間違いない。でもなー、副編集長が書きたかったのはこれなのか? という疑問が湧いてきてしまうんだ。
俺はSDカードを芽宮に渡す。
「ありがとうございます! すぐに読ませていただきますね! あ、わたし、次にここに来れるのはやっぱり1週間後になるから、でも」
「それでいいんじゃね? 各自、じっくり読み込んで、1週間後、この時間に批評、ってほど大した事は言えそうにないな、感想会ってことで」
編集長が仕切ってくれた。
うん、まあ、とりあえず、読んでみないことには始まらないな。
ちなみにGさんは表紙も背も黒ずくめにしたホラー専門文庫レーベルの立ち上げに関わって苦労したらしい。最後発になったから売れる原書は残っていなくて、結局、日本で書き手を発掘するしかなかったとか。でも結果としては、その中からベストセラーになって映画化までされたタイトルが出て来て、翻訳ものモダンホラーのブームを終わらせてジャパニーズホラーの時代を作る事ができたから苦労の甲斐があった、と言ってたな。
なぜそうなったか、モダンホラーとジャパニーズホラーの違い、なんて話もしていたし、それはそれで興味深い部分もあったが、またの機会にしよう。今は副編集長の話だ。
「キャラじゃないとは思わないけど、ラブストーリーよりは副編集長のイメージかもな、モダンホラーのほうが。こう、綺麗事だけじゃない、人の心のリアルな部分みたいなところがあってさ。いいよな、ああいうのも」
「そうだね、別に、ジャンルとして意識したことはないけれど、確かに、そういうところが好き、だったのかもしれない。
だからこそ、あれは不意打ちだったんだよ。ロバート・マキャモンの『ブルーワールド』、布留田君なら、知っているかい?」
「マキャモンね。キング、クーンツ、で、マキャモンだよな。モダンホラーっていったらこの三人だ。『ブルーワールド』は、えーと、短編集じゃなかったか? 読んだ、と思うよ。ちゃんと覚えてないけど」
「表題作の『ブルーワールド』が長くて、普通の長編くらいあるとても厚い短編集なんだ。他の短編は、いつものマキャモンらしさで、不条理で、ダークで、期待通り面白かった。最後の『ブルーワールド』だけが、全然違う小説だった。気取った小皿ばかりのコース料理の最後にいきなり、大ボリュームのハンバーガーが出てくる、あれ、でもこれすごく美味しいぞ、と思わされてしまう。とんでもない不意打ちでしょう?」
「あー、思い出してきた。そうか、あれ、ラブストーリーだったっけ?」
「恋とか愛とか一言も使ってない。地の文でも台詞でも。あったかもしれないけど少なくとも私の印象にはまったく残っていないな。いつものマキャモンらしい、甘さの欠片もない筆致だったけれど、そう、あれはラブストーリーだったよ。綺麗事の欠片もない、だれも、わかりやすい意味での幸せじゃないし、最後まで幸せにはならない。そういう意味でもいつものマキャモンで、ラブストーリー的要素なんてまったくないのに、私は、ふたりの男女が出会って、別れる、それだけのストーリーがせつなくて、せつなくて、ときめかされてしまった、ときめいてしまったんだよ。その不意打ちにやられたな、降参だ、とまで思ってしまった」
「あの、わたし、せつなそうだなとは思うんですが、どういう話なのかっぱりわからなくてムズムズするんですけど」
「オレも気になるッスね。あらすじ、あらすじを! いったいどういうストーリーなんスか!?」
こめかみに指を置いて話を整理するようすの副編集長。
「主人公は、カトリックの神父なんだ。禁欲の誓いを立てているのにある日、アダルトビデオのポスターを観てしまって、その、主演の彼女の裸が頭から離れなくなってしまう。こんなはずではない、わたしは誓いを立てた身、背教者じゃない、と苦悩しながら結局、神父という身分は隠しながらそのポルノ女優のお友達になってしまう話。ポルノ女優はポルノ女優で、彼のミステリアスなところにドキドキしてしまう軽い女で、彼に愛想を振りまいたりする。どころか、ポルノ女優をしているということを彼女も彼に隠してしまう。南部の片田舎からブロードウェースターを目指してきた、今はオフブロードウェーで修行中だけど、そろそろ大きな劇場からも声がかかっている、みたいに見栄を張るんだ。本当はどうなのか、彼は最初から知っているのに」
「どうしよう福地君、副編集長さんがどこにときめいたのかさっぱりわからなくなった」
「いやコレ、コメディでしょ!? 布留田先輩、マジ、コレなんスか? 副編集長の説明が下手ってワケじゃなくて?」
「間違っちゃいないんだよなー。実際そういう話だったし」
そう、俺はこの話をコメディとして楽しんだ記憶がある。ポスターを観た神父が、アダルトビデオを――そう、これはまだ1980年代のニューヨークの話、本番アリのエロエロ動画がネット配信でもDVDでもなくて、VHSのビデオテープとして売られているんだ――買おうとして止めて、止めたけどやっぱり買ってしまう場面、そして自分の部屋に帰って戸締まりを確認して、おそるおそるそのビデオを、真面目な宗教啓発ムービーを観るための私物のデッキで再生するまでのドタバタ劇、大笑いしたよなー。
いけないことをしている! こんなことをしちゃいけないんだ! でも、気になる! 観たい! 彼女の裸が観たいんだ! 裸で動いている彼女を観たいんだ! たとえ今、天地がひっくり返ろうと神罰が下ろうともうどうでも良い、どうとでもしろ、俺は! 今! これを観るんだ! という、他人からすればどうでもいい、本人にとっては切実な葛藤がじっとりねっとり描かれていて、俺は神父じゃないけれど、主人公の気持ちに完全にシンクロできた。こういうところはさすがのマキャモン、キングの再来と言われるだけのことはある。
そう、副編集長の言うことも間違ってない。ただのふざけたコメディじゃないんだ。ラブストーリーとして楽しむこともできる。
「うん、確かにね、コメディにもなっている。出てくるのは男も女もみんな、愚かで、自分のことしか考えていない、その場その場の感情でしか動かない。他のモダンホラーもたいていそういうキャラクターの話で、見方、書き方をちょっと変えるだけでコメディにも見える。でも、『ブルーワールド』には、他のモダンホラーにはない、綺麗さがあるんだよ。
みんな、正直なの。神父は、ポルノ女優に恋してるとも愛してるとも言わない、だって違うから。彼は、彼女の性的な部分に興味があるだけだから。最初から最後まで、彼はそのまま。まったくロマンチックではないし、女の目から見るとどうかと思うけれど、男ってそういうものでしょう? 彼は彼女に、神父であることは秘密にしているけれど、ウソはつかない、正直なの、考えていることは綺麗さの欠片もないのに、そういう意味で、まっすぐで、綺麗なの。
ポルノ女優もそう。彼女は、だれかに自分という存在を認めて欲しいだけ。だれにだってある、ごく普通の感情。彼女はそれに正直すぎて、それ以外はどうでもよくなるくらいには綺麗なの。
スターになりたかった、でもなれなかった、でも観てくれる人がいる、だからポルノにだって出る。でも足りない、そんな彼女の前に現れたのは、ストイックでミステリアスな――彼女にはそう見えた、ということだけれど、周りにはいなかったタイプの異性。彼女は、彼にこそ認めて欲しいと思った。そのためには見栄だって張る、すぐにバレるようなウソだってついてしまう。愚かすぎるくらいに必死で、自分の気持ちに正直なところがこの上ないくらい綺麗に描かれている」
「その小説を忘れられなくて、自分でも書いてみようと思った、ということですか? センパイにとっての『復讐のガンガール』みたいな?」
「ちょっと違うかな。直接のきっかけは、あなたなんだよ、宮城さん」
「わたし?」
「正確には、あなたと、布留田君だね。布留田君とあなたがしていた『女護ヶ島』と『戦国ワルキューレ』の内幕話を聞いたのがきっかけ。
私はね、創作には、私は持っていないような、何か特別なものが必要なんだと思っていた。ひらめき、発想とか、才能とか、情熱とか、そんな類の、ね。『ブルーワールド』には、作者のマキャモンの持っているそういう『特別』が詰め込まれている、だから面白いんだ、だからせつないんだ、だからときめくんだ、と思っていた。
でも、あなたたちふたりの話には、私には理解できないような『特別』な要素はひとつも出てこなかった。創作に必要なのは『表現』だ、自分の想いを、イメージを、不特定多数の相手に、文章で、声で、演技で伝えることなんだと言っていて、その理屈は、私にもとても納得できるものだった。
一応、確認しておきたいんだけれど、ふたりの話についての私の理解は間違ってないよね?」
俺は芽宮をうかがう。芽宮も俺を見ていた。
少なくとも俺には、そんな大それた、特別なものなんてひとつもない、と、思うぞ。芽宮はどうか。あのお尻は特別だと思うが、副編集長の言う特別はそういう意味じゃなんんだろうなあ。
「間違ってないと思うけど。俺達が話していたのは、その表現の難しさについて、だった、よな?」
「ですね。難しいけれど、それができる人は簡単にやっちゃう、という意味では特別かもしれませんけど」
「簡単なことだなんて、私だって思ってはいない。ふたりはしっかり結果も出している、小説もドラマも私は面白いと感じているからね。ふたりはプロとして素晴らしい表現をしているんだと思う。
でもね、私にも学校新聞副編集長としてのプライドがある。文字で、文章での表現について、同い年の人には負けない自信がある。正確で適切な表現をすれば、面白い小説が書けるのなら、私が小説を書けば、面白くならないはずがない。
そう思ったから、書いてみたんだよ」
将棋の駒を差すように、ぱちり、とSDカードを置く副編集長。
「ドラマとか映画なら、原稿用紙の束のシーンになるんでしょうけどね」
原稿用紙ってまだ売ってるのかね。少なくとも俺は、出版社で編集者が原稿用紙で仕事しているのは見たことがない。
「布留田君に読んでもらえばいいと思っていたから、これを渡すつもりだったんだけれど」
副編集長がそんなことを言うので、芽宮と福地は不満を表明する。
「ここまで聞かされて、蚊帳の外はないっスよねー?」
「わたしも読んでみたいんですけど、ダメですか?」
「部のサーバーに共有フォルダ作ってそこに上げればー? 読めるのは俺と布留田と福地にして、SDカードは宮城君に渡せばいい」
おお、さすが編集長。判断が早い、そして自分も読む気マンマンか。
「うん、でも」
しかし副編集長は、なにかをためらうようにSDカードを指で叩く。
「いや、恥ずかしいなら無理にとは言わないぞー?」
「恥ずかしい、のとはちょっと違うけど。どう言えばいいんだろうね?」
苦笑いしてる。
「これは、100%、ウソの話だから。こうだったら面白いのかな、という私の妄想、だけれど、私がこうなりたいわけじゃない、読むのなら、それを承知した上で読んでほしい、かな」
「そりゃ、そうだろ。俺だって、格好良く戦う女の子が面白いと思って書いてるが、自分が女の子になりたいわけじゃない」
「さっき、秘められた欲望がとかなんとか言ってなかったかい?
あのね、この小説の舞台は新聞部なの。主人公は副編集長で、編集長がいて、主人公と同学年がひとり、後輩が、男女ふたり」
んん? 副編集長以外の四人で顔を見合わせる。それって、この面子そのままじゃないか? 正確には、芽宮は新聞部員じゃなくて体操部員で、週一で俺と話をしに来ているだけだが。
「学校という集団の中での立ち位置とかそれぞれの性格を、ゼロから考えるのが面倒くさくて、そこだけはモデルにさせてもらったんだ。けれど、本当にそれだけ。似ているように見えるところもあるけれど、副編集長は私じゃないし、他のキャラクターも、あなたたちのことじゃない、それぞれが考えていることも、内面も、小説の中で描かれていることは、全部、現実とは違う、ウソだから。
ああ、わかってる。みんなは、フィクションと現実を混同なんてしない。それはわかってる、でも、ちょっとだけ心配になるの。私が、実は内面でこんなことを考えていたんだ、とか、私が、みんなのことをこう評価していたんだ、とか、思われたらどうしようとか思ってしまうんだ」
「そう言われっちゃうと、ちょっと怖くなるッスね、読むの。どう描かれてるんだろ、オレ?」
「バーカ。そんなふうに思われたくないって、副編集長はそう言ってるんだろ」
俺はSDカードを受け取って自分のモバイルノートでテキストファイルを読み込む。共有フォルダを作って、コピー、っと。エディタで開いてみる。タイトルは、『想い出に追いかけられて』、なるほど、少なくとも、タイトルのセンスは俺よりも良さそうだ。ざっとスクロールして流し読み。
「読ませようと思ったってことは、自信があるってことだよな。表現したいと思ったものは表現できたんだよな?」
「もちろんさ。言ったでしょう、私にもプライドがあるって。ちゃんと小説家をやっている布留田君にこんなことを言うのは思い上がりに聞こえるかもしれないけど。これは、私のあなたに対する挑戦状だよ。面白かった、と言わせてみせる」
ああ、副編集長はこういう表情もできるんだな。ちょっと意外、今まで気がつかなかったとは俺もまだまだだ。なかなか格好良いじゃないか。不敵な笑みが似合っている。
「OKOK、楽しませてもらうよ、副編集長の書きたかったせつなさを、さ」
とは言いつつ。
流し読みしたテキストに俺は、ひっかかるものを感じていた。
これでせつなさを感じるのは難しいかもしれない。
いやもちろん、副編集長の文章が、表現がおかしいわけじゃない。この小説を読むまでもなく、普段書いている記事を読んでいるから、俺は副編集長の表現力を認めている。簡潔に、的確に意図を伝える、無駄のない記事を書いていた。じゃなきゃアンカーマンを任されたりはしない。
でもこの小説の表現は、せつなさには向いていない、そう思った。決定的だったのは、括弧書き、キャラクターの内心の独白を表現するための()で囲った台詞があった事だ。それ自体が悪いわけじゃない、表現として特別なものじゃないし、ドラマチックなインパクトのありそうな台詞になっている。
面白そうなのは間違いない。でもなー、副編集長が書きたかったのはこれなのか? という疑問が湧いてきてしまうんだ。
俺はSDカードを芽宮に渡す。
「ありがとうございます! すぐに読ませていただきますね! あ、わたし、次にここに来れるのはやっぱり1週間後になるから、でも」
「それでいいんじゃね? 各自、じっくり読み込んで、1週間後、この時間に批評、ってほど大した事は言えそうにないな、感想会ってことで」
編集長が仕切ってくれた。
うん、まあ、とりあえず、読んでみないことには始まらないな。
『で、読んでみたんだな。どうだった?』
夜、俺はGさんと電話していた。
「面白かったよ。でもやっぱり、せつない、ってよりは、なんだろ、甘酸っぱい? とか、そういう感じかな。ラブコメって呼ばれるコミックみたいな」
『その副編集長とは会ったこともないからたぶんだが、努力家で真面目、なんだろうな。ラブストーリーを書こうとして、『ブルーワールド』だけじゃなく、いろいろ読んで表現や構成を研究したんだろう。今、人気があるのはそういうタッチのストーリーだからな。別に悪いことじゃない』
「もちろん、その通り、俺だってそう思ってるさ。でも」
『永斗。副編集長がお前に求めているのはどういう立場からの意見か、わかるか?』
「たぶん、だけど。同じ部の同輩としての意見、だろうね。プロとしての意見が欲しいなら、俺ならそう言うし。たとえば、面白いと思ったら、だれか出版社の編集者を紹介してくれないか、とか」
『おそらく、それは正しい。だからそれでいい』
「でもさー」
『余計なお節介だと思われるぞ』
「わかってる、それもわかってるんだけどさ。でも、せつなさを表現したい、って副編集長の気持ちも、本物だと思うんだ。だから、もしも、もしもだよ? それで副編集長が困ってるんならさ、アドバイスくらいはしてもいいんじゃないかな、と思うわけだよ」
『困っていたら、な。本人は、書いて、仕上げて、それで満足なのかもしれない、と言うか、普通はそうだ。初めて仕上げた一冊ってのは、大切なものなんだよ、書いた本人にとっては。求められる前にアドバイスなんてするもんじゃないぞ。それこそ大きなお世話ってもんだ』
「だから、わかってるって。信用ないなー。俺は、副編集長のことはいい友達だと思ってるんだぜ? 傷つけるようなことをするわけないじゃないか。
とは言いつつ、なんだけど。ラブストーリーとかラブコメとか、恋愛絡みの小説は、俺も実は得意ってわけじゃないし、そんなに詳しく調べたわけじゃないからさ。せいぜいGさんの編集者としての経験談を聞いた事があるくらいで」
『それだけで括弧書きの独白の違和感に気づけるのは大したもんだと思うがな』
「そりゃあ、気づくよ。あの、『書いてない台詞を読んだ気になっちゃった部下』の話は特に笑えたから印象に残ってる。でもまあ、念のために、というか、アドバイスが必要になったときのためというか、一度おさらいしときたいんだ。Gさんの恋愛小説歴史講座をさ」
『おいおい、どこから話させるつもりだ? 源氏物語からか?』
「そうだな、1980年代、コミックから始まったムーブメントがあったって言ってたよね? 高橋留美子さんとかあだち充さんとか。なんとなくは理解したつもりだけど、俺が産まれる20年以上前の話だろ、時代背景とか、ピンと来ないところもあってさ。そのあたり。もう一度聞かせてくれる?」
『そんなに昔の話のつもりはないんだがな。お前にとってそうなるのは、そうか、仕方ないか。嫌だな、こういう感覚は』
電話の向こうで、ジッポライターのホイールがフリントをこする音。一服する間に、Gさんは考えを整理したようだ。
『では、語ろうか。少年サンデーがきっかけを作って、『ときめきメモリアル』というゲームで完成する罠、恋愛小説を書こうとする者全てにかかった呪縛について』
Gさんの、こういうサービス精神旺盛なところが、俺は尊敬するよ、本当に。
夜、俺はGさんと電話していた。
「面白かったよ。でもやっぱり、せつない、ってよりは、なんだろ、甘酸っぱい? とか、そういう感じかな。ラブコメって呼ばれるコミックみたいな」
『その副編集長とは会ったこともないからたぶんだが、努力家で真面目、なんだろうな。ラブストーリーを書こうとして、『ブルーワールド』だけじゃなく、いろいろ読んで表現や構成を研究したんだろう。今、人気があるのはそういうタッチのストーリーだからな。別に悪いことじゃない』
「もちろん、その通り、俺だってそう思ってるさ。でも」
『永斗。副編集長がお前に求めているのはどういう立場からの意見か、わかるか?』
「たぶん、だけど。同じ部の同輩としての意見、だろうね。プロとしての意見が欲しいなら、俺ならそう言うし。たとえば、面白いと思ったら、だれか出版社の編集者を紹介してくれないか、とか」
『おそらく、それは正しい。だからそれでいい』
「でもさー」
『余計なお節介だと思われるぞ』
「わかってる、それもわかってるんだけどさ。でも、せつなさを表現したい、って副編集長の気持ちも、本物だと思うんだ。だから、もしも、もしもだよ? それで副編集長が困ってるんならさ、アドバイスくらいはしてもいいんじゃないかな、と思うわけだよ」
『困っていたら、な。本人は、書いて、仕上げて、それで満足なのかもしれない、と言うか、普通はそうだ。初めて仕上げた一冊ってのは、大切なものなんだよ、書いた本人にとっては。求められる前にアドバイスなんてするもんじゃないぞ。それこそ大きなお世話ってもんだ』
「だから、わかってるって。信用ないなー。俺は、副編集長のことはいい友達だと思ってるんだぜ? 傷つけるようなことをするわけないじゃないか。
とは言いつつ、なんだけど。ラブストーリーとかラブコメとか、恋愛絡みの小説は、俺も実は得意ってわけじゃないし、そんなに詳しく調べたわけじゃないからさ。せいぜいGさんの編集者としての経験談を聞いた事があるくらいで」
『それだけで括弧書きの独白の違和感に気づけるのは大したもんだと思うがな』
「そりゃあ、気づくよ。あの、『書いてない台詞を読んだ気になっちゃった部下』の話は特に笑えたから印象に残ってる。でもまあ、念のために、というか、アドバイスが必要になったときのためというか、一度おさらいしときたいんだ。Gさんの恋愛小説歴史講座をさ」
『おいおい、どこから話させるつもりだ? 源氏物語からか?』
「そうだな、1980年代、コミックから始まったムーブメントがあったって言ってたよね? 高橋留美子さんとかあだち充さんとか。なんとなくは理解したつもりだけど、俺が産まれる20年以上前の話だろ、時代背景とか、ピンと来ないところもあってさ。そのあたり。もう一度聞かせてくれる?」
『そんなに昔の話のつもりはないんだがな。お前にとってそうなるのは、そうか、仕方ないか。嫌だな、こういう感覚は』
電話の向こうで、ジッポライターのホイールがフリントをこする音。一服する間に、Gさんは考えを整理したようだ。
『では、語ろうか。少年サンデーがきっかけを作って、『ときめきメモリアル』というゲームで完成する罠、恋愛小説を書こうとする者全てにかかった呪縛について』
Gさんの、こういうサービス精神旺盛なところが、俺は尊敬するよ、本当に。
メッセージを送る!