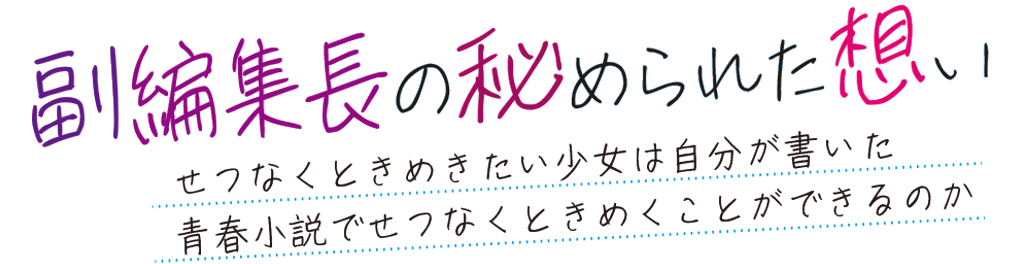第2章 硬派な出版社の中心で愛を叫んじゃった2代目が社長になって、高校球児が少女と少年の垣根を越えてニュータイプになる【前編】
一週間後。水曜日。新聞部室に再び集まった五人。
なんか空気が妙だぞ? お互いに様子をうかがい合ってる感じ。
芽宮以外の四人は、放課後にはここで毎日顔を合わせているんだが、この一週間、特に福地の様子が可笑しかった。何かを言おうとして、呑み込む、でも黙ってもいられない、そんな感じ。副編集長の小説を読んで、感想を語りたい、あるいは言いたいことがある、でも、全員が集まってからって決まっているから、先走りして語るのもはばかられる、そう思っているのがまるわかり。
空気が妙なのは、編集長も副編集長もそんな福地を見ているから、口火をきりにくい感じ。見ていない芽宮も、彼女は場を読めるから、澄ました顔で様子をうかがっている。
しょうがないなー。俺から行かせてもらいますか。
「面白かったよ。正直、予想以上だった。副編集長のこと、ちょっとナメてたな。こんな小説が書けるとは思ってなかった、ゴメンな。でも、すごいよ。楽しめた」
副編集長は、ちょっと驚いたようだ。目が少し大きくなる。
「本当に? お世辞ではないんだよね?」
「俺は小説に関しては嘘はつかないぞ。あ、書く小説の中じゃあ嘘つきまくりだけど。
この小説も、嘘のつきかたが上手い。悪い意味じゃないぞ、小説表現が上手いってことだ」
「あ、ありがとう?」
「まず冒頭。主人公の独白で始まるってのはよく使われる手法ではあるけれど、よく使われるのはそれだけ効果的だからだ。
高校3年の女の子の登校風景、今朝は夢見が悪くてちょっと寝不足、彼女は夢の内容を思い出して、憂鬱になっている。夢の中で彼女はまだ中学生、軽い気持ちで書いた小説を、試しに投稿サイト載せてみたら、これがものすごい評判になって商業出版されて映画にもなる。そんな夢だ。
彼女を憂鬱にさせているのは、この夢が本当にあったことだからだ。書いた小説も、部分的には本当の話だった。二つ違いの、幼いときに交通事故で死んでしまった兄との想い出、中学生になった彼女は、文章を綴るのが好きだったから、兄が生きていたという事を、優しくていい兄だったという事を小説という形で残そうとしたんだ。そして、それは意外な程たくさんの人に読んでもらえた。
ここまでなら別に憂鬱にはならない。いい話だよな? でも、いい話では終わらなかった。たくさんの人が読んで、いろいろに評価されて、ドラマや映画になるうちに、彼女だけのものだった想い出は彼女の手から離れてしまう。想い出の中にはいいことも悪いこともあったのに、いいことだけを取り上げて持ち上げる、感動した、泣いた、と絶賛する人がいる。一方で、お涙ちょうだいの、ありがちな、手垢の付いたストーリーの駄作だ、と酷評する人がいる。
読んだ人の中で、想い出が変わっていく。そうすると、彼女自身も思い出を信じられなくなってしまう。想い出は、本当にあったことだと信じるままに書いて小説にしたけれど、所詮は中学生の夢想、ただの綺麗事になってしまっているんじゃないか? そんなものを残されても、兄だって困るだけなんじゃないか? 自分の想い出の価値がどんどん信じられなくなっていく、そもそも小説なんて、嘘ばっかりじゃないか。
そんな風に、彼女は憂鬱なんだ。
いい。引き込まれる。幼少期、中学生、そして現在、それぞれの主人公が幸せだったり憂鬱だったり、明暗、起伏たっぷりに表現されているのがいいな。単純じゃない魅力がある。いい案配の不安定感も演出できて、これから彼女がどうなるのか、という期待感もあおってくれる。見本にしたいような冒頭だよ」
「ありがとう」
ちょっと赤くなった副編集長は視線を泳がせている。
「そこはもちろん、そう計算して書いたからね。それくらいは、私にだって書けるんだよ」
うーん初々しいなあ。そう、伝えたかったことが伝わるってのは、嬉しいよな。わかるわー。
「小説に夢を持てなくなったけど、文章は綴りたいから新聞部、って動機付けになってるのも面白いよなー。強引に見えて自然な感じになっちゃうのが不思議。これがキャラクター性ってのかな? うん、俺も楽しく読めたよ。俺らなんかモデルにして小説になるのかと思ったけど、ちゃんとなってるのがなにより驚きだよな」
「後輩キャラがちょっとチャラ過ぎて最初は抵抗あったんスけど。あ、いや、わかってますって、現実とフィクションをごっちゃになんてしないっスから! でもこう、思いっきりデフォルメされた似顔絵みたいな感じで読んだら、意外と楽しめちゃったんスよね。そういうのもダメッスか?」
それくらいならいいんじゃないかなー。お前はまだいいじゃないか。俺がモデルになったキャラなんて、キャラの一部、作家要素を副編集長に盗られた上に、主人公にとって「生理的に合わない異性」扱いだぞ。不本意にもほどがある。
でもこれはフィクションだから! 現実じゃないから! そんなことはわかってる、俺はプロだぞ!? だから文句は言わない。さすが俺。
とか思っていたら。
「それでいいんですか? みなさん」
芽宮だ。なんか、怒ってる? 声が固い感じ。
「もちろん、同じ部の仲間である副編集長さんのことを気遣ってそう言っているのはわかります。でも、わたしは新聞部じゃない部外者で、なにより、演技という表現の、まだ修行中ですけど、一応プロなんです。表現についての意見を求められたら、嘘はつきにくいんです。
編集長さんかセンパイか福地君のだれかが言ってくれるなら、それでも良かったんですけれど。みなさんが言いにくいなら、それはわたしの役目だと、わたしが決めました」
あちゃあ。これは予想しなかった。俺が言わなかったことについて、切り込むつもりだ、芽宮が。
驚くと同時に、俺は納得もしていた。そうだよな、芽宮は毎日のように、カントクに演技をしごかれてるんだもんな。しごかれて、上手くなっているという自覚もあるんだろう。自分に厳しいから、他人にも厳しい。相手が本気であればあるほどそうなる。芽宮は、副編集長が本気だと判断したんだろう。本気には本気で応えなくてはならない、そう決めたんだ。そこが俺との違いだ。
「え、ゴメン、どういうことか、わかんないンだけど、宮城ちゃん?」
「ちょっと力みすぎじゃないかなー? 言いたいことはわかるけど、ちょっと落ち着こうぜ?」
福地はわかってない。編集長はさすがに理解してるようだ。
「落ち着いてます、ううん、落ち着いてないかも? 副編集長さんを傷つけてしまうかもしれないから、言いたくないけど、でも、言わなきゃいけないんです。
副編集長さん、わたし、『ブルーワールド』も読んでみたんです。電子化もされてないから読めないかな、と思ったんですけど、古本屋にあったので。副編集長さんの言った通り、せつなくて、せつなくて、わたしも泣いちゃいました。
『想い出に追いかけられて』、副編集長さんの書いた小説も、面白かったです。
でもですね、せつなさは感じませんでした。これが不思議なんです。面白いのに、せつなくない。
泣けないんですよ、せつなくないから。まったく。涙一滴すら出ませんでした。
副編集長さんは言いましたよね? 『ブルーワールド』のせつなさに不意打ちされて、自分でも表現してみたくなった、って。表現したかったのはせつなさじゃないんですか? せつなさは表現できましたか? わたしに読み取る力がない、というのならそれでいいんですけど。
副編集長さん、自分で書いたこれを読んで、あなたはせつなくなるんですか?」
うわ、キッツいなー。横で聞いているだけなのに胸にちくちくと来る。見ろよ福地の顔が引きつってるぞ。同性同士ってのもあるかもしれないが、芽宮自身がカントクに、こんな感じでしごかれてるってのがデカいんだろうな。言葉が丁寧になってはいるが、それが余計に印象を厳しいものにしている気がする。芽宮にそういう意図はないだろうが。
「そう言われる可能性は、考えていたんだ。これは本当だよ?」
副編集長の声も固い。
「言うなら布留田君かな、と思っていたんだけれど。それは外れたかな」
「そうですね、わたしもセンパイがずけずけ言ってくれるのを期待してたんですけど。ちょっとがっかりです」
おーい、キミタチ? 勝手な予想や期待はしないでほしいかなー、なんて思うんだが。ずけずけとかがっかりとか、そもそも俺をどういう性格だと思ってるんだ。
「うん、せつなさを表現したつもりだったのに、読み返してみてもせつなくない。でもそれは、手品師がトリックを知っているみたいなもので、知らないだれかに読んでもらえばひょっとして、とも思ったんだけど」
副編集長に視線で促されて、福地はぶんぶんと首と手を振る。
「いや、オレはそもそも、そういうの小説に求めてないし、わかんないッスよ! せつなさとかって、女性向けっしょ!?」
編集長は肩をすくめた。
「読んで、楽しめた。それで満足してちゃおかしいか? それでいいと思うんだけどなー?」
「ありがとう。でもね、私が表現したかったのは、せつなさなの」
雰囲気が、場の空気が。重いっ!
副編集長が困っているなら、アドバイスをしようと思っていた。その内容だってちゃんと考えてある。別に難しい話じゃないんだ。副編集長の今の状況は、ボタンをひとつ掛け違えた間違えたみたいなモンで、どこを間違えたか指摘するだけのアドバイスだ。そんなんすぐに直せるじゃないか。
だがしかし。困り方が想定以上に深刻だ。落ち込んでいる。今の副編集長の顔を見て、
「そんなキミに、目からウロコのワンポイントレッスン! これでキミの悩みもスッキリ解決!」
とは言えない。どうすりゃいいんだこの空気?
「思い上がってたのかな、自分だって表現できるなんて。これでもけっこう本気で書いたのにね。なにが足りないのかもわからない、私には」
いや、そうじゃなくて、と思っていたら。
「大丈夫です! わたしだってわからないけど、センパイがいます! プロの作家の! ね、センパイ」
芽宮がハードル上げるし。いや上げきっていたのをさらに積んでくるし。
「なにが足りないのか、センパイはわかりますよね?」
でもまあ。勢いは作ってくれたから、その流れに乗せてもらおう。後輩の期待には応えなくちゃだしな。
「逆だよ。足りないんじゃない、足り過ぎなんだ。書き過ぎなんだよ。せつなさを表現しようとしても難しい。だったら、表現しなければいいんだ。それがせつなさになる」
場の空気変えるために、あえて謎かけみたいな言い方をしてみた。副編集長も含めて、思い詰めたような顔をしていたみんなが驚いたような、呆れたように顔をしているから、まあ、狙い通り。
「だから、思い詰めなくていいんだ。ちょっと勘違いしてるだけなんだから。副編集長にだって表現できるさ、せつなさを」
芽宮は嬉しそうにうんうん、と頷いている。さすがセンパイ、と言いたいんだろうが、なんか顔が自慢げで、愛弟子の活躍を見守る師匠、みたいな感じにも見えるから、自重しよう? 別にたいしたことは言ってないから、持ち上げてくれるなよ、くすぐったくて逃げ出したくなる。
「表現しなくていいって言ってみたりできるって言ってみたり、どっちなんスかね?」
「まー、ケースバイケースなんだよ、いろいろとさ。だから論点をはっきりさせよう。
副編集長はせつなさを書きたかった。でも書けなかった。なにがいけなかったのか? そういう事だよな。
さて、じゃあそもそも、せつなさって何だ? さっき福地は、せつなさは女性向けだ、みたいに言ってたよな? どういうところが女性向けだ? どういうのがせつなさだと思ってそう言った?」
「だからわかんないンだって……そうッスねえ、何となくですけど、少女まんがにあるような、この想いをあの人に伝えたいのに伝わらない、せつない、みたいな?」
「編集長は? どう思う?」
「そうだなー」
腕組みして天井を仰ぐ編集長。
「福地の言う、女性向けってのも間違ってはないと思うぞー。俺みたいな男が、せつない、って言っても笑われる気がするし。あーそうか、中高生の女の子が似合う感じだよな。こう、心も身体も、そして周囲の環境も急にいろいろ変わっていく中で、自己認識がぐらぐら揺れる感じ、変わっていく、見えない、予測できない不安感、みたいな?」
「OKOK。
つまり、せつなさは、不安感なんだ。思春期独特の、他人や社会との関係性、見通せない将来、確立していない自己肯定感、あらゆるものに感じている不安感全て、それがせつなさになる。
例えばだ、副編集長が、今まさに感じている、自分の表現能力に対する不安感、それがまさにせつなさじゃないか?」
「い、いきなりだね。でも、それは」
きゅっ、と胸元で拳を握りしめる副編集長。
「確かに、勝手に思い詰めて勝手に不安になっているところがあるかも。主観に支配されるな、視野を広げて客観的にならなきゃいけない、そう言いたいのかい?」
「それは、ウチの新聞部のモットー、記事を書くときの心得だろ。逆だ、逆。記事と違って、小説は、主観でいいんだ。主観をエンタメにするのが小説だ、とも言える。わからない、見えない、不安だ、っていうのがせつなさで、それは主観なんだから。主観をそのまま書けばせつなさになるんだよ。
俺は『想い出に追いかけられて』は面白いと思った。良く書けてるよ、それは嘘じゃない。でも、最初から違和感はあった、それは、副編集長がせつなさを感じてもらいたくて書いた、と言っていたからだ。せつなさには向いていない表現になっているな、と思った。なぜか?
せつなさを感じさせるには、情報が多すぎるんだ。知らないこと、見えないことが不安感になってせつなさになるのに、知らないはずのこと、見えないはずのことを全部、表現してしまっている。だから俺は、足り過ぎ書き過ぎ、表現しなくてもいいって言っている。
せつなさは主観だ。でも、この小説の描写は、客観的すぎるんだ。繰り返すけど、新聞の記事と小説は違う。小説は、主観でいいんだ。主観がいいんだ」
「ええ……」
副編集長は戸惑っている。
「それは。でも。この小説が一人称描写ならそれでいいかも知れないけれど。三人称で書いたんだから、客観的に書かないと」
良くある勘違いなんだなー、これが。
「僕は、私は、みたいに、主人公ないしは誰かの視点で語られるのが一人称描写、彼は彼女はみたいに客観的に書かれるのが三人称描写、と思われてるけど。
じゃあ、彼は、彼女は、って語っているのは、『誰』なんだろうな?」
編集長が苦笑いする。
「また意地の悪い言い方をするなーお前は。誰かわからない第三者、神様とか、あるいは作者自身、どっちにしても主観で、三人称描写=客観描写じゃないって言いたいんだろ?」
「正解。少なくとも俺は、三人称描写であっても、視点は想定して書いているし、Gさんから聞く限りでは同じようにしている作家さんがほとんどだ。
理由はふたつ。そうした方が書きやすいし、読みやすいから、だ。後者の理由のほうが大きいな」
「読みやすい?」
「そう。あー、前に、芽宮に説明したんだけど、副編集長も聞いてたよな? 俺が初めて書いた小説、『復讐のガンガール』な、あれの冒頭、Gさんにムチャクチャこき下ろされた。なんでこき下ろされたか、覚えてる?」
「確か……観た映画の映像を文章で再現しようとして、説明? になってしまっていて小説の表現になっていない、これでは伝わらない、ネットの駄文以下だ、みたいな話だったと記憶しているけど」
まあだいたいその通りなんだけど駄文以下とまでは言わなかったと思うんですけどーっ! もう昔の話なんだけど言われた時のショックを思い出してヘコみかけるが、今はそういう話の流れじゃないので平気な顔をしたまま話を続ける。
「あの時、俺はいろいろ考えたんだ。映像を文章に置き換えるんじゃ描写にならない、説明になってしまう。じゃあどうすれば描写になるのか? 面白いと感じた小説の文章を思い出して、考えた結果、俺なりの結論が出た。
絵を説明しようとするからダメなんだ。文章は絵じゃないんだから。文章でしか書けないもので勝負するしかない。それは何だ? 主観なんだ。絵では書けない、心の中、頭の中、感じたもの、考えていることを書くんだ。
俺は絵心はないから、綺麗な夕日の絵は描けない。でも、夕日を見たときの心の中を書いて、マンガや絵では出来ない事が出来る、マンガや絵に勝てる。
例えば時間は放課後、帰り道の途中だ。学校であった事を思い出しながら歩く。楽しかった? 辛かった? 一日の終わりに思うのは、もう、なのか、やっと、なのか、おっと夕餉の匂いがしてきたぞ、あそこの家はカレーかな、家に帰れば誰が待っているのか、賑やかなのか寂しいのか、それを書くのが小説だ。そういう主観描写で、読んだ人に、絵を使わずに夕日を美しいと感じさせるのが小説なんだ。
主観なんだから、見えないものは書かなくていいんだ。見えていても、主観の邪魔になるものはばっさり削ってしまっていい。削るべきだ。夕日を前に感慨に耽っている時に、実は夕日はゴミが浮いたドブ川の向こうに見えてますとか、夏の盛りだから夕日でも正面からだと顔が焼けそうですとか客観的な事を書いても意味がない、美しくないし、そもそもそんなものは夕日を美しいと感じる人の目には入ってない、主観において見えないものはないのと同じ扱いで構わないんだ」
「主観でいい、つまり」
副編集長は真剣な顔で、『想い出に追いかけられて』をゆっくりとスクロールさせている。
「主人公からは見えないもの、例えば他のキャラの、見えない情報は削らなくてはいけない?」
無意識に、にっこりしてしまう。さすが副編集長、もう正解を出した。
「主人公以外のキャラの主観描写な。とりわけ、()書きの心情台詞とかは、主人公以外のものは削った方がいい。『想い出に追いかけられて』では、主人公が書いた小説を読んだ事があるのかないのか、読んで面白いと思ったのかお涙頂戴の駄作だと思ったのか、そもそもそれを書いたのが主人公だと知っているのか。これは主人公の不安感を演出する重要な情報で、せつなさを感じさせるキモになる。主人公の主観では絶対に出てこない情報なんだから。主人公が気になっているけど聞けない、そこをバラしちゃったら台無しだろ?」
「それは。そうかもだけど。少し待ってほしいな、考える、それで書いたとしたら」
掌をこっちに向けて目を閉じる副編集長。頭の中で完成形をシミュレートしているんだろう。俺もよくやる。
「駄目だな、それじゃあ、話のトーンが暗くなってしまう。他人が見えなくて、わからなくて不安になる主人公に引っ張られて、読者まで不安になって。……あっ」
副編集長はぱちっと目を開く。
なんか空気が妙だぞ? お互いに様子をうかがい合ってる感じ。
芽宮以外の四人は、放課後にはここで毎日顔を合わせているんだが、この一週間、特に福地の様子が可笑しかった。何かを言おうとして、呑み込む、でも黙ってもいられない、そんな感じ。副編集長の小説を読んで、感想を語りたい、あるいは言いたいことがある、でも、全員が集まってからって決まっているから、先走りして語るのもはばかられる、そう思っているのがまるわかり。
空気が妙なのは、編集長も副編集長もそんな福地を見ているから、口火をきりにくい感じ。見ていない芽宮も、彼女は場を読めるから、澄ました顔で様子をうかがっている。
しょうがないなー。俺から行かせてもらいますか。
「面白かったよ。正直、予想以上だった。副編集長のこと、ちょっとナメてたな。こんな小説が書けるとは思ってなかった、ゴメンな。でも、すごいよ。楽しめた」
副編集長は、ちょっと驚いたようだ。目が少し大きくなる。
「本当に? お世辞ではないんだよね?」
「俺は小説に関しては嘘はつかないぞ。あ、書く小説の中じゃあ嘘つきまくりだけど。
この小説も、嘘のつきかたが上手い。悪い意味じゃないぞ、小説表現が上手いってことだ」
「あ、ありがとう?」
「まず冒頭。主人公の独白で始まるってのはよく使われる手法ではあるけれど、よく使われるのはそれだけ効果的だからだ。
高校3年の女の子の登校風景、今朝は夢見が悪くてちょっと寝不足、彼女は夢の内容を思い出して、憂鬱になっている。夢の中で彼女はまだ中学生、軽い気持ちで書いた小説を、試しに投稿サイト載せてみたら、これがものすごい評判になって商業出版されて映画にもなる。そんな夢だ。
彼女を憂鬱にさせているのは、この夢が本当にあったことだからだ。書いた小説も、部分的には本当の話だった。二つ違いの、幼いときに交通事故で死んでしまった兄との想い出、中学生になった彼女は、文章を綴るのが好きだったから、兄が生きていたという事を、優しくていい兄だったという事を小説という形で残そうとしたんだ。そして、それは意外な程たくさんの人に読んでもらえた。
ここまでなら別に憂鬱にはならない。いい話だよな? でも、いい話では終わらなかった。たくさんの人が読んで、いろいろに評価されて、ドラマや映画になるうちに、彼女だけのものだった想い出は彼女の手から離れてしまう。想い出の中にはいいことも悪いこともあったのに、いいことだけを取り上げて持ち上げる、感動した、泣いた、と絶賛する人がいる。一方で、お涙ちょうだいの、ありがちな、手垢の付いたストーリーの駄作だ、と酷評する人がいる。
読んだ人の中で、想い出が変わっていく。そうすると、彼女自身も思い出を信じられなくなってしまう。想い出は、本当にあったことだと信じるままに書いて小説にしたけれど、所詮は中学生の夢想、ただの綺麗事になってしまっているんじゃないか? そんなものを残されても、兄だって困るだけなんじゃないか? 自分の想い出の価値がどんどん信じられなくなっていく、そもそも小説なんて、嘘ばっかりじゃないか。
そんな風に、彼女は憂鬱なんだ。
いい。引き込まれる。幼少期、中学生、そして現在、それぞれの主人公が幸せだったり憂鬱だったり、明暗、起伏たっぷりに表現されているのがいいな。単純じゃない魅力がある。いい案配の不安定感も演出できて、これから彼女がどうなるのか、という期待感もあおってくれる。見本にしたいような冒頭だよ」
「ありがとう」
ちょっと赤くなった副編集長は視線を泳がせている。
「そこはもちろん、そう計算して書いたからね。それくらいは、私にだって書けるんだよ」
うーん初々しいなあ。そう、伝えたかったことが伝わるってのは、嬉しいよな。わかるわー。
「小説に夢を持てなくなったけど、文章は綴りたいから新聞部、って動機付けになってるのも面白いよなー。強引に見えて自然な感じになっちゃうのが不思議。これがキャラクター性ってのかな? うん、俺も楽しく読めたよ。俺らなんかモデルにして小説になるのかと思ったけど、ちゃんとなってるのがなにより驚きだよな」
「後輩キャラがちょっとチャラ過ぎて最初は抵抗あったんスけど。あ、いや、わかってますって、現実とフィクションをごっちゃになんてしないっスから! でもこう、思いっきりデフォルメされた似顔絵みたいな感じで読んだら、意外と楽しめちゃったんスよね。そういうのもダメッスか?」
それくらいならいいんじゃないかなー。お前はまだいいじゃないか。俺がモデルになったキャラなんて、キャラの一部、作家要素を副編集長に盗られた上に、主人公にとって「生理的に合わない異性」扱いだぞ。不本意にもほどがある。
でもこれはフィクションだから! 現実じゃないから! そんなことはわかってる、俺はプロだぞ!? だから文句は言わない。さすが俺。
とか思っていたら。
「それでいいんですか? みなさん」
芽宮だ。なんか、怒ってる? 声が固い感じ。
「もちろん、同じ部の仲間である副編集長さんのことを気遣ってそう言っているのはわかります。でも、わたしは新聞部じゃない部外者で、なにより、演技という表現の、まだ修行中ですけど、一応プロなんです。表現についての意見を求められたら、嘘はつきにくいんです。
編集長さんかセンパイか福地君のだれかが言ってくれるなら、それでも良かったんですけれど。みなさんが言いにくいなら、それはわたしの役目だと、わたしが決めました」
あちゃあ。これは予想しなかった。俺が言わなかったことについて、切り込むつもりだ、芽宮が。
驚くと同時に、俺は納得もしていた。そうだよな、芽宮は毎日のように、カントクに演技をしごかれてるんだもんな。しごかれて、上手くなっているという自覚もあるんだろう。自分に厳しいから、他人にも厳しい。相手が本気であればあるほどそうなる。芽宮は、副編集長が本気だと判断したんだろう。本気には本気で応えなくてはならない、そう決めたんだ。そこが俺との違いだ。
「え、ゴメン、どういうことか、わかんないンだけど、宮城ちゃん?」
「ちょっと力みすぎじゃないかなー? 言いたいことはわかるけど、ちょっと落ち着こうぜ?」
福地はわかってない。編集長はさすがに理解してるようだ。
「落ち着いてます、ううん、落ち着いてないかも? 副編集長さんを傷つけてしまうかもしれないから、言いたくないけど、でも、言わなきゃいけないんです。
副編集長さん、わたし、『ブルーワールド』も読んでみたんです。電子化もされてないから読めないかな、と思ったんですけど、古本屋にあったので。副編集長さんの言った通り、せつなくて、せつなくて、わたしも泣いちゃいました。
『想い出に追いかけられて』、副編集長さんの書いた小説も、面白かったです。
でもですね、せつなさは感じませんでした。これが不思議なんです。面白いのに、せつなくない。
泣けないんですよ、せつなくないから。まったく。涙一滴すら出ませんでした。
副編集長さんは言いましたよね? 『ブルーワールド』のせつなさに不意打ちされて、自分でも表現してみたくなった、って。表現したかったのはせつなさじゃないんですか? せつなさは表現できましたか? わたしに読み取る力がない、というのならそれでいいんですけど。
副編集長さん、自分で書いたこれを読んで、あなたはせつなくなるんですか?」
うわ、キッツいなー。横で聞いているだけなのに胸にちくちくと来る。見ろよ福地の顔が引きつってるぞ。同性同士ってのもあるかもしれないが、芽宮自身がカントクに、こんな感じでしごかれてるってのがデカいんだろうな。言葉が丁寧になってはいるが、それが余計に印象を厳しいものにしている気がする。芽宮にそういう意図はないだろうが。
「そう言われる可能性は、考えていたんだ。これは本当だよ?」
副編集長の声も固い。
「言うなら布留田君かな、と思っていたんだけれど。それは外れたかな」
「そうですね、わたしもセンパイがずけずけ言ってくれるのを期待してたんですけど。ちょっとがっかりです」
おーい、キミタチ? 勝手な予想や期待はしないでほしいかなー、なんて思うんだが。ずけずけとかがっかりとか、そもそも俺をどういう性格だと思ってるんだ。
「うん、せつなさを表現したつもりだったのに、読み返してみてもせつなくない。でもそれは、手品師がトリックを知っているみたいなもので、知らないだれかに読んでもらえばひょっとして、とも思ったんだけど」
副編集長に視線で促されて、福地はぶんぶんと首と手を振る。
「いや、オレはそもそも、そういうの小説に求めてないし、わかんないッスよ! せつなさとかって、女性向けっしょ!?」
編集長は肩をすくめた。
「読んで、楽しめた。それで満足してちゃおかしいか? それでいいと思うんだけどなー?」
「ありがとう。でもね、私が表現したかったのは、せつなさなの」
雰囲気が、場の空気が。重いっ!
副編集長が困っているなら、アドバイスをしようと思っていた。その内容だってちゃんと考えてある。別に難しい話じゃないんだ。副編集長の今の状況は、ボタンをひとつ掛け違えた間違えたみたいなモンで、どこを間違えたか指摘するだけのアドバイスだ。そんなんすぐに直せるじゃないか。
だがしかし。困り方が想定以上に深刻だ。落ち込んでいる。今の副編集長の顔を見て、
「そんなキミに、目からウロコのワンポイントレッスン! これでキミの悩みもスッキリ解決!」
とは言えない。どうすりゃいいんだこの空気?
「思い上がってたのかな、自分だって表現できるなんて。これでもけっこう本気で書いたのにね。なにが足りないのかもわからない、私には」
いや、そうじゃなくて、と思っていたら。
「大丈夫です! わたしだってわからないけど、センパイがいます! プロの作家の! ね、センパイ」
芽宮がハードル上げるし。いや上げきっていたのをさらに積んでくるし。
「なにが足りないのか、センパイはわかりますよね?」
でもまあ。勢いは作ってくれたから、その流れに乗せてもらおう。後輩の期待には応えなくちゃだしな。
「逆だよ。足りないんじゃない、足り過ぎなんだ。書き過ぎなんだよ。せつなさを表現しようとしても難しい。だったら、表現しなければいいんだ。それがせつなさになる」
場の空気変えるために、あえて謎かけみたいな言い方をしてみた。副編集長も含めて、思い詰めたような顔をしていたみんなが驚いたような、呆れたように顔をしているから、まあ、狙い通り。
「だから、思い詰めなくていいんだ。ちょっと勘違いしてるだけなんだから。副編集長にだって表現できるさ、せつなさを」
芽宮は嬉しそうにうんうん、と頷いている。さすがセンパイ、と言いたいんだろうが、なんか顔が自慢げで、愛弟子の活躍を見守る師匠、みたいな感じにも見えるから、自重しよう? 別にたいしたことは言ってないから、持ち上げてくれるなよ、くすぐったくて逃げ出したくなる。
「表現しなくていいって言ってみたりできるって言ってみたり、どっちなんスかね?」
「まー、ケースバイケースなんだよ、いろいろとさ。だから論点をはっきりさせよう。
副編集長はせつなさを書きたかった。でも書けなかった。なにがいけなかったのか? そういう事だよな。
さて、じゃあそもそも、せつなさって何だ? さっき福地は、せつなさは女性向けだ、みたいに言ってたよな? どういうところが女性向けだ? どういうのがせつなさだと思ってそう言った?」
「だからわかんないンだって……そうッスねえ、何となくですけど、少女まんがにあるような、この想いをあの人に伝えたいのに伝わらない、せつない、みたいな?」
「編集長は? どう思う?」
「そうだなー」
腕組みして天井を仰ぐ編集長。
「福地の言う、女性向けってのも間違ってはないと思うぞー。俺みたいな男が、せつない、って言っても笑われる気がするし。あーそうか、中高生の女の子が似合う感じだよな。こう、心も身体も、そして周囲の環境も急にいろいろ変わっていく中で、自己認識がぐらぐら揺れる感じ、変わっていく、見えない、予測できない不安感、みたいな?」
「OKOK。
つまり、せつなさは、不安感なんだ。思春期独特の、他人や社会との関係性、見通せない将来、確立していない自己肯定感、あらゆるものに感じている不安感全て、それがせつなさになる。
例えばだ、副編集長が、今まさに感じている、自分の表現能力に対する不安感、それがまさにせつなさじゃないか?」
「い、いきなりだね。でも、それは」
きゅっ、と胸元で拳を握りしめる副編集長。
「確かに、勝手に思い詰めて勝手に不安になっているところがあるかも。主観に支配されるな、視野を広げて客観的にならなきゃいけない、そう言いたいのかい?」
「それは、ウチの新聞部のモットー、記事を書くときの心得だろ。逆だ、逆。記事と違って、小説は、主観でいいんだ。主観をエンタメにするのが小説だ、とも言える。わからない、見えない、不安だ、っていうのがせつなさで、それは主観なんだから。主観をそのまま書けばせつなさになるんだよ。
俺は『想い出に追いかけられて』は面白いと思った。良く書けてるよ、それは嘘じゃない。でも、最初から違和感はあった、それは、副編集長がせつなさを感じてもらいたくて書いた、と言っていたからだ。せつなさには向いていない表現になっているな、と思った。なぜか?
せつなさを感じさせるには、情報が多すぎるんだ。知らないこと、見えないことが不安感になってせつなさになるのに、知らないはずのこと、見えないはずのことを全部、表現してしまっている。だから俺は、足り過ぎ書き過ぎ、表現しなくてもいいって言っている。
せつなさは主観だ。でも、この小説の描写は、客観的すぎるんだ。繰り返すけど、新聞の記事と小説は違う。小説は、主観でいいんだ。主観がいいんだ」
「ええ……」
副編集長は戸惑っている。
「それは。でも。この小説が一人称描写ならそれでいいかも知れないけれど。三人称で書いたんだから、客観的に書かないと」
良くある勘違いなんだなー、これが。
「僕は、私は、みたいに、主人公ないしは誰かの視点で語られるのが一人称描写、彼は彼女はみたいに客観的に書かれるのが三人称描写、と思われてるけど。
じゃあ、彼は、彼女は、って語っているのは、『誰』なんだろうな?」
編集長が苦笑いする。
「また意地の悪い言い方をするなーお前は。誰かわからない第三者、神様とか、あるいは作者自身、どっちにしても主観で、三人称描写=客観描写じゃないって言いたいんだろ?」
「正解。少なくとも俺は、三人称描写であっても、視点は想定して書いているし、Gさんから聞く限りでは同じようにしている作家さんがほとんどだ。
理由はふたつ。そうした方が書きやすいし、読みやすいから、だ。後者の理由のほうが大きいな」
「読みやすい?」
「そう。あー、前に、芽宮に説明したんだけど、副編集長も聞いてたよな? 俺が初めて書いた小説、『復讐のガンガール』な、あれの冒頭、Gさんにムチャクチャこき下ろされた。なんでこき下ろされたか、覚えてる?」
「確か……観た映画の映像を文章で再現しようとして、説明? になってしまっていて小説の表現になっていない、これでは伝わらない、ネットの駄文以下だ、みたいな話だったと記憶しているけど」
まあだいたいその通りなんだけど駄文以下とまでは言わなかったと思うんですけどーっ! もう昔の話なんだけど言われた時のショックを思い出してヘコみかけるが、今はそういう話の流れじゃないので平気な顔をしたまま話を続ける。
「あの時、俺はいろいろ考えたんだ。映像を文章に置き換えるんじゃ描写にならない、説明になってしまう。じゃあどうすれば描写になるのか? 面白いと感じた小説の文章を思い出して、考えた結果、俺なりの結論が出た。
絵を説明しようとするからダメなんだ。文章は絵じゃないんだから。文章でしか書けないもので勝負するしかない。それは何だ? 主観なんだ。絵では書けない、心の中、頭の中、感じたもの、考えていることを書くんだ。
俺は絵心はないから、綺麗な夕日の絵は描けない。でも、夕日を見たときの心の中を書いて、マンガや絵では出来ない事が出来る、マンガや絵に勝てる。
例えば時間は放課後、帰り道の途中だ。学校であった事を思い出しながら歩く。楽しかった? 辛かった? 一日の終わりに思うのは、もう、なのか、やっと、なのか、おっと夕餉の匂いがしてきたぞ、あそこの家はカレーかな、家に帰れば誰が待っているのか、賑やかなのか寂しいのか、それを書くのが小説だ。そういう主観描写で、読んだ人に、絵を使わずに夕日を美しいと感じさせるのが小説なんだ。
主観なんだから、見えないものは書かなくていいんだ。見えていても、主観の邪魔になるものはばっさり削ってしまっていい。削るべきだ。夕日を前に感慨に耽っている時に、実は夕日はゴミが浮いたドブ川の向こうに見えてますとか、夏の盛りだから夕日でも正面からだと顔が焼けそうですとか客観的な事を書いても意味がない、美しくないし、そもそもそんなものは夕日を美しいと感じる人の目には入ってない、主観において見えないものはないのと同じ扱いで構わないんだ」
「主観でいい、つまり」
副編集長は真剣な顔で、『想い出に追いかけられて』をゆっくりとスクロールさせている。
「主人公からは見えないもの、例えば他のキャラの、見えない情報は削らなくてはいけない?」
無意識に、にっこりしてしまう。さすが副編集長、もう正解を出した。
「主人公以外のキャラの主観描写な。とりわけ、()書きの心情台詞とかは、主人公以外のものは削った方がいい。『想い出に追いかけられて』では、主人公が書いた小説を読んだ事があるのかないのか、読んで面白いと思ったのかお涙頂戴の駄作だと思ったのか、そもそもそれを書いたのが主人公だと知っているのか。これは主人公の不安感を演出する重要な情報で、せつなさを感じさせるキモになる。主人公の主観では絶対に出てこない情報なんだから。主人公が気になっているけど聞けない、そこをバラしちゃったら台無しだろ?」
「それは。そうかもだけど。少し待ってほしいな、考える、それで書いたとしたら」
掌をこっちに向けて目を閉じる副編集長。頭の中で完成形をシミュレートしているんだろう。俺もよくやる。
「駄目だな、それじゃあ、話のトーンが暗くなってしまう。他人が見えなくて、わからなくて不安になる主人公に引っ張られて、読者まで不安になって。……あっ」
副編集長はぱちっと目を開く。
メッセージを送る!